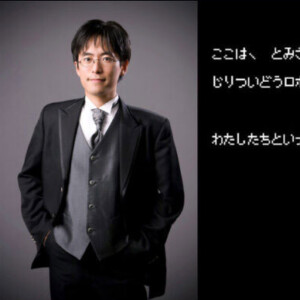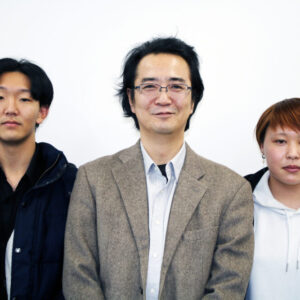高専時代に教員に憧れて進学の道を選び、2022年に岐阜工業高等専門学校・環境都市工学科に着任した井向日向先生。高専時代に土木の魅力を知った井向先生が専門とするコンクリートの話や、現在に至るまでの足跡についてインタビューしました。
土木の魅力は、スケールの大きさ
―高専へ進学した理由を教えてください。
建物をつくることに興味があり、家を建てている現場は小さい頃から何度か目にしていました。ですので、研究職志望ではなく建築の仕事に早く就きたいと考えていましたね。
高専への進学を勧めてくれたのは、大工として働いていた父でした。「専門的な知識を身に付けるなら」と、建築士への道が最も早かった福井高専の環境都市工学科のことを教えてくれたので、自分なりにモチベーションを持って受験したことを覚えています。
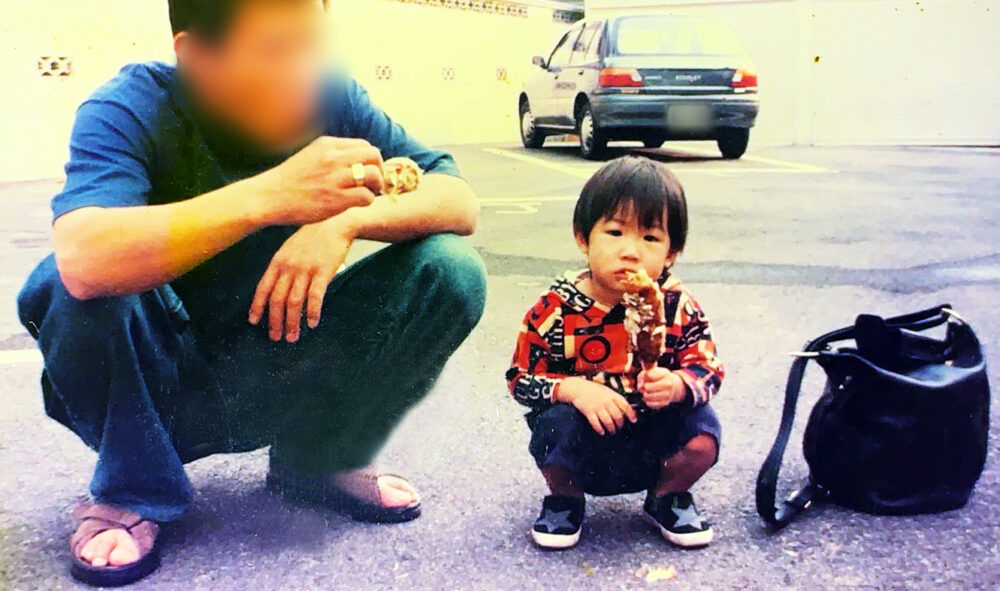
福井高専は、土木も建築も複合的に学べるのが特徴です。私自身、最初は建築士を目指していたのですが、勉強していくうちに「なんだか違うな」と思うようになりました。
その一方で、土木の勉強が楽しくなってきたんです。家よりも大きな橋をつくることができるし、構造分野の勉強もおもしろい。「計算でこんなことができるんだ!」と夢中になっていきました。

また、3年生の頃くらいから友達に勉強のことで頼られることが多くなり、その経験の中で教える楽しさを知りました。自習時間に黒板を使って解説したり、「これ、どういうこと?」と聞かれてわかりやすく説明したりしていましたね。
さらに、専門の授業が増えてから、先生方と話す機会も増えました。高専の先生の専門性の高さと見識の広さに憧れて「高専の先生になろう!」と思い、大学・大学院博士課程への進学を志しました。
鯖江市にある高専へは、地元の福井市から電車に乗り、片道1時間くらいかけて通っていましたね。勉強も忙しかったのですが、中学から続けていた卓球部にも所属していたので、部活動にも熱心に取り組みました。課外活動では、3年生の頃から全国の高専のデザインコンペティション「デザコン」に出場していたことも良い思い出です。

―進学先はどのように決めたのでしょうか。
長岡技術科学大学を選んだ理由は多々ありますが、例えば高専との連携コースがあり、高専とのつながりが強い大学であった点や、長期のインターンシップがあり、実務上の問題を認識してから大学院の研究に臨める点に魅力を感じました。留学生が多く、さまざまな文化に触れたり英語力を磨いたりできること、授業料免除などの経済的支援が多く見込めそうだったことも志望理由の1つです。
大学院は、同大学でできたばかりの技術科学イノベーション専攻(5年一貫制博士課程)に進学しました。この専攻では学科を問わず学生を受け入れており、修士・博士の一貫教育を実施しています。大学に進学した目的が博士課程に進んで高専の教員になることだったので、さまざまな機会に恵まれている同専攻に進学しました。

大半の学生にとって、高専卒業後の進学の目的は研究のためですが、私の場合は「高専の先生になること」でした。しかし、ユニークな道を進むことは不安というより、むしろ楽しみでしたね。技術科学イノベーション専攻を選択した時も同様で、「人と違う進路を選びたい」と考えるタイプ(笑) ただ、「挑戦できる機会が多い場所を選ぶ」ということは大切にしていました。
教員を目指す一方で、研究にも没頭
―大学・大学院での研究はいかがでしたか。
大学で出会った研究室の先生は、コンクリートの分野ではトップリーダーで、業界の第一線で活躍されている方でした。目標は「高専の先生になること」でしたが、いざ研究をはじめると、詳しく知りたくなるものですよね。高専時代、デザコンの引率に来ていた先生に誘われてコンクリート製の建物や橋梁の構造解析の研究をしていたこともあり、そのままコンクリートの分野にのめり込みました。

私が専門とするのは、コンクリートの「クリープ」と呼ばれる現象です。「クリープ」は英語で「ゆっくり進む」という意味。力を加えられているコンクリートが、時間をかけて変形していく現象を研究しています。
例えば橋梁の場合、橋の重さやクルマの移動などの力が加わり続けると、ゆっくりとたわんできます。また、最近は「プレストレストコンクリート」というあらかじめプレスされた組み立て式の素材が使われるため、特にたわみが起こりやすくなるんです。こうした現象を予測して安全な状態を保つには、クリープの現象を精度よく見積もることが重要です。
そのために、研究室内で状況を再現して実験をしています。具体的には「直径10cm、高さ20cmくらいの円柱型のコンクリートを圧縮し続ける」という実験です。その経過を1週間、1カ月間単位で調査して、現場に応用することになります。

クリープの研究は1980~90年代に日本で流行った研究分野で、上の世代には技術者・研究者ともにたくさんいらっしゃるのですが、一方で若手が少なくなっています。大学4年生の頃、恩師である先生から「せっかくならクリープを究めなさい」と声を掛けていただいたこともあり、今後もこの分野で研究を続け、世代をつなぐ役割を果たしたいと考えています。
―海外留学についてもお聞かせください。
高専5年生の時、長岡技大との連携コースがあり、ベトナムに1週間行ったのが最初です。現地では海外支店のある企業を訪ねて技術者の生の声を聞き、素直に「かっこいいな」と感激しました。ハノイ工科大学の学生と交流する機会もあり、大いに刺激を受けましたね。

2度目の海外は、大学3年生の冬、1~2月の時期です。この時期は授業がほとんどなく、各自がアルバイトや企業インターンで自分の時間を有効に使うといった慣例があったので、海外に行くことにしたのです。
ベトナムに行った頃は、まだ専門知識が十分にはなかったので「もっと力をつけて海外に行きたい」と感じていました。海外の学生のモチベーションや知識、語学力の高さや将来に対する考え方などに刺激を受けて少し悔しい思いをしたことも、2度目のチャレンジのきっかけです。また、1週間という短期間ではなく、もっと自由に時間を使って勉強したいという思いもありました。
留学先のインド工科大学マドラス校は学生の知識レベルが高く、語学も計算もみんな得意。設備も優れていて、先生もすごい方ばかりです。ただ、現地での暮らしは……“サバイバル”でしたね(笑) できたばかりのきれいな寮に入ったのですが、トイレ4つのうち3つは壊れているし、シャワーは水しか出ない、洗濯は手洗いのみ、しょっちゅう停電する。不便ばかりでしたが、とても良い経験でした。

レポートのコメントはしっかりと
―夢が実現して高専の先生に。指導で気を付けていることはありますか。
実験系の科目が多く、レポートが評価の重点になるので、コメントをたくさん残すようにしています。私自身、高専時代に先生のコメントを読むのが楽しみでしたし、授業に興味を持つきっかけにもなりました。レポートの最後に設けている「感想」の欄は、学生たちがたくさん書いてくれるので、毎回読むのを楽しみにしています。

卓球部の顧問も担当しているので、放課後はだいたい部活動の様子を見に行きます。自分も卓球が好きで大学までずっと続けていたし、学生と一緒にスポーツができる機会は貴重ですよね。これまでの部活動でたくさんの先輩や後輩、仲間ができたし、大学生の頃に指導していた地域のスポーツクラブで出会った人もたくさんいるので、コミュニケーションのうえでも大切だと実感しています。

現在部員は30人くらいで、すごく良い雰囲気で練習していると思います。他の選手の試合を見ながら課題を見つけたり、問題を改善したり。私が何もしなくても、学生たちは主体的に練習や試合に取り組んでいます。その分、私自身もきちんと応援したいし、「しっかりとサポートしなければ」と身が引き締まる思いです。
.jpg)
―現役&未来の高専生へメッセージをお願いします。
人に負けない知識や得意になって話せることがあると、将来きっと役立つはずです。また、機会があれば海外に行くことをおススメします。自分のルーツや日本の歴史・文化についてよく聞かれるので、知っておくとコミュニケーションが取りやすいと思いますよ。
計画を立てたら諦めずに、何事にも全力で。もし高専に入学したら、ぜひ気軽に話しかけたり、研究室に遊びに来たりしてくださいね!
井向 日向氏
Hyuga Imukai
- 岐阜工業高等専門学校 環境都市工学科 助教

2015年3月 福井工業高等専門学校 環境都市工学科 卒業
2017年3月 長岡技術科学大学 工学部 建設工学課程 卒業
2022年3月 長岡技術科学大学大学院 工学研究科 5年一貫制博士課程 技術科学イノベーション専攻 修了
2022年4月より現職
岐阜工業高等専門学校の記事



アクセス数ランキング

- 研究職からプロアドベンチャーレーサーに転身! 「自分の選んだ道こそが正解」と胸を張って言える人生に
- プロアドベンチャーレーサー
イーストウインド・プロダクション 代表
田中 正人 氏


- 高専は何でも学びになるし、人間としての厚みが出る。「自立して挑戦する」という心意気
- 黒田化学株式会社 グローバル品質保証部 品質管理課
宮下 日向子 氏

- 養殖ウニを海なし県で育てる! 海産物の陸上養殖普及に向けて、先生と学生がタッグを組む
- 一関工業高等専門学校 未来創造工学科 化学・バイオ系 教授
渡邊 崇 氏
一関工業高等専門学校 専攻科 システム創造工学専攻1年
上野 裕太郎 氏
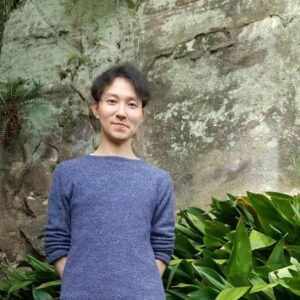
- 「突き詰めたい」という気持ちが原動力。地域の人たちと地理、観光開発の関係性を解き明かす観光地理学
- 東京都立産業技術高等専門学校 品川キャンパス ものづくり工学科 一般科 助教
朝倉 槙人 氏

- 「工学」+「数学」=「無限の可能性」!? 数学のプロが考える、これからのモノづくり
- 佐世保工業高等専門学校 電子制御工学科 准教授
濵田 裕康 氏
-300x300.jpg)
- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと
- 鹿児島工業高等専門学校 校長
上田 悦子 氏

- 苦手分野を研究に⁉“昆虫好き少年“がたどり着いた「工学×生物」という新たな道
- 佐世保工業高等専門学校 電子制御工学科 助教
松田 朝陽 氏


- 高専生が多色ボールペンで特許申請!自ら抱いた疑問を自ら解決する「自主探究」活動とは
- 八戸工業高等専門学校 総合科学教育科 教授
馬渕 雅生 氏
八戸工業高等専門学校 産業システム工学科(電気情報工学コース) 教授
中村 嘉孝 氏