
石川高専専攻科をご卒業後、福井大学大学院に進学され、今もなお「子どもの遊び環境」について研究を続けている福井大学准教授の粟原知子先生。建築学科から教育に関わる分野にどうやって展開したのか、そしてご自身が子育てをする中でどんな気付きがあったのか、お話を伺いました。
受験問題が面白いなら、授業もきっと面白いはず!
―高専を目指したきっかけを教えてください。

きっかけは父から薦められたことでした。私自身は高専という存在をそれまでまったく知らず、将来の夢や希望する進路も特にないまま、中学校生活を送っていたんです。今思えば、そんな私を見かねて、父は進路を示してくれたのかもしれません。高専を知ってからは、自由な校風や独特な学習環境に心惹かれるようになりました。
特に魅力的だったのは「受験問題」でした。受験の際に、それまでの模試とはまったく違って「解くのが面白い!」と感じました。高校受験の問題はどれも同じような形で、試験のために覚えたことをひたすら解いていくだけ。でも、高専の問題は自分の頭で考える必要があったし、知的好奇心をくすぐられる問題だったんです。
こんなに面白い問題をつくってくれるなら、学校に入ればきっと面白い授業が受けられるんじゃないか? そう期待して進路を決めました。
―実際には、いかがでしたか?

先生の研究や専門分野を話してくれる授業が、とても面白かったですね。それぞれ研究している分野が専門的で、自身の研究テーマについて話してくださるので、まるで大学の授業みたいで飽きることがありませんでした。
たとえば、国語の先生は作家・村上春樹を研究している方で、授業でもよく村上作品が取り上げられました。この授業を受けてからすっかり村上春樹の文章に魅せられて、彼の著作物は読破しました。
他にも、歴史の先生が地元・津幡町の歴史や町名の由来を教えてくださったり、数学の先生が魔方陣について話してくださったりと、すごくマニアックなんですが、それが余計に面白くて。高専一年生の頃から「先生が楽しく授業をしている」のが当たり前の光景でした。
もし、普通の進学校に行っていたら、こんな授業は受けられなかっただろうし、高校でも「受験のための勉強」をしていたかもしれません。私はそれが嫌だったので、高専に進んで大正解だったと思います。
建築の分野から、子どもの環境にアプローチ
-大学院に入学したきっかけを教えてください。

5年生のときに卒業研究に取り組み、研究の面白さに目覚めたんです。本当は卒業したらすぐに就職するつもりで高専に入ったのですが、5年生になっても社会にでるイメージが湧かず、そのまま研究の道を選びました。
私が所属していたのは建築学科でしたが、「環境が人の心に及ぼす作用」に興味があって、先生から「心理学に興味があるなら、子どもの遊び空間をテーマにしてみたら?」と言っていただいたんです。

ちょうどその頃に読んでいたのが『子どもとあそび:環境建築家の眼』(仙田満 著)という本で、著者の仙田さんは建築家だったんです。心理学や幼児教育は発達心理学の分野だと思っていたのが、建築からもアプローチできるんだというのが驚きでした。
本の中では、「子どもが遊べなくなったのは都市の変化が関係している」と解説されていて、子どもがいかに環境に影響を受けるかを知り、ますます興味が湧きました。

先生も「あなたは子どもに好かれるから、向いているんじゃない?」と背中を押してくださいました。私はなぜだか、昔から子どもやお年寄りから好かれるタイプで、街を歩いていても、よく声をかけられるんです(笑)。
私自身も子どもと接するのが好きなので、学童保育でアルバイトをしながら調査研究をさせてもらうようになりました。高専時代は学童保育、大学院時代は障害者施設でアルバイトをしながら現場での感覚を培い、社会人となった今でも「子どもの遊び環境」について研究を進めています。

子育てを通して芽生えた、新たな視点
―遊びの重要性とは、どんな部分でしょうか。

心の余裕だと思うんです。余裕という意味での「遊び」も、Playという意味での「遊び」も、どちらも豊かな人生を送るために欠かせない要素です。ルールがガチガチに決まっていれば、一度失敗すると心がくじけてしまったり、人間関係がギスギスしたりします。余裕がないと先行きが不安で、心のバランスを崩したりもしますよね。
コロナ禍で心を病む人と、そうでない人の違いも、ここにあるんじゃないかと思います。遊びは「ここまでやって大丈夫」という自分の範囲を広げる行為です。子どもの頃に遊びの経験が少ないと、大人になって自分の自由な範囲が掴みづらくなってしまう。未知の状況に置かれても、いかに自分らしく楽しく生きられるかは、心の余裕にかかっていると思うんです。
だからこそ、子ども時代の遊びを通して「どんな状況でもその場を楽しむスキル」「置かれた環境を力いっぱい楽しむ能力」を、鍛えることが必要だと考えています。
-先生は現在、子育て中だそうですね。

ええ、6歳と8歳の子育て真っ最中です。今まで子どもに関する研究を続けてきて理想像があったんです。でも、現実にはなかなかうまくいかないんですよね。宿題をしないで学校に行けば先生に怒られるので、遊ぶ時間を減らしても宿題をさせなくちゃいけないし、遊ぶ場所がないからといって、山奥に引っ越すわけにもいきません。
研究者として「こうしたい」という思いはあっても、自分の子どものこととなると、なかなか実践できず、理想と現実のギャップに頭を抱えることがあります。また、目の前で成長していく子どもたちを見ていて、子どもをとり巻く環境について新たな問題意識が芽生えたりもしています。

大学で研究を続けていくのが良いのか、実際に子どもが生活している現場に入り、実践家として実証研究を目標にするのが良いのか、この先進むべき道についても検討しているところです。
-最後に受験生や現役の高専生に、メッセージをお願いします。

私は高専を卒業した後、大学院へ進み、現在は国立大学に所属しています。大学院が高専と大きく違う点は、日本全国・海外からも学生が集まってきている点です。学会にも多数所属し、学際的な視点で研究を進めることができました。研究の視野だけでなく、自分の人生をどう生きていくのか、あらためて考える時間をいただいたとも感じています。
私自身の経験を振り返ってみると、受験に合格するためだけの勉強に時間を使わず、面白いと思えることを勉強していたら大学院にいた、という感じかもしれません。大学院には10年ほど在籍していたので、社会に出る準備にすごく時間をかけてしまいましたが、今は毎日仕事を楽しんでいます。
みなさんも「楽しい」「面白そう」と感じることに素直になって、じっくり進路を考えてみてくださいね。

粟原 知子氏
Tomoko Awahara
- 福井大学 国際地域学部 准教授

2000年 石川工業高等専門学校 建築学科 卒業
2002年 石川工業高等専門学校 専攻科 環境建設工学専攻 修了
2004年 福井大学 工学研究科 ファイバーアメニティ工学専攻 博士前期課程 修了
2007年~2010年 アイビー医療福祉専門学校 非常勤講師
2010年 福井大学 工学研究科 ファイバーアメニティ工学専攻 博士後期課程 単位取得満期退学
2010年~2017年 大原学園福井校 非常勤講師
2011年 福井大学 教育地域科学部附属地域共生プロジェクトセンター 助教
2016年 福井大学 国際地域学部 講師
2021年 福井大学 国際地域学部 准教授
石川工業高等専門学校の記事

-290x300.jpg)

アクセス数ランキング


- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について
- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教
藤田 健太郎 氏



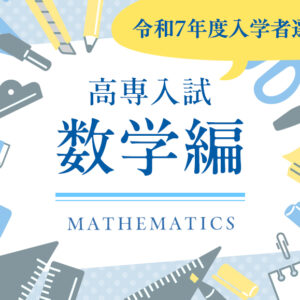

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む
- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教
久保田 翔大 氏
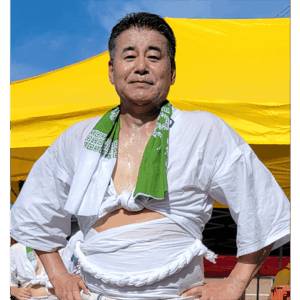
- 光学デバイスの研究から大学発ベンチャーへ。研究と事業をつなぐ「橋渡し役」としての歩み
- 株式会社オプトプラス 代表取締役
小田 正昭 氏












