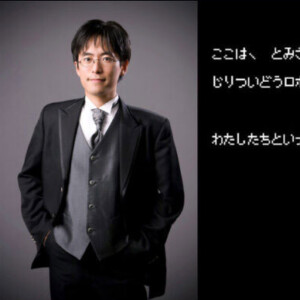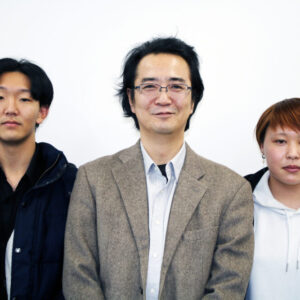心疾患や認知症の原因にもなり得るタンパク質の研究を進める、室蘭工業大学大学院工学研究科の徳楽清孝先生。2021年に英科学誌『ネイチャー』にも掲載された論文についてなど、最新の生物化学の応用研究について伺いました。
「生物」と「情報」を糸口に
―高専に進学されたきっかけを教えてください。
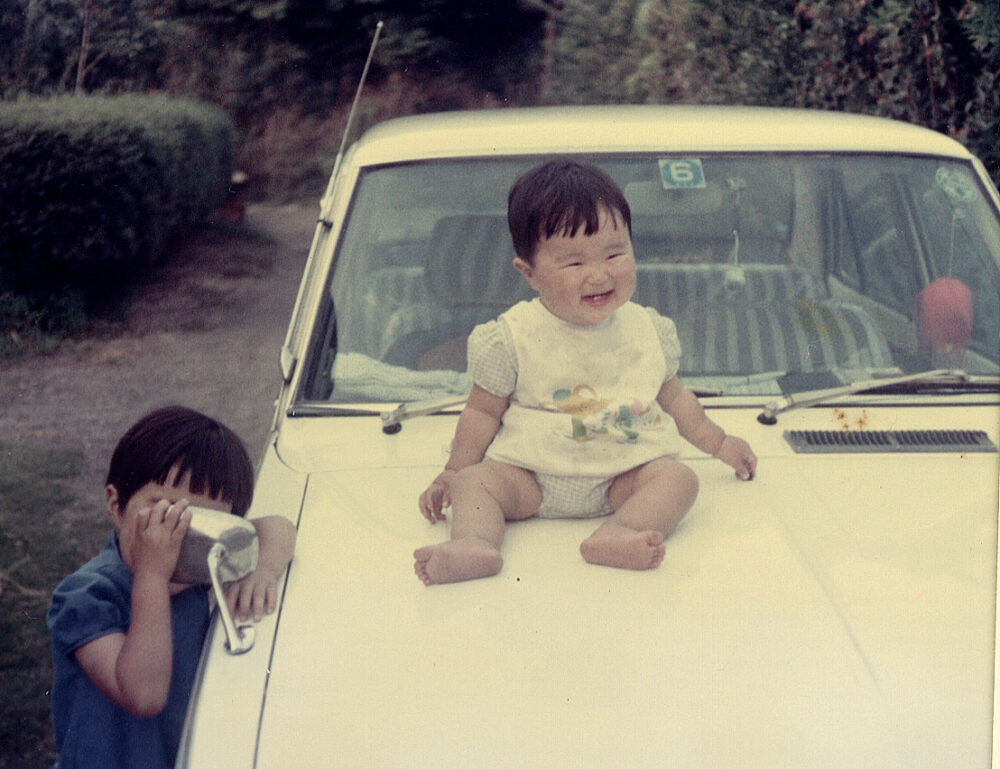
鹿児島県の東南部に位置する曽於郡・大崎町出身で、小さい頃から自然に囲まれて育ちました。海に行って釣りをしたり、凧づくりをして凧あげをしたり。のびのびした環境でした。
当時から理科や技術家庭科が好きで、ラジオづくりや椅子づくり、金属加工などの授業が印象に残っています。釣りでも自作の仕掛けで工夫するなど、ものづくりが好きだったのでそうした仕事に携わりたいと思っていたのです。
年上のいとこが都城高専に通っていたので、実験や実習が多いとは話に聞いていました。実家から通うのは遠かったので寮に入り、部活動は小学3年生から続けていた剣道部に。朝も昼休みも武道場に通い詰めるような生活でした。
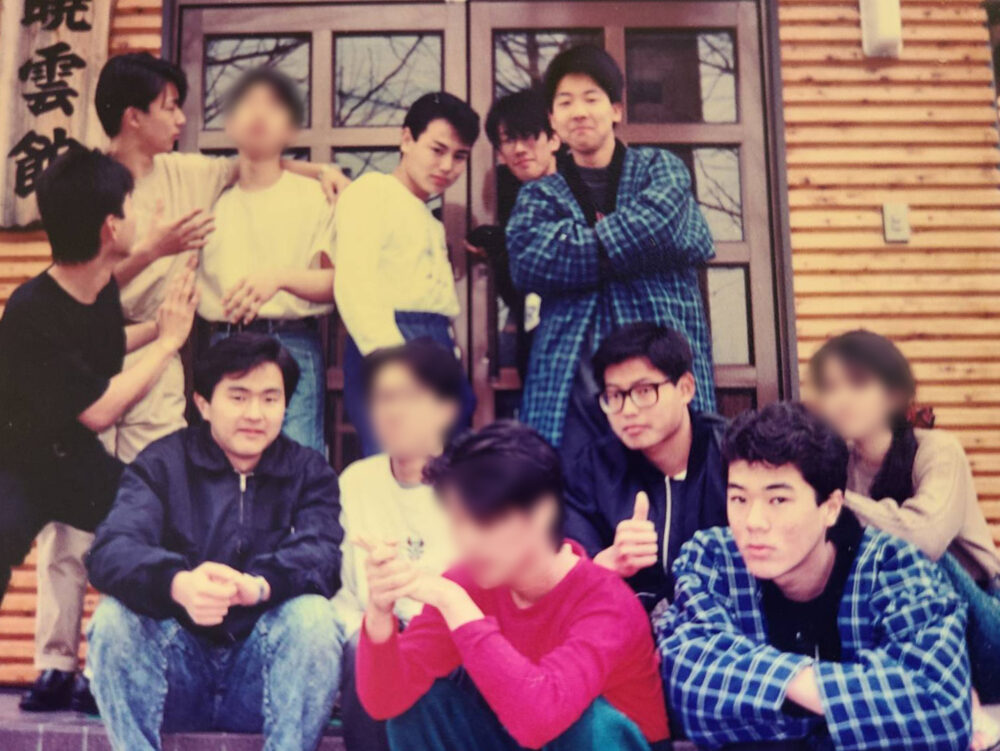
また、高専は春休みや夏休みが比較的長いので、農協でアルバイトをしていました。実家が兼業農家で父が農協に勤めていたので、田植えや稲刈り、農作物を育てる環境がとても身近だったのです。
職員の方に教えてもらいながら、苗づくりや稲刈り、稲の乾燥などをするので「アルバイト」と言うより本格的な「仕事」でした。掛け持ちで電気工事のアルバイトもしていて、この時の経験は後の人生でものすごく役立っています。

貯めたお金の使い道はバイクです。ツーリングが趣味だったので50ccのバイクを寮に、400ccのバイクを友達の家に置かせてもらい、空いた時間でバイクを走らせていました。
―その後の進路についてお聞かせください。
3年生の授業で「生物化学っておもしろい!」と興味が深まり、当時まさに黎明期を迎えていた情報技術にも関心があったので、その両方を学べる九州工業大学工学部へ進学しました。大学で所属した研究室はバリバリの生物専門の研究室。実はじゃんけんに負けて決まったのですが、その研究が今につながっているので「負けてよかった」と思っています(笑)
基礎から応用へ。分野横断的な研究の広がり
―大学院以降の研究について教えてください。
筑波大学のバイオシステム研究科、その後、九州工業大学の情報工学研究科で博士号を取得しました。学生と一緒に研究・開発をするのはとても楽しく、勤務先は大学が適していると思っていたのですが、高専に専攻科ができて生物系の科目が増える話もあり、2000年に母校の都城工業高等専門学校の講師となりました。

その後、子どもが年長になるタイミングをはかって、アメリカのネブラスカ州立大学メディカルセンターで在外研究員になり、2008年から1年間海外で研究生活を送りました。
研究内容は、当時注目を集めていたアルツハイマー病についてです。タンパク質の動きが脳にどのような影響を与えるのか、その動きを可視化できる仕組みをつくろうと研究を進め、帰国後にスクリーニング技術を確立することに成功しました。

さらに研究に集中するために、2011年に室蘭工業大学の大学院へ行きました。北海道は寒い地域ですが、ネブラスカでは冬にマイナス20度になっても家の中は大丈夫だったので、温暖な九州出身でも耐えられるだろうと不安はありませんでしたね。
―室蘭工業大学での研究について教えてください。
細胞分裂など生物のメカニズムについての基礎研究から始まり、現在は細胞骨格などに関わるタンパク質の研究を専門としています。タンパク質は消化酵素や筋肉、抗体など、ヒトのからだをつくる基本で、最大10万種あると言われています。
そして、他の細胞とくっつきやすい性質を持っているので、老化でそのはたらきに異常が出て変な集まり方をすると、心疾患や心筋梗塞、認知症などを引き起こす原因となります。例えるなら、自転車がさびて動きが悪くなるのと一緒ですね。タンパク質も人間と同じで、みんなで集まるといろんなことができるようになり、たまには悪さをしてしまいます。
そのメカニズムを学生や企業と協力して研究するのが私の仕事です。最近の成果では、私が参加した国際共同研究グループが心筋梗塞後の心機能低下のメカニズムを解明し、2021年5月に英科学誌『ネイチャー』に論文が掲載されました。

生物化学と情報に始まり、筑波大学では農業とサイエンス。その後の九州工業大学大学院では基礎的な研究を。その後、タンパク質についての研究へと移り、これまでの研究のすべてが現在につながっていると実感します。
研究に必要な器具や装置が必要になったとしても、「とりあえずつくってみる」と発想できるのは医学出身とは異なる高専出身者の利点だと思います。普通は「つくろう」なんて発想はないし、面倒で躊躇するものですが、「おもしろそうだから」とシンプルに考えることができますからね。
ミスや想定外があるからおもしろい
―センター長を勤めていらっしゃる「クリエイティブコラボセンター」について教えてください。

「情報化されたMONOづくり」をキーワードに、本学を代表する「地域協働AIラボ」「先端ネットワークシステムラボ」「北海道マテリオームラボ」「スーパーマルチキャスティングアロイラボ」「アーバンインフォマティックスラボ」「構造物減災リサーチラボ」「自然災害・防災技術リサーチラボ」「災害廃棄物リサーチラボ」が活動しています。
学内外の協働研究を通じて「持続可能で豊かな社会」を実現するための科学技術開発の推進が目的で、そのベースとなるのが令和元年に本学が策定した「北海道MONOづくりビジョン2060 ―『ものづくり』から『価値づくり』へ―」です。実現したい未来を先に描き、逆算的に考えて研究に取り組んでいます。

学生たちと一緒に研究するのはすごく楽しいですよ。熟練の研究員が集まる研究所だとミスは起こりませんが、学生は思いもしないミスをするので、予想外の結果が出てくることがあるからです。
単位を1桁間違えたり、手順を飛ばしてしまったりと、まったくの想定外の間違いをすると、想像もしなかった発見ができるんです。例えば、タンパク質の研究で必須の熱処理の手順をミスした結果、見たこともない結果が出たことがありました。こうした間違いが「世紀の大発見」につながることもありますから。ただ、いずれにしても「記録」は大切なので習慣づけてもらうよう徹底しています。

私たち研究者は仮説を立てて予測はしますが、予想通りでなくても許されるのが「企業」との違いかもしれません。大事なのは、疑問を持って実際に自分でやってみること。そして結果です。「予想外=もっとおもしろいことが起きている」ということですから、その結果がまた次の予想につながることもあります。
―10代の時に挑戦しておいたほうがいいことはありますか。

とにかく手を動かすことです。アルバイトでも何でもいい。その経験がどこで役に立つのかはわかりませんが、経験があれば、知らない世界に飛び込みやすくなるからです。
私自身、達成したい具体的な目標があるわけではありませんが、いつもおもしろいことを続けていたいと思っています。学生たちや企業、自治体といっしょに楽しく研究する。その積み重ねが社会の役に立てば、これほどうれしいことはありません。
徳楽 清孝氏
Kiyotaka Tokuraku
- 室蘭工業大学大学院 工学研究科 教授

1992年 都城工業高等専門学校 工業化学科(現物質工学科) 卒業
1994年 九州工業大学 情報工学部 生物化学システム工学科(現生命情報工学科) 卒業
1996年 筑波大学大学院 バイオシステム研究科 修了
1999年 九州工業大学大学院 情報工学研究科 修了
1999年 通産省工業技術員産業技術融合領域研究所 博士研究員
2000年 都城工業高等専門学校 講師(2003年 助教授、2007年 准教授)
2008年 ネブラスカ州立大学メディカルセンター 在外研究員
2011年 室蘭工業大学大学院 工学研究科 准教授(2021年より現職)
都城工業高等専門学校の記事



アクセス数ランキング

- 高専は何でも学びになるし、人間としての厚みが出る。「自立して挑戦する」という心意気
- 黒田化学株式会社 グローバル品質保証部 品質管理課
宮下 日向子 氏

- 養殖ウニを海なし県で育てる! 海産物の陸上養殖普及に向けて、先生と学生がタッグを組む
- 一関工業高等専門学校 未来創造工学科 化学・バイオ系 教授
渡邊 崇 氏
一関工業高等専門学校 専攻科 システム創造工学専攻1年
上野 裕太郎 氏


- 高専のさらなる可能性に挑戦! 企業での経験を生かし「ACT倶楽部」を設立
- 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 情報コース 教授
吉田 晋 氏

- 高専から東京大学大学院へ。進学して感じた「高専の強み」と、「進学するメリット」とは?
- 東京大学大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻(東京大学総合研究博物館 所属)
廣田 主樹 氏
東京大学大学院 理学系研究科 生物科学専攻(国立科学博物館 所属)
山本 真生 氏
-300x300.jpg)
- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと
- 鹿児島工業高等専門学校 校長
上田 悦子 氏
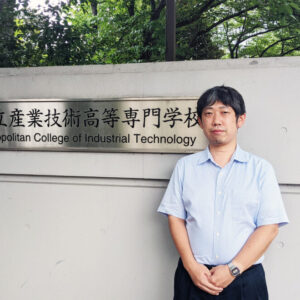
- 「流れ星」を使って災害時にも使える通信を! 2,000㎞をつなぐ「流星バースト通信」の可能性
- 東京都立産業技術高等専門学校 ものづくり工学科 情報通信工学コース 准教授
髙﨑 和之 氏


- 研究は技術だけでなく「人と人がクロスする連携」が重要。「集積Green-niX」の「X」に込めた半導体への思い
- 東京工業大学 科学技術創成研究院 集積Green-niX+研究ユニット(工学院電気電子系担当)教授
若林 整 氏

- 「高専での体育授業」の在り方を追い求める! 教える対象によって「グッドコーチ」は変わる
- 宇部工業高等専門学校 一般科 准教授
小泉 卓也 氏