
NHKのロボコンをきっかけに、旭川高専に進学された土谷圭央(つちや よしお)先生。北海道大学に進学されたあと、現在は苫小牧高専でロボコンの指導もされています。そんな土谷先生に、学生時代のエピソードや研究内容についてお伺いしました。
中学生の頃から、授業で工学分野に触れていた
―土谷先生は、どのような学生生活を送られていたんですか。

子供の頃から外で遊ぶのが好きで、20歳までボーイスカウトをしていました。「自然体験学習者」という資格も取りましたね。中でもキャンプが好きで、テントを載せた自転車で200km先まで行ったり、歩いて100km先まで行ったりもしていました。
ものづくりには、小学生の頃から興味を持っていたと思います。だから、夏休みに開催される科学館の工作体験教室にも参加していましたね。また、中学生の頃にプログラミングやものづくりについて授業で学ぶ機会があったので、そこでより工学系の分野に興味を持ちました。
―旭川高専での生活を教えてください。

高専を知ったきっかけは、NHKで放送されていた「ロボコン」です。中学校でプログラミングを学んでいたこともあって、ロボットには興味がありました。それに、自宅から10kmほどのところに旭川高専があったんです。その距離なら自転車で通えるとも思ったので、旭川高専への進学を決めました。
高専では、ひたすらロボコンに取り組んでいた記憶がありますね。ロボコンに出場した最後の年には、2足歩行でレールの上を走って人を運ぶロボットをつくりました。残念ながら、全国大会に出場ことはできなかったのが心残りです。
ロボコンの顧問だった阿部晶先生には、本当にお世話になりました。研究室も阿部先生を選んだのですが、夜遅くの研究にも付き合っていただいて、他愛もない話をしていたことを覚えています。
ロボコンとの違いに苦労した「エコラン」
―大学生活はどうでしたか。

研究室配属が決まる直前に、僕は大学編入を決意したんです。自分の目標を実現するためには技術や知識が不足していると思い、高専の5年間だけでは足りず、「もっと勉強したい」と感じたんですよね。
室蘭工業大学には、「エコラン」という、ホンダが主催しているコンテストに出場するプロジェクトがあったので、そこに所属しました。これは人が乗れる車をつくって、1リットルのガソリンで何km走れるかを競うコンテストでした。
高専時代と同じように「ものづくり」をしていましたが、ロボットと車は全くの別物だったので、最初は苦労しました。ロボコンではプログラムと回路の製作担当。しかし、エコランではカウル製作の担当だったので、他のチームにアドバイスをもらいながら進めていました。結果的に優勝ができなかったことは悔しかったですね。
―北海道大学院に進まれた理由を教えてください。

室蘭工業大学に進んだ時点で、大学院に進むことは視野に入れていました。それを研究室の高氏先生に話したときに、「北海道大学の話を聞いてみたら?」と紹介されたんです。そこで引き合わせていただいたのが、金子俊一先生と田中孝之先生でした。
その研究室では、画像照合やロボットに関する研究をされていました。僕自身、画像照合やロボットに関する研究は興味があったので、それが進学先の決め手になりましたね。
失敗しても恐れずに理由を伝えることが大切
―研究を行う上で大事にされていることはありますか。

必ず全力を尽くすことですかね。基本的には「何とかなる精神」で生きているんですが(笑)、「何とかしなければならない」という気持ちが強いのかもしれません。「この日までに結果を出さなければならない」と決まっているときは、徹夜をしてでも結果を出そうと努力はしています。
それでも何とかならないことはあって、失敗することもあります。そんなときは、恐れずに「失敗を報告すること」が重要だと思うんですよね。
僕自身、何回も失敗してきました。実験結果が出た後で振り返ったとき、「この実験はやらなくても良かった」って思うことだってあるんですよ(笑)。でも、失敗から学べることもあるので、期限内にやれるに関しては、全力を尽くすことを意識しています。
「勝ちたい」という思いを尊重し、厳しく指導
-高専では、ロボコンの顧問をされているんですね。

高専生のときの経験もあるので、現在もロボコンに携わらせてもらっています。1年目の終わりに学生と話をして、「どこを目指したいのか」と問いました。それによって僕の指導方法も変わると思ったんですよ。
すると、多くの学生から「勝ちたい」という言葉が出てきたので、厳しく指導することを決め、優勝を目指せるようにチームを指導しています。苫小牧高専がもっと上にいけるように、今後も指導していきたいですね。
―現在は、どのような研究をされているんですか?
僕は大学院の頃から、企業と共同で「腰にどれだけの負担がかかっているかが分かるシステム」の研究をしていました。その研究を今も引き続き行っています。センサーが内蔵されたウェアを着てもらうことで、腰にかかっている負担の数値がわかるんです。
現在は大成建設と協力して、建設業の最適な人員配置や新しいアシスト機器開発にそのシステムを役立てていこうとしています。システムを着用して一人ひとりにかかる負担量を知ることで、誰がどの作業をしたら最適かを調べられるんですよ。
それぞれに合った場所で作業をすることが、命を守ることにもつながると思います。今後も研究を進めて、肉体労働が必要とされる業界で、このシステムが役立てば嬉しいですね。
あとは学生と協力して、地域企業の課題を解決する研究も行っています。これは、地域企業が既に特許を取っているロボットをさらにアップデートするための研究です。「自動印刷機」や「左官ロボット」など、実際に学生が改良機をつくりながら、研究を進めています。
学生のうちにたくさん挑戦して、失敗も経験して欲しい
―現役の高専生にメッセージをお願いします。

高専生には、何でも挑戦して失敗して欲しいですね。学生の間は、たくさん失敗して良いと思うんですよ。社会に出てから失敗すると、大惨事になることだってあります。だから何事もやる前から諦めないで、次々と挑戦をして、失敗も糧にして欲しいですね。
また、先生にいろいろなことを聞くことが大事だと思います。高専は大学と比べると教員との距離が近いので、気軽に質問しやすい環境なんです。高専の先生は専門性が高いので、会話をするだけで知識や経験を得ることもできますよね。今のご時世では対面は難しいかもしれませんが、積極的に先生と話す機会をつくってもらいたいですね。
土谷 圭央氏
Yoshio Tsuchiya
- 苫小牧工業高等専門学校 創造工学科・機械系 准教授

2011年 旭川工業高等専門学校 制御情報学科 卒業
2013年 室蘭工業大学 工学部 機械航空創造系学科 卒業
2015年 北海道大学大学院 情報科学院 修了(修士)
2018年 北海道大学大学院 情報科学院 修了(博士)
2018年 苫小牧工業高等専門学校 創造工学科・機械系 助教
2022年 苫小牧工業高等専門学校 創造工学科・機械系 准教授
苫小牧工業高等専門学校の記事


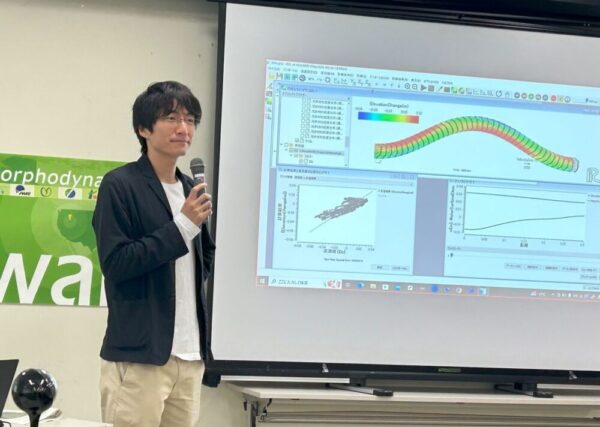
アクセス数ランキング


- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける
- 京都大学 化学研究所 助教
西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会
- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師
田原 熙昻 氏




- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について
- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教
藤田 健太郎 氏


- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡
- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師
盛田 有貴 氏








