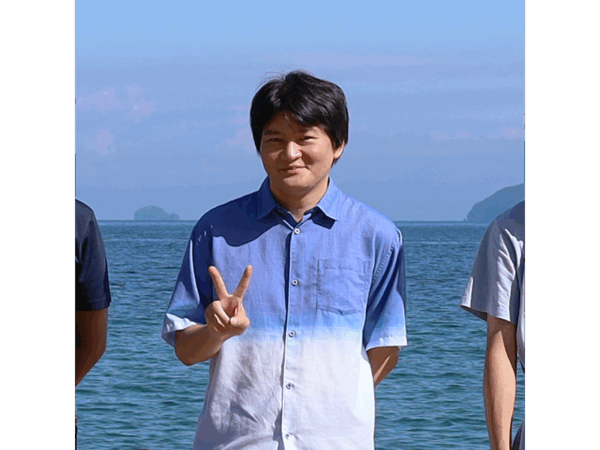-1.png)
大島商船高専での教員を経験し、離島航路の維持・確保をテーマに研究を続けている九州産業大学の行平真也先生。幼少期から海や船に親しみ、公務員として現場を経験した異色の経歴を持つ先生に、研究への想いや教育者としての挑戦、離島航路を未来につなぐための展望について伺いました。
海と船に導かれ、研究者への航路を拓く
―進学先として長崎大学の水産学部を選んだ理由を教えてください。
幼い頃の定番の遊びは牛乳パックを切って船をつくることで、昔からとにかく船が好きでした。また、父方の祖父が大分県の国東市で漁師をしており、夏休みに祖父宅に行く際には漁船に乗せてもらい遊んでいました。船や海というものを身近に感じていたことから、船のことを学びたいと思い、自然と水産学部を選びました。
大学時代で印象に残っている授業も、やはり乗船実習です。船に14日間乗り、沖縄や韓国まで航海する実習は、とても楽しかった記憶があります。

―大学卒業後の進路を教えてください。
九州大学の大学院に進学しました。しかし、入学してすぐの6月に受験した大分県庁の採用試験に合格したため、大学院を中退しています。当時、同じ研究室の大学院生にとって、県庁職員は非常に人気のある進路でした。そのため、私も大学院1年生の時に練習のつもりで試験を受けてみると、思いがけず合格をいただき、県庁に入庁することにしました。
―大分県庁ではどのようなお仕事をされていたのでしょうか。
水産振興課や水産研究部などで業務に携わっていました。水産振興課では魚礁や増殖礁を設置する水産基盤整備事業などに携わっていました。
魚礁は、海底にできた突き出た部分で、魚の集まる場となる箇所です。この魚礁を人工的にコンクリートブロックなどでつくり、海中に設置して魚が集まる場所を設けることで、漁獲の増大や操業の効率化などのメリットがあります。
―大分県庁で職員をしながら、和歌山大学大学院で博士号を取得されています。
県庁に入庁してからもプライベートな時間に研究は続け、学会に参加したり、論文を書いたりしていました。その流れで和歌山大学の大学院の博士後期課程に受け入れていただき、博士号を取ることができました。長崎大学水産学部で指導していただいた先生にも副査(※)に入っていただき、学位論文の公聴会では長崎から和歌山まで来ていただきました。
※学位論文審査委員会における審査委員のこと。学位論文審査委員会は1名の主査と複数の副査で構成される。
博士論文は「乗船実習の教育効果」をテーマにしました。自分自身にとって、大学時代の乗船実習が学生時代の最も印象深い出来事であり、大きな影響があったと思っています。そのため、乗船実習は非常に大切な教育であると感じており、多くの方々に乗船実習を体験してもらいたいという思いがあります。
海上という自分の力ではコントロールできない環境に身を置くことで、陸上では得られない経験をすることができ、大きく成長できると考えています。
大島商船高専での教員時代は、今までの人生で一番充実した3年間
―大島商船高専の教員になったきっかけは何だったのでしょう。
当時、大分県庁では臼杵市の水産業普及指導員をしており、臼杵市で楽しく仕事をしていました。しかし、県庁では2~3年で異動があり、いずれ臼杵市に関われなくなります。臼杵市にもこれからも関わり続けたいという強い思いがあり、退職を考えていたんです。

その話を学会でお会いする先生方に相談すると「高専の教員公募があるから応募してみては?」と勧められることがあり、その中の1つに大島商船高専の交通工学の教員公募がありました。
大島商船高専は山口県にあり、地元の九州から比較的近い場所です。また、船に関わる研究ができる点にも魅力を感じて、応募したところ採用していただきました。
私自身は高専の出身ではないため、着任前に高専という独特な雰囲気を知りたいと思っていました。そんな時に出会ったのが、林檎子先生の漫画『それゆけ女子高専生』です。当時は脚色された部分も多いのではと思いながら読んでいましたが、実際に着任してみると「むしろ抑え目に描かれていたのでは」と感じる内容も多々ありました。
高専の教員になる人は高専出身者が多いため、高専の内部事情を理解した状態で着任できます。しかし私のように高専に縁がなかった人は、ゼロから環境に慣れる必要があります。前もって雰囲気や特色を知っておくことは重要だと思いますので、この漫画は高専に行ったことがない赴任前の先生にはぜひ読んでいただきたいですね。今では私にとってバイブルのような存在です。
ちなみに、この漫画は私が高専に行くことが決まった頃に連載が始まり、着任日の2016年4月1日の前日に最終話が公開され連載が終了しました。この連載期間には何か特別な縁を感じ、とても感慨深いものがありました。
―大島商船高専での教員生活はいかがでしたか?
非常に刺激的で毎日が充実していたのを覚えています。今までの人生で一番充実した3年間でした。言葉にするのが難しいのですが、もう一度学生生活を楽しめたような感覚でした。同年代の教員と意見を交わしながら研究を進める時間は、かけがえのないものでした。

大島商船高専には3年間勤め、その後、九州産業大学に移り、現在は准教授として勤務しています。ただ、高専で出会った先生方とは、今でも飲み会を開いたり旅行に行ったりするなど、良い仲間に恵まれました。今年は2泊3日で沖縄に行きました。
―大島商船高専での研究について教えてください。
「フェリー利用者の交通行動分析」をテーマに研究を行っていました。どこの方が何のためにフェリーに乗り、どこに行かれるのかを調べる調査を、大分県と愛媛県を結ぶ3航路や、大分県と山口県を結ぶ航路で行っていました。
フェリーの利用実態を可視化することで、観光戦略の立案などの具体的な施策に活用できる、地域振興に貢献できる研究です。

離島航路を未来へつなぐ、自分の強みを生かした研究者に
―現在の研究に関して教えてください。
離島航路の維持・確保をテーマに研究を進めています。大島商船高専でフェリーの研究をしていましたが、その中でも困難な状況に置かれている離島航路に注目し、この研究を始めました。
離島航路は島民にとって、本土または離島間を結ぶ生活の足であり、欠かすことができない公共交通機関です。しかし一方で、多くの離島においては深刻な少子高齢化や島外への人口流出に伴う人口減少が著しく、航路利用者の減少など、離島航路を取り巻く環境は大変厳しい状況です。
離島航路を維持するための方法の1つとしては、船を小型船舶化することが挙げられます。19トン以下の小型船舶にすることで運航にかかるコストを削減して、維持していこうという考え方です。もちろん、導入が難しい島もあり、全てを小型船舶化できるわけではありませんが、九州では数例、小型船舶にした事例があります。
また、母港変更も1つの手段です。多くの離島航路は母港が離島側にあるため、船員は離島に住む必要があります。しかし、船員不足が深刻化している中で、縁もゆかりもない離島に住むことを条件に求人を行ってもなかなか船員確保は難しいです。
かつては、島に住む方々が船員として働く流れが一般的でしたが、今や離島の人口は減り、その役割を担う人がいなくなっています。そこで、母港を離島から本土に変更し、本土に住みながら船員として働けるようにすることで、船員確保がしやすくなると考えられています。しかし、島の実情から島発としたいという島民の方の思いもあります。実際の事例を基に、島民の方々や船員さんにお話しを聞くなど、研究を進めているところです。

―今後の目標を教えてください。
現在、中国地方や九州地方の自治体や航路事業者から離島航路に関する相談を受けることがあります。まずはそれに応えられる研究者になりたいと思っています。
また、離島航路の問題を抱える地域は全国にありますが、その多くが可視化されていません。離島航路の研究の中で、「この問題なら同じ事例が〇〇航路でもありました」と担当者同士をつないだり、視察の調整をさせて頂いたこともあります。今後も様々な形で、離島航路に関する問題解決のサポートができればと思っています。
また、私が特に自治体とスムーズに連携できるのは、公務員出身だからだと考えています。元県職員として、行政関係の資料を読み解けることは大きな強みです。今後もアカデミックな研究だけでなく、行政の実情に基づいた、現場に寄り添った研究を続けていきたいと思っています。
.jpg)
―教育者として、大切にされていることを教えてください。
私は「良い授業ができる教員」を目指しています。少なくとも受けてよかったと思っていただけるような、とにかく良い授業をしたいです。そのため、まずは話し方から改善していきたいと思い、アナウンススクールに通い始めました。毎日、発声練習をちゃんとやっています。
また、学生に楽しいと思ってもらえるような授業をするため、来年度はR-1グランプリへの出場も考えています。1回戦突破を目指します。
―最後に、高専生へのメッセージをお願いします。
大島商船高専の商船学科の教員を経験して良かったと思う点の1つは、九州産業大学が船関係の大学ではないことから、「なぜ九州産業大学の教員が船の研究をしているのか」と疑問を持たれた際に、「大島商船高専の商船学科で3年間教員をしていました」と説明するだけで理解を得られ、全てがスムーズに進む点です。
それだけ、業界での商船高専のネームバリューは大きいものです。商船高専出身の方はぜひそのことを誇っていただきたいですし、それに見合った活躍を期待しています。私も元商船高専の教員として、それに見合った教育や研究をしていきたいと思います。
また、商船高専に限らず高専全体を見ても、私が知っている高専生や高専卒業生はみんな高専に愛着があり、高専が大好きな人が多い印象です。高専という環境は非常に独特で、個性が尊重される場所です。私が初めて高専に着任した際も、そのユニークな雰囲気に驚きました。ぜひ、今の環境を生かして、自分らしく自由に楽しんでもらえたらと思います。
行平 真也氏
Masaya Yukihira
- 九州産業大学 地域共創学部 地域づくり学科 准教授
-1-470x388.png)
2007年3月 長崎大学 水産学部 水産学科 卒業
2008年3月 九州大学大学院 生物資源環境科学府 修士課程 中退
2008年4月 大分県職員(水産振興課、農林水産研究指導センター水産研究部、中部振興局)
2014年3月 和歌山大学大学院 システム工学研究科 博士後期課程 修了
2016年4月 大島商船高等専門学校 商船学科 航海コース 助教
2017年4月 同 准教授
2019年4月 九州産業大学 地域共創学部 地域づくり学科 講師
2024年4月より現職
大島商船高等専門学校の記事



アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける
- 京都大学 化学研究所 助教
西尾 幸祐 氏



- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会
- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師
田原 熙昻 氏


-300x300.jpg)
- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと
- 鹿児島工業高等専門学校 校長
上田 悦子 氏

-300x300.png)
- “女子は無理”と言われた時代を超えて──長い研究人生の先で挑む、高専での技術者教育
- 奈良工業高等専門学校 校長
近藤 科江 氏

- 大切なのは「双方向でのコミュニケーション」。学生の積極性を育てる、杉浦先生の授業方針とは。
- 大阪府立大学工業高等専門学校 総合工学システム学科 教授
杉浦 公彦 氏