
今回は、さまざまな高専を卒業したOBOGで、現在は九州大学工学部 応用化学科の分子生命工学コースに所属する皆さんと、教授の神谷典穂先生からお話を伺いました。高専入学から九州大学での研究、これからの目標に至るまで、先輩方の軌跡と活躍に注目していきます。
これからの化学を担っていく高専卒業生
―皆さんが高専に入学された理由を教えてください。

西村さん:僕は有明高専の出身なのですが、地元が有明ということもあり、小学生の頃からオープンキャンパスなどに参加する機会が多くありました。そのため、高専を身近に感じていて、入学しました。

田中さん:僕が中学生の時、当初は周りの人と同じように公立の進学校に行くんだろうなと思っていました。でも、進学校に行った仲の良い先輩がつらそうに勉強をしているのを見て、公立の進学校ではなく高専に行きたいと思うようになりました。

林さん:僕は、中学生の頃から化学に強い興味を持っていて、文系の教科はあまり得意ではなかったので、高専を選びました。

馬越さん:私は、中学生の時に理科の授業が好きで、その中でも化学に興味を持ちました。また、化粧品会社に行きたいなとも思っていたので、高専の生物応用化学科に入学しました。

岡尾さん:私は、中学生の時から理科の実験が好きでした。特に物理というよりは、溶液を混ぜて反応を見るような化学の実験が好きで、北九州高専の物質科学工学科に入学しました。
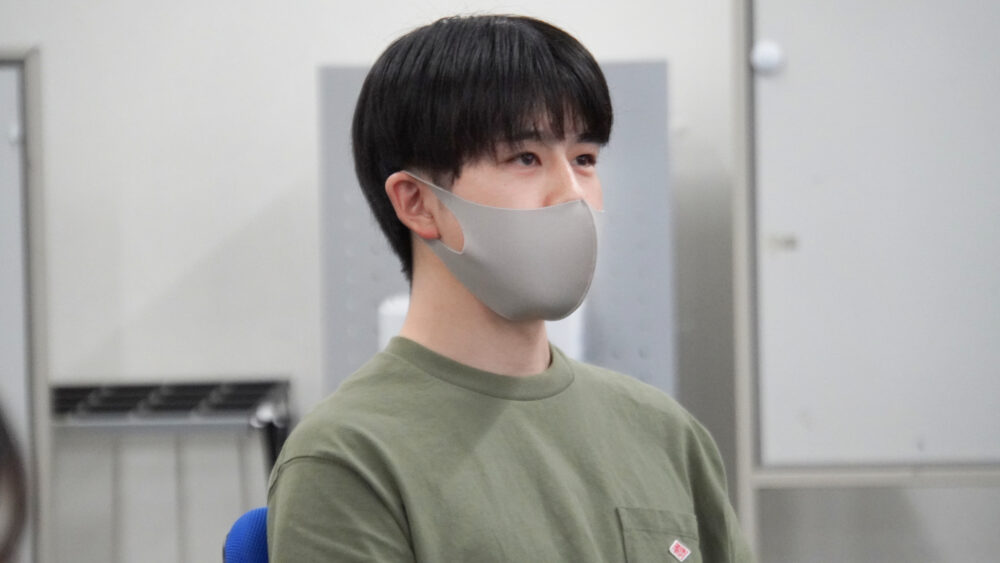
佐伯さん:僕も、北九州高専の出身ですが、実家から通える距離であったことが大きな要因です。また、自分のレベルにもあっていたため選びました。
―高専に入学してよかったことを教えてください。

西村さん:専門性が高かったことだと思います。そのため、九大に入ってからもすんなりと学べました。さらに、自分の専門とは異なる先生からも教えてもらえたのは、高専の強みだったかなと思います。
田中さん:公立の高校よりも実習や実験がたくさん行えると思いますね。基礎的なノウハウを得られることもよいと思います。加えて、高専の先生は博士号を持っている人が多いので、あまり関係ない分野も知識のある先生からしっかり学べます。生物の先生には薬学博士だった先生もいましたよ。
林さん:卒業研究では、研究活動に没頭できました。僕は、卒研で「ポリイミド」というものを作っていました。やはり、公立高校に比べて、専門性が高いことが強みだと思います。
馬越さん:低学年の頃から、専門的な先生から専門的な分野を学べますし、学んだことを実験して、実証することが出来ます。実験器具などの設備なども整っていることが一番の強みだと思います。
岡尾さん:北九州の工業地帯が近いこともあり、毎年一回工場見学に行っていましたね。TOTOや肥料を作っている企業などに行ったんですが、10代の頃からそのような体験ができることは貴重だと思います。
佐伯さん:実験などの時間が多いので、時間の使い方が上手になったと思います。高専だと、バックグラウンドの違う人が多くて、刺激的なところもよいと思います。

神谷先生:高専出身者は、いい意味で、こだわりを持ってきた学生さんが多いですね。特に高専生は、実験好きが多い印象です。好きなことに自由に取り組んでもらって、学生さんが出してくるデータから新しいことを知ることが私自身もあります。編入生と一般入試で入ってきた学生は、互いに良い影響を与え合っていると思います。
九州大学での、それぞれの学びと今後の夢
―皆さんが九州大学 応用化学科に入ってよかったと思うことを、教えてください。

佐伯さん:周りの人の意識が高いので、ここにきて自分の意識を変えることが出来ましたね。
岡尾さん:周りが一生懸命勉強しているのを見て、自分も頑張らないといけないなと思うことが出来ました。また、他の研究室の先生や仲間にも助けてもらえることは、とてもありがたいです。
馬越さん:私も皆さんと同じように、仲間からたくさんの刺激をもらえることが、この学科に入ってよかったことだと思います。
林さん:教育が充実していますね。例えば、実験や研究だけではなく、文章の書き方なども教えてもらえる。また、研究室の隔たりがないことも、この学科特有のものだと思います。
田中さん:周りの意識が高く、仲が良いのでいろいろな人とコミュニケーションが取れます。
西村さん:カリキュラムがとても整っています。「リサーチプロポーザル」という科目があるのですが、自分の研究でない分野を研究し、発表を行い、その専門の分野の先生に質問攻めにされるというプログラムがあります(笑)。これは、本当にきついんですけど、終わった後、自分自身で成長を感じることができます。
神谷先生:教員の間でもしっかりと連携を取って、学生たちを皆で教育していこうと団結しています。応用化学科では、他の研究室の装置の使用や、他の研究室の先生からアドバイスをもらうことが、当たり前のようにできます。
また、修士の学生向けには「総合試験」という特徴あるプログラムがあります。自分が学んでいる研究とは違う分野のトピックを選択し、総説を作成し、プレゼンするのですが、自分の研究分野以外の知識も深まり、大変良いトレーニングになります。
―化学、生化学のどこが好きですか?

西村さん:化学は予想どおりにいかないっていうところに、面白みを感じています。
田中さん:程よいわかりやすさと、程よい理解がこの分野にはあると思います。例えば、電気が流れている、でもなぜ、どのように流れているか分からない。こういうような身の回りの不思議だなと思うことや、虹が出るのはなぜ?とか。そういうことを考えるのはすごく好きです。
林さん:身の周りのものはすべて化学でできています。それってすごいなって感じています。それを、実用的なモノづくりにつなげていくことに面白さを感じます。
馬越さん:医療機器に関する研究で、新しい高分子によってどのような生体反応が起きるのかなどに興味を持って研究しています。
岡尾さん:私は、有機化学が研究分野なのですが、組み合わせや掛け合わせる順番で、つくれるものが無限大というところが好きです。
佐伯さん:教科書に書かれていることは、自分の体の中で起きていることで、それを調べていけるということに面白味を感じています。
―皆さんのこれからの目標と、高専生の後輩へ一言をお願いします。

西村さん:小学生の頃から教授になりたいと思っていました。いまでもその目標は変わっていません。高専生の皆さんへは、自分が本当に何をやりたいのかということを問いかけてみてほしいです。
田中さん:研究に集中的に取り組める大学で研究して、いつか大きなことを成し遂げたいと思います。皆さんには、何か勉強以外で本気で取り組めることを見つけてほしいと思います。
林さん:役に立つモノづくりをしたいと思っています。時間もあるし、編入も簡単にできるので、高専に入学できたことをハッピーだと思ってほしいです。
馬越さん:私も、人に役立つモノづくりをしたいです。皆さんには、研究だけでなく人とのコミュニケーションを取るためにも、大学に入ることをお勧めします。
岡尾さん:自分の今の研究を生かしていくことが目標です。長期的な目標としては、「化学に詳しい人になれた」と自分自身が思えるようになりたい。皆さんには、勉強以外の趣味を見つけてほしいです。
九州大学工学部応用化学科
〒819-0395
福岡市西区元岡744 伊都キャンパス ウェスト4号館4階441号室応用化学科事務室
分子生命工学コース事務室 TEL092-802-2852(ダイヤルイン)
http://www.cstm.kyushu-u.ac.jp/
機能物質化学コース事務室 TEL092-802-2893・2894(ダイヤルイン)
http://www.cstf.kyushu-u.ac.jp/
アクセス数ランキング

- 自ら教え続け、研究し続ける“現役”の校長——立場が変わっても貫く「人づくり」の教育
- 函館工業高等専門学校 校長
清水 一道 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡
- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師
盛田 有貴 氏

-300x300.jpg)
- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと
- 鹿児島工業高等専門学校 校長
上田 悦子 氏



- 10年間の研究が地球環境大賞を受賞! 鉄鋼スラグを用いた画期的な藻場創出プロジェクトに迫る
- 宇部工業高等専門学校 物質工学科 教授
杉本 憲司 氏
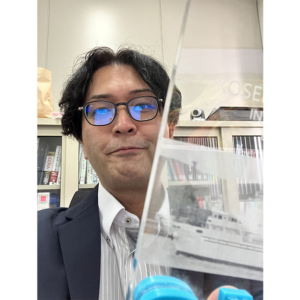
- 「やさしく、ふかく、たのしく」学ぶ情報工学。色付き有限オートマトンの可能性
- 大島商船高等専門学校 情報工学科 准教授
高橋 芳明 氏

-150x150.jpg)
- 「自分にしかできないこと」を追い求めたから、今がある。デザインで街を元気にする取り組みとは
- 石川工業高等専門学校 建築学科 教授・副校長(地域・国際連携)
道地 慶子 氏











