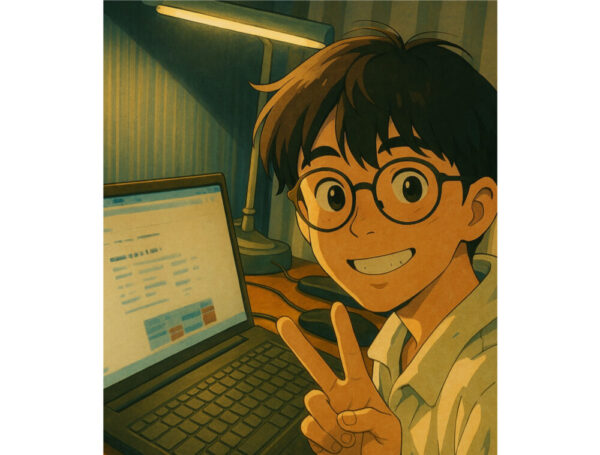神戸高専の出身で、現在は東京工業大学の学長を務められている益一哉氏。来年度に控えた東京医科歯科大学との歴史的な統合を前に、大学改革への取り組みや高専に対する思いについてお話を伺いました。
普通では面白くない「高専」という選択肢
―神戸高専から東工大へ進まれた経緯からお聞かせください。
小学校の頃、プラモデルにモーターを入れて走らせていたのですが、電池をたくさん積むとモーターが速く動き、「電気って面白いな」と興味を持ちました。建築にも興味があったのですが、芸術的センスのなさを自覚して電気の道を選びます(笑)
そして、高校への進学を考えた際、天邪鬼(あまのじゃく)なところがあって、高校で普通のことをやるのは面白くないなと思いました。すぐに電気の勉強をしたいと考え、進学雑誌で調べたところ、大学と同じレベルの専門教育を5年間で行う「高専」の存在を知り、神戸高専を受験したんです。

当時はちょうど大阪万博(1970年)の頃で、ポケット電卓が発売され、父親が「持ち運びできるんだ」と、会社から家に持ち帰っていたのをよく覚えています。電子計算機と呼ばれていた時代ですが、コンピュータや今で言うプログラミングに興味を持つきっかけになりました。
そして、高専で電気の勉強をしながらプログラミングの勉強をしていた1973年に、江崎玲於奈先生が半導体内のトンネル効果でノーベル賞を受賞します。半導体の授業も受けていたので、半導体系の仕事に行くかコンピュータ系の仕事に行くか、どっちも面白いなあと、二股をかけて勉強していました。
その後、もう少し専門の勉強をしたいと思い、大学に編入することを考えました。当時、京都大学や大阪大学にはまだ編入制度がなく、東北大学がいいなあとも思ったのですが、東京工業大学が編入制度を始めたという話を聞き、“高専の親玉みたいな大学”だと思って(笑)、受験し合格できたので進学しました。
―博士まで東工大に在籍した後、東北大へ研究の場を移されています。
東工大に編入学したときから確信犯的に修士課程には進むことを決めていました。父親からは「話が違うぞ」と怒られましたが(笑) 卒論を始めた頃から真面目に研究を極め、行くとこまでやってみたいという気持ちが芽生え、博士まで進学しました。博士の後のことはそのとき考えようと思っていました。
そうこうしていたら「東北大で電気通信研究所の助手を探しているのだけど、どうする?」と声がかかりました。後で聞いたところでは「東工大に誰か若い、イキのいいやつはいないか」という話でした。大学編入時には東北大か東工大の2つを目指しており、東北大への憧れもありましたので、東北大にお世話になりました(笑)
結果、東北大には18年間いましたが、「東工大の精密工学研究所が半導体分野の人をすずかけ台キャンパス(横浜市)で探している」という話が来ました。この分野の教授を探していたということで、東工大の教授として採用され戻ることになりました。
「高専卒」の学長として、教育改革・研究改革に取り組む
―東工大の学長として、大学で取り組んでいらっしゃることをお聞かせください。
前任の三島学長から東工大の教育改革・研究改革などを引き継いでいます。教育改革は三島先生が導入されてから2年経ち、本当にきちっと進んでいるのか検証もしないといけませんでした。また研究力のアップ、産学連携もやらないといけません。研究所の経験が長いので、研究を強化するべきと取り組みました。
ガバナンスについては、三島先生が構築した学長のリーダーシップが発揮しやすい体制をうまく引き継げば、教育だけではなく、研究も強くできるはずだという気持ちで取り組みました。学長就任2年間は楽しくやりましたね。ただ、さあこれから、海外との連携もより一層進めよう、というときに、「コロナ禍」になってしまいました。
―東工大における「教育の場としての大学像」はどんなものですか。
東工大での教育は一流の研究者が教えていますので、同じことを教えていても、端々で物事の理解力が違います。何かを究めた人が基礎を教えるのが一流の研究大学だと思っていますが、東工大はそれが実現できている大学です。

そして、多様な学生がいることが理想です。研究においては例えば、原理や性能ばかり追及するのではなく応用や社会実装も目指すような、単一的じゃない考え方が必要になってきます。そのためにはチームメンバーに多様性があることが、イノベーションを産むきっかけになり得ると考えています。
それこそ多様な考え方が科学にも技術にもあるわけですから、いろいろな発想を持った人たち、当然、日本だけではなくて外国の人もいてしかるべきです。最近よく言うのですが、広い意味での多様性として、特に女子学生の存在は大きいですね。

提供:東京工業大学
現在の東工大は関東6県出身の学生が多く、出身地が偏った「東京地方工業大学」になりつつある状況です。それに対して、高専からの編入学生約40人は全国から集まってきます。この意味は大きいです。
全国の高専から東工大に優秀な編入生が来てもらえれば、大学全体が活性化するはずです。私が「高専卒の東工大学長」と言われることでも、東工大の宣伝という役割を果たすことができればと思います。
ただし、高専出身であっても、求める学生像としては区別していません。他の学生同様にアドミッションポリシーに則り「科学技術への知的好奇心や探究心と社会に貢献したいという志を有し、その基本的概念や基礎知識とそれを活用できる力を身に付けた人材」であることを求めています。
―高専生を対象とした奨学金も創設されました。制度についてお聞かせください。
今年度から高専生を対象に、東工大基金奨学金『みらい創造高専起業奨学金』を創設しました。学士課程に編入学を希望する優秀な高専在学生または卒業生であり、修士課程に進学予定で、自らが学んだ技術・研究を生かして、将来的には起業に意欲・興味のある人を対象に支援するものです。ユニークな奨学金です。

提供:東京工業大学
―来年度は東工大と東京医科歯科大学との統合が控えていますね。
2024年度中の東京医科歯科大学との統合を目指して進めています。統合して一緒に新しい研究分野をつくっていくことについて、多くの賛同、応援のお声をいただきました。これからの大学のあり方のひとつとして、自然なことだと皆さんが捉えてくれているのではないでしょうか。
名称ですが「東京科学大学」で申請をしています。新大学が、これからの「科学」の発展を担い、社会と共に活力ある未来を切り拓いていくという、強い意志を表現した象徴的な校名として考えています。とにかく新しい大学が無事に出発できるよう、学長職としての総仕上げを行いたいと思っています。
「科学技術は進化する」ということを知ってほしい
―現在の高専がさらに目指すと良いことは、何だと考えていらっしゃいますか。
高専は大学で学ぶレベルの専門教育を凝縮して勉強する分、リベラルアーツの学びが不足していると思います。ただ、それを補うには教員も不足していると思いますので、高専同士の横の連携がもっと進めば良いのかもしれません。
あと、国内の企業が海外進出する場合、工場をアジアに置くことが多いと聞きます。それにはアジアに優秀な技術者がいなければならないはずで、その供給元としてKOSEN(高専)が大きな役割を果たすと考えています。海外に設立されるKOSENは教育の輸出という意味でも極めて高く評価するべきであり、応援したいですね。
就職においては、高専生の専門性・能力を評価し、それに見合った条件(給料など)を提示できていない企業が存在することが残念です。同じことが、博士後期課程修了者にもいえます。高専生が活躍するためには、日本社会が多様な評価軸を持つことが必要です。
―それでは、現役の高専生にメッセージをお願いします。
今学んでいることはいろいろな形で将来につながると思います。しかし、それが将来にわたって通用するわけではないですので、新しいことを学び続けなければならないでしょう。「科学技術は進化する」ということを理解していれば、学び続ける必要性、知りたいという好奇心を体感しているはずです。その気持ちを持ち続けてほしいですね。

提供:東京工業大学
―これから高専を目指す、未来の高専生にもメッセージをお願いします。
私の高専時代もそうだったのですが、1年生だった15歳のときに、5年生の20歳の先輩を直接知り得たことはとてもいい経験でした。高専の5年生は遥かに大人でした。
大学編入にしても、高校から進学する場合と比べたメリットは、大学受験を前提としない勉学に集中でき、早い段階で専門的なことが学べ、社会につながるリアルワールドが見られることです。そして、高い目標を自然と意識できるようになることだと思います。あなたの興味を本当にすぐに実体験させてくれる学校が高専です。
早い内からやりたいことや将来のビジョンが見えていることは「志がある」といえます。「志を持つ」ということと、10代という多感な時期に本来学ぶべきことを大学受験対策に時間をとられず学べることが、差となってくるのではないでしょうか。
益 一哉氏
Kazuya Masu
- 東京工業大学 学長

1975年3月 神戸市立工業高等専門学校 電気工学科 卒業
1977年3月 東京工業大学 工学部 電子物理工学科 卒業
1979年3月 東京工業大学 大学院理工学研究科 電子工学専攻 修士課程 修了
1982年3月 東京工業大学 大学院理工学研究科 電子工学専攻 博士後期課程 修了
1982年4月 東北大学 電気通信研究所 助手
1993年4月 同 助教授
2000年6月 東京工業大学 精密工学研究所 教授
2016年4月 東京工業大学 科学技術創成研究院 教授、東京工業大学 科学技術創成研究院長 兼務
2018年4月より現職
神戸市立工業高等専門学校の記事
-600x458.jpg)


アクセス数ランキング
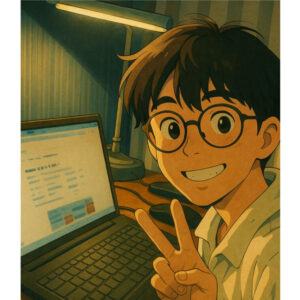
- 静岡でAIに熱狂する高専生! 経営者への取材活動を通して感じた、起業するときの「大人」の存在
- 沼津工業高等専門学校 制御情報工学科 3年
田村 愛琉 氏

- 合唱部創設、体育祭でのeスポーツ導入。NHKでも生き続ける「ないものはつくる」高専の精神
- NHK松山放送局 コンテンツセンター
下平 啓太 氏
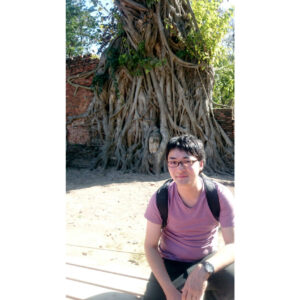
- バックドライバビリティ(逆駆動性)の研究で、誰もやっていない制御技術の先駆者を目指す!
- 一関工業高等専門学校 未来創造工学科 電気・電子系 助教
川合 勇輔 氏


- 「電気を光で置き換える」可能性の追求。電子情報と応用物理の間で見つけた自分の道
- 東京科学大学 未来産業技術研究所 助教
相川 洋平 氏

-300x300.jpg)
- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと
- 鹿児島工業高等専門学校 校長
上田 悦子 氏

- 得意の語学を究めるために高専へ! 趣味の筋トレから学ぶ、他者と比較せず、継続することの大切さ
- 埼玉大学 経済学部 3年
青木 大介 氏


- 夢は持たなくてもいい! 基礎能力があればどこにでも行ける。だからこそ、日々の学びを大切に
- 富山高等専門学校 商船学科 航海コース 講師
村田 光明 氏