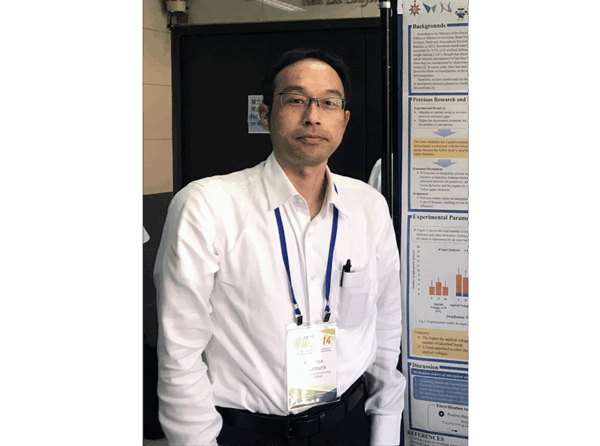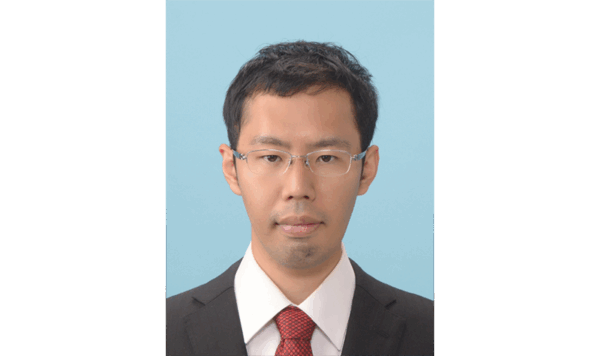国立高専機構と月刊高専が主催で2025年2月開催した「第2回高専起業家サミット」のイントラプレナー部門で、沖縄高専のチーム「ゆがふぁーむ(from ミヤギ農家)」が優秀賞を受賞しました。また、Honda IGNITION賞(提供:本田技研工業様)も受賞しています。
土壌内に音響刺激を与えて微生物を活性化させることで農業における土壌劣化を防ぐ「Smart AgreenTech」を目指しています。その詳しいビジネスプランについて、代表の石垣幹人さんと、プレゼンやピッチ、そしてビジネス化サポートを担当されている大嶺結葉さん(ともに生物資源工学科 4年)にお話を伺いました。
化学肥料や農薬による土壌劣化を防ぐ
―Smart AgreenTechについて教えてください。
石垣さん:AgreenTechはAgriTech(農業技術)とGreenTech(環境技術)を組み合わせた造語で、持続可能な農業と環境保全の融合を目指す革新的な技術領域を指します。現在、私たちは土壌内に特定の振動刺激を与えることで微生物を活性化させ、土壌機能を回復させることにより、化学肥料や農薬に依存しない農業の実現を目指したサービスの確立に取り組んでいます。
また、独自に開発したシステムにより、土壌中の微生物活性を可視化・数値化し、AIで解析した上で最適な刺激を与えるという一連のプロセスを実装している段階です。本ビジネスプランの構築は、2024年8月頃から本格的に取り組み始めました。

―土壌内に音の刺激を与えるとは、斬新なアイデアですね。
大嶺さん:そもそも、この方法を考案したきっかけは、海外の研究者によって、土壌にいる微生物が音響刺激に反応して活性化されることが明らかになったことです。これまで微生物を活性化させるためには一般的に堆肥といった有機資材が用いられていましたが、この研究結果によって、音響刺激が新しい方法として加わったことになります。
ただ、先行研究の課題として、音響刺激は土壌中での減衰が大きいため、主に土壌表面付近の微生物への作用にとどまり、その効果が限定的でした。
私たちは、土壌の深部にまで刺激を与えることで、より多くの微生物を活性化させ、これを持続可能な環境再生型農業に応用できると考えました。そこで、ゆがふぁーむでは独自の技術的工夫を施し、土壌深部まで効果的に刺激を与える仕組みを開発。現在、特許取得も視野に準備を進めている段階です。
実際の農地で検証することはまだできていませんが、校内の複数のプランターで実証実験をしまして、土壌内の微生物が活性化している可能性があることが分かりました。また、農作物の葉が大きくなったことも確認できています。今後は、次世代シーケンサーやPCRにより土壌微生物叢の詳細な分析を行うとともに、特定の微生物をより効果的に刺激するための手段を確立させていく予定です。


―そのビジネスプランを考えた背景は何なのでしょうか。
石垣さん:化学肥料や農薬の多用によって土壌劣化が起こっている問題があることです。また、農業における温室効果ガスの大量排出が問題になっている点も挙げられます。世界の温室効果ガス排出量の22%が農林業由来でして※、その原因としては農業用機械、家畜動物のほか、化学肥料の生産・使用などがあるのです。
※「IPCC 第6次評価報告書 第3作業部会報告書(2022年)」より
Smart AgreenTechは化学肥料・農薬の使用量の削減を大きな目標に据えているサービスですが、不耕起栽培にも生かせると考えています。これは、振動刺激に土壌をほぐす効果があるためです。
不耕起栽培は農地を耕さずに行う農業のことで、土壌に炭素を貯留しやすくなることから、温室効果ガス排出量の削減が期待されている方法です。私たちのサービスは土壌に刺激を与えるため、トラクターや耕運機といった機械を必要とせず、不耕起栽培と相性が良いと考えています。
将来的なフランチャイズ展開を考える理由
―Smart AgreenTechを農家の方が導入される場合、どれくらいの負担になるのか教えてください。
石垣さん:現状、一筆(独立した1つの土地)あたりの耕地面積を2.4ha※とした場合、現状では年間132万円程度を想定しています。ただ、地球温暖化防止の効果が高い営農活動をされている農家さんには、農林水産省から環境保全型農業直接支払交付金などといった補助金が年間40万円以上交付される他、現在はシステムの自動化による低コスト化についても検討を進めている段階です。
※2.4haは、2023年の農業構造動態調査(農林水産省)による、都府県の「一経営体当たり経営耕地面積(農業経営体)」である。経営耕地面積が都府県よりも圧倒的に広い北海道のデータは含んでいない。
また、近年高騰している化学肥料・化成肥料の費用を大幅に削減することも可能です※。年間132万円以上の利益を農家さんが享受できるように、これからもビジネスプランを詰めていきます。
※2023年調査の営農類型別経営統計(農林水産省)によると、畑作経営(個人経営体)の場合、肥料費の平均は165万8千円となっている。ちなみに、2022年調査だと132万3千円であり、2022年から2023年の1年間で30万円以上高くなっていることが分かる。
―直近の目標と、1年後の目標を教えてください。
石垣さん:直近の目標は、市場導入に向けて、振動刺激による微生物活性化の確実性を高めることです。実証実験の回数を重ねて、日々取り組んでいます。
1年後に関しては、県内でまずSmart AgreenTechを展開させ、その後、近隣のオーガニックビレッジ※で展開できればと考えています。近々だと、鹿児島県の徳之島町での展開を検討しています。
※農林水産省が創出を支援している「有機農業の生産から消費まで一貫し、農業者のみならず事業者や地域内外の住民を巻き込んだ地域ぐるみの取組を進める市町村」のこと。
また、第2回高専起業家サミットで「Honda IGNITION賞」を受賞し、Hondaさんの社外向けインキュベートプログラム「IGNITION CHALLENGE 2025」の一次審査参加権をいただきましたので、そちらでビジネスプランをよりブラッシュアップさせていきたいです。
―将来的な事業展開については、どのように考えていますか。
大嶺さん:Smart AgreenTechの技術やノウハウを若手農家さんへフランチャイズ展開することを考えています。沖縄はそのほかの都道府県から物理的にかなり離れていますので、フランチャイズ展開が最適だと判断しました。また、これによって日本全国の土壌データを収集しやすくなると考えています。
先輩チームの取り組みから生まれたアイデア
―チーム名に「from ミヤギ農家」が含まれていますが、その理由は何なのでしょうか。
石垣さん:「ミヤギ農家」は私たちの取り組みの前身となった先輩方のチームの名称です。大半のメンバーは卒業してしまいましたが、一緒に活動していた時期もあります。
チーム「ミヤギ農家」は昨年の第1回高専起業家サミットに出場し、DCON2024では農林水産大臣賞を受賞しています。また、2025年に農水省で開催された第1回みどり戦略学生チャレンジでは大学の部で農林水産大臣賞を受賞した実績もあります。そうした経緯から、「ミヤギ農家」のネームバリューを活かすために、今回のチーム名にも入れました(笑) もちろん、名前を使ってよいかの確認はしています。

石垣さん:ミヤギ農家では、ドローンとAIによって農作物の生育状況と土壌(地力)の関係性を可視化し、地力バランスのどこがズレているのかを把握したのち、ミヤギ農家で開発した堆肥を加えることで、最適な土壌に導くことを目指しています。地力バランスは土壌の「物理性」「化学性」「生物性」の3つの指標で評価され、「物理性」は排水性や通気性など、「化学性」はpHや養分など、「生物性」は微生物などの量や活発さで評価されます。
しかし、ミヤギ農家では「物理性」「化学性」の評価は上手くできたものの、「生物性」の部分では課題があったんです。そこで、ゆがふぁーむは生物性、つまり微生物に着目することにしました。先ほどビジネスプランの背景として土壌劣化などの話をしましたが、もう1つの背景としてはミヤギ農家が挙げられるわけです。「from ミヤギ農家」は、ただ単に名前を借りただけではありません(笑)
―そして、「ゆがふぁーむ(from ミヤギ農家)」として第2回高専起業家サミットに出場されました。サミットの感想を教えてください。
大嶺さん:ピッチに関しては、練習やリハーサルのときよりもクオリティ高くできたかなと思っています。その場の独特の空気を感じつつ、聞いている方々の表情を見ながら発表できたので、ものすごく楽しいピッチになりました。

大嶺さん:交流会では、同じ年代で志の高い高専生たちと交流できたので、刺激をもらえました。「自分はもっと頑張れるのではないか」という悔しさも感じましたね。
石垣さん:私は交流会を通じて「高専生マインド」——つまり、自分たちの技術で社会に貢献するという気概は、どの高専生も共通して持っているんだと感じました。私は沖縄高専という離れた場所にある高専の学生ですので、他校の高専生とさまざまなことについてディスカッションできたことが楽しかったです。

―これまでの経験を踏まえて、起業を考えている現役の高専生へアドバイスを送るとしたら、どのようなことを伝えたいですか。
大嶺さん:私はゆがふぁーむに携わる前から「起業したい」と考えていたのですが、目指している起業の内容だと、生物系の私には情報系の技術力が足りないのではないかと、すごく悩んでいた時期がありました。
ゆがふぁーむのメンバーには石垣や私といった生物系の学生以外にも、技術力を持った情報系の学生がいます。そういったメンバーが身近にいると、「高専生は普通の人よりも技術力やスピード感があるな」と強く感じますし、それが起業における大きな強みになると思っています。ぜひ頑張ってほしいです。
石垣さん:まだ4年生なので、起業についてどうこう言える立場ではないですが、高専での5年間は、大学受験もなく、自分のやりたいことができる期間だと捉えることができます。起業を目指すには十分な時間があるのではないかと思います。
そして、国立高専機構がアントレプレナーシップ教育を強化するために環境を整えようとしている現在において、自分の中にある「やる/やらない」のマインドやパッションは、より重要になってくるはずです。波に乗れるときに乗ったほうが良いと、私は思います。
◇
<お知らせ>
【第3回 高専起業家サミット】(主催:国立高専機構、月刊高専)の開催が決定しました。
現在プレエントリーを受付中です(2025年9月11日(木)まで)。
募集要項などの詳細はHPをご覧ください。
https://startup.gekkan-kosen.com/
沖縄工業高等専門学校の記事



アクセス数ランキング

- 「まずはプラズマを当ててみよう」! 失敗を恐れずまずは行動。研究の魅力は「なぜ」から始まる
- 大島商船高等専門学校 電子機械工学科 教授
中村 翼 氏


- 高校で選ばなかった「生物」を研究へ。蛋白質研究を軸に“学び続ける研究室”を育てる
- 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教
早乙女 友規 氏

-300x300.jpg)
- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと
- 鹿児島工業高等専門学校 校長
上田 悦子 氏


- 「自分はどうありたいか」で考えれば将来は無限大。高専を卒業し、今はスポーツビジネスの現場へ
- アイリスオーヤマ株式会社 会長室
株式会社ベガルタ仙台 ファシリティマネジメント部(業務委託)
武市 賢人 氏

-300x300.png)
- “女子は無理”と言われた時代を超えて──長い研究人生の先で挑む、高専での技術者教育
- 奈良工業高等専門学校 校長
近藤 科江 氏

- 「パワーバランスが取れた公平な訴訟」を目指して。「法律」という武器をつくって磨く、鍛冶屋になりたい!
- 広島商船高等専門学校 流通情報工学科 准教授
金子 春生 氏




-300x300.png)