
国立高専機構と月刊高専が主催した【第2回高専起業家サミット】のプラチナスポンサーである本田技研工業では、新事業創出プログラム「IGNITION」を毎年実施しています。人々が持つアイデア・技術・デザインを発掘し、その事業化を支援する「IGNITION」は、2017年に社内従業員向けとして始まりましたが、2024年度からは従業員以外の方を対象とした「IGNITION CHALLENGE(旧:IGNITION一般公募)」もスタートしました。
その初となる「IGNITION CHALLENGE 2024」では、【第1回高専起業家サミット】でプラチナ協賛企業賞「Honda IGNITION賞」を受賞した沼津高専「MIG」のメンバーである蔭山朱鷺さんのアイデア「自分好みのビオトープでロボットと共に植物を育てる“ロビオトープ”」が採択。最終の二次審査までHondaの支援を受けながら事業開発を進めました。
そこで、本記事の<第一部>と<第二部>では、蔭山さんを支援したタスクフォースチーム(TFT)のメンバーであるPMO(Project Management Office)の高野将吾さん、デザイナーの望月鞠花さん、エンジニアの坂田さち恵さんに、蔭山さんへの支援内容についてお伺いしました。また、<第三部>では、2025年の「IGNITION CHALLENGE」などについて、IGNITION運営事務局の松澤拓未さんにお話を伺っています。
※【第1回高専起業家サミット】のプラチナスポンサー取材でも、IGNITIONについてお伺いしています。コチラからご覧ください(高専生のための就職・進学情報サイト「高専プラス」に遷移します)。
<第一部>アイデアベースから事業化/IGNITIONの支援内容
―高野さん、望月さん、坂田さんは、蔭山さんを支援するにあたり、それぞれどのような役割を担っていたのでしょうか。
高野さん:事業開発の一歩目を踏み出すにあたってのマイルストーン設定や予算管理のほか、事業コンセプトの設計、事業開発における顧客インタビューの設計といった、全体的な取りまとめを行っていました。

望月さん:私はペーパープロトタイプの作成が担当です。また、顧客インタビューを一緒に実施したほか、お客様から正しい反応をいただくことを目的とした「実証実験の場づくり」もサポートしていました。
あと、蔭山さんのソリューションは製品として固まっておらず、アイデアベースの段階でしたので、どのような方針で形にしていくのかを、高野さんや坂田さん含め一緒に話していきましたね。

坂田さん:私は蔭山さんのアイデアを原理実証・顧客検証するためのプロトタイプ作成をサポートしていました。
IGNITION CHALLENGEは社内従業員向けとは異なり、Hondaの中からエンジニアが1人つくことになっています。蔭山さんのもともとのアイデアが「人と植物の間をつなぐロボット」に着目したものでしたので、以前より「人」と「ロボットやシステム」のコミュニケーションについて研究していた私にお声がかかり、エンジニアとして参加することになったのです。

―蔭山さんのロビオトープのアイデアを初めて知ったとき、どのような印象を受けましたか。
高野さん:アイデアベースではあったものの、蔭山さんのピッチ(短いプレゼンテーション)を見て、環境や生態系に対する危機感が十分に言語化されていると感じました。
さらに、それを危機として捉えるだけでなく、「自分ごととして将来的に解決したい」「その解決に向けて踏み出す人を増やしたい」といった明確な問題提起や、次世代の人たちへの目線があったことが素晴らしかったです。
望月さん:「私がイメージしていた高専とは違う」と感じました。テクニカルなことだけではなく、「子どもたちのワクワク」や「体験価値」をすごく重視していて、時代が変わったと思いましたね。そして、そのアイデアを自分が持つ技術で叶えたいと本当に考えていらっしゃったのが印象的でした。
高野さん:蔭山さんの提案は、普段Honda内で取り組んでいる課題解決型のテーマとは少し異なり、どちらかというと価値提案型でした。だからこそ、アイデアベースだった蔭山さんの提案を、「何をしたいのか」や「どういう世界をつくりたいのか」といった観点からまず言語化する必要があると考えましたね。
―蔭山さんを支援するにあたり、各段階でどのような目標設定をしていましたか。
高野さん:最終的な目標としては、私たちの支援がなくても、蔭山さんがその後の事業を円滑に進められる——その一歩目を踏み出せるようになることをイメージしていました。
そのための最初の目標は、アイデアベースだった事業プランの言語化です。そして、ソリューションをペーパープロトタイプとして具体化させ、顧客検証をするというPDCAを繰り返しました。赤坂の当社オフィスで週1回ほどの対面ミーティングをチームメンバーで実施し、言語化やソリューションの具体化に時間を割きましたね。
望月さん:週1回ぐらいのペースでミーティングをするのが私たちIGNITIONにとっての“当たり前”でした。一般的に見られる「企業の人が学生を支援する」といったプロジェクトと比べると、かなり多いのではないかと思います。静岡の沼津から毎週しっかりとミーティングにいらっしゃる蔭山さんの姿勢には、フレッシュさを感じました。
高野さん:ソリューションが固まった後は、事業化に向けた資金調達先と円滑にコミュニケーションが取れるように、ソリューション含めた事業提案をピッチに落とし込むことを目指しました。
―坂田さんはいかがですか。
坂田さん:私はチームメンバーから生まれるアイデアをいかに実現するかを考えて開発を進めていました。
しかし、話し合いながら仕様を決定していくので、開発中にはさまざまな変更があったんです。結果、最初は「植木鉢の横にいる、動かないロボット」だったのが、最終的には「植木鉢を上に乗せ、カメラをまるで顔のように動かしながら、車輪で動き回るロボット」になりました。さらに、コミュニケーションの部分だけを切り出し、スマートフォンのアプリとして楽しめるようにしました。
つまり、最初はロボットだけを開発するつもりが、ロボットとアプリという「2つのプロトタイプ」を開発したことになります。変更がたびたび起こりますので最終的な目標を設定することは難しかったですが、アイデアは形にしてみないと面白いかどうかわかりませんので、都度生まれるアイデアをモノとして実現できるよう集中していました。
※ IGNITION CHLLENGE参加中の蔭山さんの対談記事もコチラからご覧ください(IGNITION公式サイト「一般公募採択者 特別対談Vol.1」に遷移します)。
<第二部>事業化を目指すのに必要な力
―IGNITIONの期間中、蔭山さんの姿はどのように映っていましたか。
坂田さん:何度も起こるソリューションの変更を全部受け入れていたのがすごかったです。「そういうアイデアも面白いですね」とおっしゃっていただき、とても開発しやすい環境でした。
望月さん:蔭山さんからはさまざまなことを学びました。特に学んだのは、社会人としての学生との関わり方です。未来のある学生だからこそ悩みが多かったり気持ちが傾きやすかったりすると思い、これからどう生きていくのかを熱く話したこともあります。私自身、学生を支援することは初めてでしたので、勉強になりました。
高野さん:蔭山さんは事業開発のご経験がない状態でIGNITIONに応募いただいたので、本当に分からないことだらけだったと思います。しかし、自身が理解していること/理解できていないことをちゃんと言葉にすることで私たちとコミュニケーションを取ろうとされる姿勢を見て、言語化することの大事さを改めて学びました。
―蔭山さんは、最終の二次審査でどのような結果になったのでしょうか。

高野さん:最初に設定した出口は、「VC(ベンチャーキャピタル)から資金調達を受けて、かつシナジーがあればHondaからも出資を受ける」でした。しかし、結論から申し上げますと、蔭山さんと当時の事業開発の状況を話し合った結果、VCから調達および出資を受けるという着地にはしませんでした。よって調達には至っていません。
しかし、顧客検証の結果を受けて、Hondaの関連子会社から「プロダクトを実際にローンチできるように、2025年度もぜひ検証を続けたい」というお話をいただきました。この機会を蔭山さんにはぜひ活かしていただき、今後事業化に繋がることを願っています。
―起業を目指す高専生にアドバイスをお願いします。
高野さん:高専生の武器である技術力を「強み」としてはっきりと表明してほしいです。しかし、技術力は「How」です。それだけでなく、なぜそれをやりたいのか、つまり「Why」の部分も合わせて持っていてほしいと思います。「Why」があれば、私たちタスクフォースチームが何とかします!
望月さん:「Why」はピッチのストーリーづくりにも必要とされますが、自分のためにも必要だと考えています。中途半端な信念だと、事業化は難しいです。「自分が絶対にしたいこと」と「自分ができること」が重なっている部分は一体何なのかを明確にすると良いと思います。
坂田さん:私は「Why」以外にも「What」——つまり「何を実現するのか」が重要であることをお伝えしたいです。
「What」のポイントは、アイデアの「シンプルさ」と「強さ」です。最近では、ハードウェアであれば3Dプリンタ、ソフトウェアであれば大規模言語モデルのサポートもあって、経験がない人でも短時間である程度のクオリティが担保されたモノを実現できるようになっています。だからこそ、「シンプルさ」と「強さ」があることで、「何をつくりたいのか」「どこをどう改善するべきか」の焦点が定まり、より良いモノが実現できるのです。
そして、事業アイデアにおいては「What」だけでなく、「コスト」と「信頼性」も重要だと思います。コストと信頼性には強い関係性があり、信頼性が低いものを使うと、後々どんどんコストがかかります。ですので、できるだけシンプルなアイデアから信頼性の高いモノをつくり、それを育てていくことが重要だと思います。
高野さん:あと、蔭山さんと事業化を進めている際にはさまざまな課題が出てきましたが、そういう状況下では「検証し続ける胆力」と「フットワークの軽さ」が必要です。それは起業した後も同様に求められる能力だと思いますよ。
<第三部>IGNITIONは高専生に適している? 2025年度のIGNITION CHALLENGEについて
―2024年度から一般公募である「IGNITION CHALLENGE」が始まりました。その理由を教えてください。
松澤さん:Hondaでは創業以来、ブランドスローガン「The Power of Dreams」にあるように、夢の力で新しい価値を創出し続けてきました。その原点にあるのは、創業者である本田宗一郎の「社会や人の役に立ちたい=社会課題を解決したい」という想いです。
IGNITIONの目的も社会課題の解決であり、熱い想いを持っている社外の方もご支援しようと考えたのがIGNITION CHALLENGEを始めた理由です。また、社外の方のアイデアと私たちの技術や知見を組み合わせることで、さらに新しい価値創造につながることも期待し、IGNITION CHALLENGEはスタートしました。

―初めての「IGNITION CHALLENGE」。その手ごたえはいかがでしたか。
松澤さん:学生の蔭山さんに加え、大学教授の方、大学発スタートアップの方と、出自の違う3名の方々にご支援させていただきましたが、みなさまから「このプログラムに参加してよかった」とのお声をいただいています。
これまで私たちが社内従業員向けのIGNITIONで行ってきた価値提供が、社外の方からも価値として感じていただけるのかが不安でしたが、手応えとしては良いものが得られました。

―2025年度もIGNITION CHALLENGEが実施されます。2024年度を踏まえて変更した点はありますか。
松澤さん:大きな枠組みで捉えると変更点はそこまでありませんが、募集対象を「日本国内における起業を目指す個人又は設立から3年以内の日本登記の法人の代表者、又は同法人に所属する者」から、「日本国内における起業を目指す個人」に絞ります。
というのも、2024年度のIGNITION CHALLENGEで私たちが1番価値を提供できたのが蔭山さん、つまり「日本国内における起業を目指す個人」だと考えているんです。もともとIGNITIONで行っていた「社内従業員のアイデアを募集し、事業化の0から1までを支援する」という点で、蔭山さんは一番フィットしていました。そこで、私たちが一番得意とするところに重点的にリソースを投下したいと考え、募集対象を変更するに至ったのです。
また、これも蔭山さんの成功事例をもとに変更した点なのですが、一次審査と二次審査(2025年度から「デモデイ」に変更予定)の2つの審査の間に「マッチングデー」を設け、Hondaの事業部や技術研究所とPoC検証(概念実証)などの面で何かコラボレーションできないかマッチングしようと考えています。
これは、IGNITIONが終わった後もHondaとご一緒できるかどうかを探索することを目的としています。蔭山さんが最終的にHondaの関連子会社と協業することになったのは、IGNITIONの期間中からその会社と一緒に価値検証をしていたからだと考え、「マッチングデー」の設置を決定しました。
―高専生に向けてIGNITION CHALLENGEをPRするとしたら、どういった点を伝えたいですか。
松澤さん:やはり「手厚い伴走支援」です。IGNITION CHALLENGEでは、Hondaの社員も「自分の事業」だと思って本気で支援します。PMOでしたらリサーチや事業計画の策定、さらには資本政策まで考えますし、エンジニアも現役のHondaの社員が参加してモノをつくります。
そして、デザイナーによる支援は、IGNITION CHALLENGEの大きな特徴です。新規事業をつくるうえで、デザインの力は大きな役割を果たしています。それは単純に「モノをデザイン」するだけでなく、自分は何によって世界をどう変えていきたいのかを人にはっきりと伝えるために「世界観をデザイン」することも含まれます。IGNITION CHALLENGEでぜひデザインの力を体感いただきたいです。
―最後に、起業を目指す高専生にメッセージをお願いします。
松澤さん:個人的な考えにはなりますが、高専生にはすごく可能性を感じているんです。高専は地域に密着しているので、地に足をつけて地域課題と向き合うことができる環境ですし、それを解決するための技術も高専生は持っています。最近はアカデミア発スタートアップが盛り上がっていますが、「高専生」と「地域の社会課題を解決する事業で起業すること」の親和性は高いと考えています。
あと、私は「自分の技術やアイデアで世界をこうしていきたい」といった強い想いが大切だと思っています。実際、起業までたどり着く方は、やはり強い想いを持っています。社内従業員向けIGNITIONで活躍している方の中には高専卒社員もおり、高専生や高専を卒業された方の多くは強い想いを持っていらっしゃる印象です。
そして、私たち社会人側には「若い方をサポートしたい」と考えている方が多いこともお伝えしたいですね。年齢が若いうちにどんどんチャレンジしていただいて、社会課題を解決する事業を生み出してほしいです。IGNITION CHALLENGEへのご応募、お待ちしています!
◇
○IGNITION HP
https://global.honda/jp/ignition/
○IGNITION CHALLENGE HP
https://global.honda/jp/ignition/public_submission/
沼津工業高等専門学校の記事



アクセス数ランキング

- 実験指導から組織運営まで。学生の「できる」を信じて、一番近くで成長を支える技術職員の仕事
- 鈴鹿工業高等専門学校 教育研究支援センター 技術長
鈴木 昌一 氏
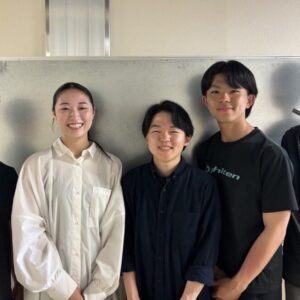

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡
- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師
盛田 有貴 氏



- 活動の源は世界平和! 環境にやさしい持続可能な木造建築を追求し、40代で研究者の道へ飛び込む
- 米子工業高等専門学校 総合工学科 建築デザインコース 助教
川中 彰平 氏



- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む
- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教
久保田 翔大 氏









