
富山高専を卒業し、現在は滋賀大学で大学生活を送る松本彩夏さん。高専時代は、研究活動はもちろん、学生会にダンスと、多彩な分野で結果を出されています。大学卒業後はエンタメ会社でマーケティング職として働くという松本さんに、高専時代の思い出や、大切にしている生き方について伺いました。
ダンスと英語の2つの軸が自分を支えてくれた
―松本さんの幼少期はかなりアクティブだったそうですね。
小さい頃、テレビでたまたま観た英会話教室のCMがとても楽しそうに見えたんです。そこから「やりたい!」と親にお願いして、英語を習い始めました。街中で外国の方を見かけたら、拙い英語ながら話しかけていました。高専に入学するまで英会話教室に通い続けたのですが、自分の読み聞きできる文章が増えることが嬉しかったです。当時からの積み重ねで、現在はTOEIC900点を超えるまでになりました。
また、ダンスにも力を注ぎました。テレビで観たパフォーマンスに衝撃を受けたのがきっかけです。EXILEのライブステージで、バックダンサーがボーカルの目の前まで出て踊る姿を見て、「こんなに魅せるダンスがあるんだ!」と強い衝撃を受けました。そこからプロバスケットボールチーム「富山グラウジーズ」の専属ダンスチーム育成スクールに入り、シーズン中はダンサーとしても活動しつつ、同時並行で通っていた別のダンススクールのオーディションを受け、中学2年生では全国大会を目指して活動していました。

中学3年生になると受験に向けてレッスンの頻度は減りましたが、その代わりにワークショップを開いたこともあります。振付や技術を地元の小さな子どもたちに教えるのが楽しくて、ダンスを通じて周りとつながる喜びを知りました。

―松本さんが富山高専に進学されたきっかけを教えてください。
中学校の担任の先生に「英語と、興味があるビジネス分野を軸にして進学先を考えたい」と伝えた際、「一般的な高校とは少し違う学校がある」と高専を紹介していただきました。早い段階から自分が興味のあることを勉強した方がいいと感じ、そこからは「絶対に高専に行きたい!」と思いました。
入学したての頃は周りの学力の高さに驚きましたね。中学までの自分の感覚でいると、あっという間に置いて行かれそうになるんです。でも逆に言えば、そうしたレベルの高い仲間がたくさんいるのは刺激でもあって、「もっと勉強しよう」と意欲がかき立てられました。
印象深い授業としては、田嶋先生が担当されたマーケティング論が面白かったです。田嶋先生は民間企業のご出身かつ高専OBで、実際に企業で働かれていた頃のエピソードや、広告を分析する視点を教えてくださいました。街中に貼ってある広告が、どんなターゲットに向けて、どんなデザインでつくられているかを意識するようになり、「売れる仕組み」の知見が広がりました。
―高専でもダンス部に所属されたそうですが、そこでの思い出を教えてください。
ダンス部は、私の青春の大半を占めるほど大きな存在です。入部した時から目標としていたことが2つありました。「全学生を自分のファンにするぐらい頑張ること」と、「高専でダンス人口を増やすこと」——それを叶えるために、たくさん行動しました。
コロナ禍では自分でInstagramのライブ機能を使ってダンスのレッスンをし、それでダンスに興味を持ってくれた友達や後輩とも繋がることができました。コロナが明けた後、オンライン上で繋がっていたメンバーと実際にステージで踊ることができたのは、すごく思い出深いです。
また、次第に部員の数が増えて、それぞれ違うダンスジャンルに挑戦したいというメンバーが集まると、振付や曲の構成をどうまとめるか頭を悩ませることも多かったです。それでも、みんなで話し合いを重ねながらステージを作り上げるプロセスは本当に楽しくて、4年生最後の文化祭(北斗祭)では「自分たちがやりたいこと全部盛り!」という勢いで完成度の高いパフォーマンスに仕上げました。

ジャンルとしてはヒップホップとR&B、KRUMP(クランプ)、スタイルヒップホップがメインだったのですが、その中でもスタイルヒップホップはそれまでのダンス部にはなかったもので、私が取り入れました。友情や絆を歌った曲に合わせて、それが滲み出るような振り付けをつくり、とてもいいステージになったと思います。私たちの代はいろいろなジャンルでダンスをしたいメンバーが多かったので、多彩なジャンルを後輩たちに残すことができました。
―学生会の副会長も務めていたそうですが、こちらはどのような活動をされていたのでしょうか。
4年生の時に学生会の副会長としてイベントの企画運営などを担当しました。特に印象深い思い出が球技大会です。それまでは本郷キャンパスと射水キャンパスの合同で行っていたのですが、参加する学生の満足度を高めるために、各キャンパスでの開催を提案しました。
学校側としては、「交流する場をつくるためにも合同でやった方がいいのではないか」という意見だったのですが、タイムスケジュールが合わなかったり、帰宅が遅れて不満が出たり、運営も分散してしまって難しいという問題があったんです。
そこでそれぞれのキャンパスごとで行ったところ、結果的には運営面がスムーズになり、楽しかったという声もたくさんもらえました。当日まではミーティング続きでとても大変でしたが、「視点を少し変えるだけでイベントがこんなにも盛り上がるんだ」と学べた経験でしたね。

―卒業研究はどのようなことをされましたか。
卒業研究では、論文を書くことをただの作業にしたくなかったので、論理的思考力を学べる宮重先生のゼミを選びました。
宮重先生は経営学の授業で、「私たちの日常で言うと、こういうことだよ」と、身近な例を出しながら教えてくれるんです。例えば「このXY理論は、アルバイトをただお金をもらうためだけにしている人はX理論的、自己実現のためにしている人はY理論的だ」と、分かりやすく落とし込んでくれたので納得感がありました。
卒業研究では「ブランド・コミュニティにおけるコミュニケーションがブランド・コミットメントを向上させるプロセス」というタイトルで論文を書きました。具体的には、同じ商品が好きな人同士が情報交換をすることで、どのようにブランドへの愛着が増すかという分析です。私はこれをスターバックスの事例を取り上げながら考察しました。
事例調査を行ったところ、スターバックスの場合は、好きなドリンクだけでなく、店舗そのものの雰囲気やサービスに対して共通の価値観が生まれやすい点が興味深かったです。そうした「ファン同士のやり取り」が、結果的にブランドへの好意をさらに高めるまでのプロセスを分析しました。
一番大変だったのは、論理を矛盾なくつなげていく作業です。レジュメをつくった段階では、私の中で「この論理とこの論理はつながっている」と思っていても、宮重先生に「コインの表裏を見ているだけ」と指摘をいただくこともあり、頭を悩ませましたね。
―卒業後、編入学先として滋賀大学を選んだ理由を教えてください。

最初は地元にも残りたい気持ちがあって専攻科も考えたのですが、高専で幅広くビジネス分野を学ぶうちに「より深く経営学やマーケティングを究めたい」という思いが強まり、滋賀大学の経営学部に編入学することを決めました。経営学を軸にしながらAIやデータサイエンスも学べるカリキュラムが滋賀大学にはあったんです。

大学3年次には組織論やリーダーシップ論をメインに研究するゼミに入り、そこで「破壊的リーダー」と呼ばれるパワハラ型のリーダーや、部下のモチベーションに関するグループ研究に取り組みました。高専時代にはブランドや消費者コミュニティといった企業の外の人に向けた戦略部分を学んだので、今度は企業の内部の人に焦点を当てたいと思いました。
破壊的リーダーはパワハラ型のリーダーであり、結果的に組織や部下のモチベーションを破壊してしまうのですが、一方で、社外から見れば功績を残す変革型カリスマリーダーという評価を受けるケースもあります。最終的には、立場や見方によってリーダーの姿は違うのではないかといった仕方でそれぞれ分析しました。
グループ研究は初めてだったので、グループで1つの結果を出すためにはどういう動きをすればいいのか、とてもいい経験になりました。特にみんなが持つそれぞれのアイデアのすり合わせが大変でしたが、高専時代に論文執筆を経験していた分、「研究をどう進めるか」についてはイメージがしやすく、改めて高専で培った土台の大きさを感じました。
“Real eyes, Realize, Real lies.”
―卒業後はエンタメ系の企業でマーケティングを行うそうですね。
はい。エンタメ企業のマーケティング職として内定をいただき、来年からはデジタルマーケターとして働く予定です。
就職活動中は沢山のインターンシップに参加しました。特に印象に残ったインターンシップでは、実際に扱っているクライアントの商品の広告をインターン生が制作し、実際に広告運用していただいたのですが、広告の表示から購入まで進むにつれて人数が減っていき、結果的には購入者がほとんど出ませんでした。「こんなに悔しいことがあるのか」と思うほどショックを受けましたが、同時に「なぜ売れなかったのか」という仮説を立てて検証を進めるプロセスがとても勉強になりました。

就職の決め手になったのは、企業理念や企業の考え方に共感したことと、「人の心を動かす力」をいち早く身につけられそうだと感じた点です。私は将来、マネージャーとしてもプレーヤーとしても活躍できる人材になりたいので、まずは現場でプレーヤーとしてどんな商材でも売り出せる力を身につけ、その先にマネージャーとして組織を動かしていきたいと考えています。
―残りの大学生活は、どうしていきたいですか。
今後は大学生らしい1年を過ごしたいと思っています。勉強だけでなくアルバイトや遊びも全力投球していくつもりです。また、大学院の授業を受講できるプログラムも活用し、学べるものは可能な限り吸収したいという気持ちでいます。

私が好きな言葉で、ラッパーの2Pacが言ったとされる「Real eyes, Realize, Real lies.」(※)があります。「真実の眼で嘘を見抜け」という意味です。私たちの世代は、いろいろな情報が取りやすい時代に生きていますが、流れてきた情報を鵜呑みにするのではなく、たくさんの見方を持っておきたいです。
※編集部注:「Real eyes, Realize, Real lies.」は2Pacの言葉として紹介されていることが多いが、2Pacがこれまで残したメッセージなどと親和性が高いフレーズではあるものの、このフレーズそのものを公式に使った記録はない。ストリート文化などから自然と生まれた可能性もあり、作者不詳となっている。
また、「自分がこれをやりたい」と思ったときに、すぐにそれを実行できる自分でいたいという気持ちはずっとあります。将来の自分が後悔しないために行動できるのは今の自分だけだと思うので、これからも日々コツコツと積み重ねていきたいです。
―最後に高専生へのメッセージをお願いします。
高専は明確な意思がある人、やりたいことが決まっている人にとってはすごくいい環境だと思います。逆に、それがないと苦しいと思うので、その時は高専を選んだ理由を思い出してほしいです。もし「自分は何のために高専にいるんだろう」と悩むことがあれば、まずは周りの人に相談したり、興味のあることを徹底的に試してみたりするのがおすすめです。
私は授業やゼミ、部活や学生会など、本当に高専生活を楽しみ尽くしました。友人曰く、私は「タイムスケジュールの鬼」なのですが(笑)、期限に対してバッファを設けつつも、ストイックに取り組んだことが、自分の世界を広げてくれたと思います。
ぜひ、高専生の皆さんも自分の合うやり方を見つけて高専生活を楽しんでください。5年間という時間があるからこそ、自分の興味あることだけではなく、興味のないことまでぶつかりに行ってほしいです。その先に自ずと自分のやりたいものが見つかると思いますよ。
松本 彩夏氏
Sana Matsumoto
- 滋賀大学 経済学部 企業経営学科 4年

2024年3月 富山高等専門学校 国際ビジネス学科 卒業
2024年4月 滋賀大学 経済学部 企業経営学科 編入学
富山高等専門学校の記事



アクセス数ランキング
-300x300.jpg)
- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと
- 鹿児島工業高等専門学校 校長
上田 悦子 氏

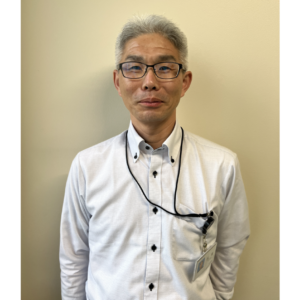
- 世の中で一番強い形は○○!? 12年間に及ぶ国内最難関のトンネル工事に挑む
- 清水建設株式会社 北海道支店 土木部 部長
松尾 勝司 氏

- 「学びたい」を原動力に、金融×ITの最前線へ。成長意欲が連鎖するNTTデータフォースでの、高専卒社員2人の姿
- NTTデータフォース株式会社 北海道・東北ビジネス本部 チーフ
小田中 拓馬 氏
NTTデータフォース株式会社 システム開発事業本部 本部長
有田 久幸 氏


- 母校で社会実装に励む。地域の未来を見据え、本当に必要な支援ができるのは高専だからこそ
- 鳥羽商船高等専門学校 情報機械システム工学科 教授
江崎 修央 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡
- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師
盛田 有貴 氏


- 自ら教え続け、研究し続ける“現役”の校長——立場が変わっても貫く「人づくり」の教育
- 函館工業高等専門学校 校長
清水 一道 氏




-150x150.jpg)







