
幼い頃にテレビで観た“匠の仕事”に憧れ、木更津高専の環境都市工学科へ進学した石久保将也さん。現在は新潟県の佐渡島の企業で、現場監督として地域インフラを支えています。土木の知識と経験を土台に新たな分野に挑戦する石久保さんに、これまでの歩みをお伺いしました。
ものづくりへの興味に導かれ、高専へ
―高専に進学したきっかけを教えてください。
小学生の頃に夢中で観ていたテレビ番組「大改造!! 劇的ビフォーアフター」がきっかけです。様々な問題を抱えた戸建て住宅が「匠」と呼ばれる一流建築士のリフォームによって劇的に大変身する様子が紹介されていて「ものづくりでこんなに人を喜ばせることができるんだ」と感動したのを覚えています。以来、自分も誰かのためになる仕事がしたいと思うようになりました。
そんな姿を見ていたからか、ある日、母が木更津高専の環境都市工学科を紹介してくれたんです。建築でこそないものの、道路や橋、トンネルといった公共構造物をつくる仕事に関わるのも楽しそうだと思い、説明会やオープンキャンパスに行ってみると、校舎が広くて学生寮もあり、自分が想像していた「学校」のイメージと大きく違っていたことに強く惹かれました。何より、5年一貫制という点が普通高校とは大きく異なり、人と違うことが好きだった自分にとっては非常に魅力的でした。
―高専に進学してみて、ものづくりに対する熱意はどう変わりましたか。
.jpg)
入学してからは、その思いはより一層強くなりましたね。公共構造物をつくる仕事に興味があった私にとって、必要な知識がたくさん得られる環境では毎日が新鮮で、やはりこの分野で仕事をしていきたいという気持ちが増しました。
1年次から土木技術研究同好会にも所属し、とにかくコンクリート尽くしの5年間でした。コンクリートでカヌーをつくったり、文化祭用にモルタルでモアイ像をつくったりもしていました。卒業研究も「フライアッシュセメントを用いたコンクリートの基礎的性状」をテーマにしました。
.jpg)
―卒業後、大学進学を選んだのはなぜでしょうか。
入学当初は就職を目標にしていたのですが、大学に編入する道もあると知り、次第に進学に興味を持ちました。また、さまざまな分野に触れる中で「もっと幅広い研究に携わってみたい」と思うようになったことも決め手です。長岡技術科学大学を選んだのは、恩師である青木先生をはじめ、お世話になった先生方の出身校として安心感があったことが大きな理由でした。
トンネル構築に尽力し、やがて佐渡島への移住で新たなスタート
―大学での思い出を教えてください。
学部3年次の1月から3月にかけて、休暇を利用してベトナムに行きました。また、企業や海外の大学、国内外の研究機関等に派遣する「実務訓練(長期インターンシップ)」という制度を利用して、マレーシアのマラ工科大学(UiTM)に5カ月留学したこともあります。現地の土質試料を採取して「湿潤崩壊」という現象について研究していました。
.jpg)
当時はTOEIC400点くらいの英語力だったため、試験方法や文献の翻訳、現地の教授とのコミュニケーションに苦労しましたね。しかし、せっかく行ったのに狭いコミュニティにとどまっていたらもったいないと、下手なりにも関係を築こうと、翻訳アプリを駆使しながら頑張りました。おかげで、マレーシアやインドネシア、韓国、日本人留学生も含めたくさんの友人と出会うことができました。
.jpg)
大学院修了後に建設コンサルタントを志望したのも、この経験を通じて、インフラが十分に整っていない新興国の社会基盤整備に携わりたいと考えるようになったからです。結果的には、大学院時代に携わっていたシールド工法の研究実績を買っていただき、トンネル設計が強みのグループ会社に技術研修出向することになったわけですが……(笑)
―大学院時代に取り組んでいた、シールド工法の研究について教えてください。
シールド工法とは、シールドマシンという掘削機で地盤を掘り進めると同時に、セグメントと呼ばれる円弧状のブロックを組み上げ、トンネルを構築する工法です。都市部のような地下空間が複雑化している場合や軟弱地盤を含む多様な地質条件で採用されています。例えば、東京湾アクアラインのトンネル区間はシールド工法で施工されています。
私が研究していたテーマは、主に「シールド機操作条件の挙動に与える影響」と「シールド蛇行修正アルゴリズムのセグメント割付に関する研究」の2つ。こうしたシールドに関する研究業務をする企業は多いのですが、大学で専門的に取り扱っているところは、実は少ないんです。
長岡技科大にはこの分野で有名な先生がいたこともあり、「シールド分野を極めたら、社会に出たときに重宝されるのではないか」と思い、研究テーマに決めた経緯がありました。ですので、入社先でこの研究実績を認めていただけたのはありがたかったですね。入社した年の8月に出向し、主に地盤を掘削してトンネル本体を構築し、その後埋め戻して構築するという「開削トンネル」や、「シールドトンネル」の構造設計、施工計画の業務に従事していました。
.jpg)
そして、3年目になるタイミングで、当時お付き合いをしていた新潟県の佐渡島出身の妻と結婚し、2024年に島への移住を決意しました。現在は、妻の実家が代々経営する中野工業建設会社に入社し、現場監督として、道路の改良工事や舗装工事などの施工管理業務を担当しています。
―佐渡島という新天地で仕事を始めて、いかがでしたか。
前職の設計業務を主とした仕事とは内容も規模も大きく異なるので、まだ試行錯誤中の部分はありますが、工事に携わった道路が形になり、地域の方々が不便なく使っている姿を見るのは非常にうれしいです。その意味では、高専に進学するきっかけとなった「ものづくりで人を喜ばせたい」という願望は叶えられていると思います。
また、建設会社ではありますが、佐渡島内の空き家問題や宿泊施設不足に対応するため、古民家を再利用した民泊事業のサポートも手掛けています。これまで経験してきた環境と違う点も多々あり、最初は戸惑いもありましたが、関わってくださる皆さんと力を合わせて一つのことを成し遂げる日々はやりがいに満ちあふれています。
.jpg)
―今後、実現したいことはありますか。
佐渡島は都心部と違い、競合する建設会社が入ってきづらいため、技術力を磨いたり新しい技術を取り入れたりといった取り組みが、本土と比べるとどうしても遅れてしまう傾向にあります。私一人の力でどうにかできる問題ではないものの、この現状を変えられないだろうかと日々考えています。
例えば、近年は自動化やデータの活用で現場業務をスマートに改善する「建設DX」が進んでいますが、今後はこうした情報を少しずつ取り入れながら、今ある資源を有効に生かして佐渡島に貢献していきたいですね。
.png)
―最後に、高専生にメッセージをお願いします。
私は高専の環境都市工学科で土木や環境について学びました。でも、在学中に感じたのは、学科の枠にとらわれず、ほかの分野にいくらでも挑戦できるということです。同時に、学んだ分野と同じ業界に就職しなければいけない決まりもありません。まったく違う分野に進んでも、高専で得た経験や考え方は、必ずどこかで生きてくるはず。だからこそ、自分の将来を狭い視野で決めつけず、もっと自由に選んでほしいと思います。
.jpg)
これから高専を目指す中学生のみなさんは、まず一度、実際に高専を見に来てください。普通高校に比べると異なる点は多々ありますが、それ以上に得られるものがたくさんあります。先生方はユニークでフランクに話せる方ばかりですし、自由度が高く、自分で動くからこそ成長できる環境は、学びの場としてとても魅力的です。特に「人と違うことをしてみたい」と思うなら、高専はおすすめです。きっと新しい世界が広がりますよ。
石久保 将也氏
Masaya Ishikubo
- 中野建設工業株式会社 土木部
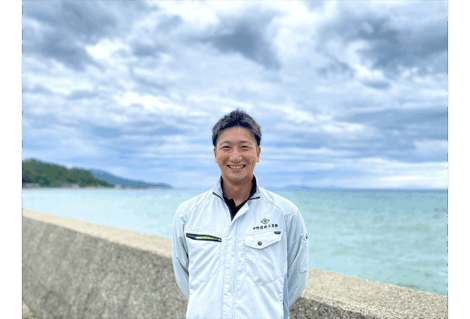
2018年3月 木更津工業高等専門学校 環境都市工学科 卒業
2020年3月 長岡技術科学大学 工学部 環境社会基盤工学課程 卒業
2022年3月 長岡技術科学大学大学院 工学研究科 環境社会基盤工学専攻 修了
2022年4月 日本工営株式会社 入社
2022年8月 日本シビックコンサルタント株式会社(日本工営株式会社グループ会社) 出向
2024年10月より現職
木更津工業高等専門学校の記事



アクセス数ランキング


- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡
- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師
盛田 有貴 氏

- 高専卒のマネージャーとして奮闘中! 全国から150名以上の高専生を採用するAmazonが「毎日が始まりの日」の精神で取り組む仕事とは
- アマゾンジャパン合同会社 RME Site Mainte Area Manager
小久保 大河 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む
- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教
久保田 翔大 氏


- AI技術やシステム開発で社会にインパクトを。テック領域の最前線を切り拓くトップリーダー
- 株式会社ベクトル 執行役員兼グループCTO
株式会社オフショアカンパニー 代表取締役
野呂 健太 氏

- チャンスを掴めば、見える景色が変わってくる! 目の前にある機会を活かし、中国と日本の橋渡しを目指す
- 株式会社フェローシップ グロキャリ事業部
矢後 英一 氏


- 高校で選ばなかった「生物」を研究へ。蛋白質研究を軸に“学び続ける研究室”を育てる
- 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教
早乙女 友規 氏
-300x300.jpg)
- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと
- 鹿児島工業高等専門学校 校長
上田 悦子 氏




-300x300.png)



