
長年にわたって半導体業界の最前線で活躍し、現在は応用電機の神奈川事業部で事業部長を務める新山尚寿さんは、熊本電波高専(現:熊本高専 熊本キャンパス)の卒業生です。高専時代の思い出から、就職と起業、そして応用電機との合併に至るまで──技術者としてのキャリアの軌跡をお伺いしました。
ものづくりへの興味と、ロボコンに熱中した高専時代
─熊本電波高専の電子制御工学科に入学された経緯を教えてください。
小学生の頃にガンダムのプラモデルづくりに夢中になり、ものづくりへの関心は自然と芽生えていました。父が日曜大工を楽しむ姿を見て育ったことも影響していると思います。そして、中学生の頃に改めて自分の進路を考えた際、「やっぱりものづくりに関わりたい!」と思ったんです。
高専の存在を知ったのは、中学校の掲示板に貼られていた熊本電波高専の募集要項を見たのがきっかけでした。5年間学んだのちに就職できると知り、それが技術者になる最短の道ではないかと考えたのです。
─高専時代の思い出を聞かせてください。
入学してまず驚いたのは、20歳を超える先輩たちの存在でした。失礼な話ですが「おじさんがいる」とカルチャーショックを受けたのを覚えています(笑) 先輩なのか先生なのか、区別がつかないこともありました。
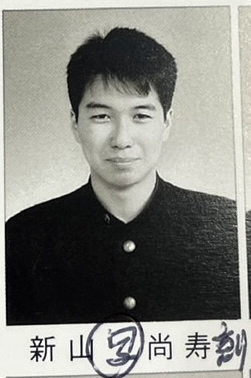
3年生から5年生までは、ロボットコンテスト(ロボコン)に力を入れていましたね。私は当時、熊本電波高専としてロボコン(1990年第3回大会)に出場した初めてのメンバーでした。確か、バスケットボールを転がして、円に入れるロボットをつくったと思います。当時の熊本電波高専には機械科がなかったですが、先輩たちと知恵を絞ってロボットを製作しました。ロボコンは、私の高専生活の中で非常に大きなウエイトを占めていたと思います。
部活動は1年生から2年生まで剣道をやっていました。3年生になると、もう少し華のあることをしたいと思い、軽音楽部でバンド活動に熱中。当時はちょうど第二次バンドブームだったんです。洋楽と日本のロックのコピーバンドを掛け持ちし、ドラムとボーカルを担当しました。

─卒業研究では、どのようなことをされたのですか。
プログラミング言語のLISPを使用した、トランジスタ回路の3次元解析について研究しました。トランジスタ回路を設計する上で必要な設定値や抵抗値などを、手計算ではなくLISPを使用して自動的に解析し、回路に使う最適な値を見つけ出すソフトをつくったんです。
LISPは「人工知能言語」と言われ、当時は流行りの言語だったのですが、これを勉強するのに最初は手間取りました。当時の高専では習わないような言語でしたので、本を買ってきて独学で勉強するしかなかったんです。
また、私は電子制御工学科の1期生だったので、先輩から受け継いだ研究などもありませんでした。自分たちで一から研究テーマを決めないといけない点も苦労しましたね。
半導体検査装置メーカーから起業、そして合併へ
─高専卒業後、アメリカに本社を置くテラダインへの就職を決められた理由について教えてください。
もともとテラダインが熊本に新しく工場を建てることを新聞で知っていた私は、偶然参加した合同会社説明会にテラダインのブースがあるのを見つけました。人事の方と1対1で話をしたところ、なんとその1週間後に「うちに来ませんか」と電話をいただいたんです。即決で「行きます」と返事をしました。
ただ、あまりにもとんとん拍子に話が進んだため、気がつけば学校を通さずに就職先を決めてしまっていたんです。本来であれば、推薦など正式な手続きを踏む必要があり、後で学校からかなり叱られました。
それでも、テラダインの方は「私たちはあなたという人に魅力を感じて雇ったのであって、学校や成績は関係ありません」とおっしゃってくださって、外資系企業ならではの柔軟な考え方や個人重視の文化を感じました。
─テラダインは半導体を中心とした電子部品の自動検査装置メーカーであり、世界トップクラスの企業です。選ばれた理由は何でしょうか。
もともと半導体業界には興味があったのですが、当時から私は「半導体メーカーは、今はすごく売れている企業でも、5年後10年後にはどうなっているかわからない不安定な業界だ」と思ったんです。それなら、製造装置系のメーカーにいる方が長続きするんじゃないかと考えました。小学校の頃から英語を習っていたので、外資系の会社で生かしたいという理由もありましたね。
─テラダインでの仕事は、いかがでしたか。

イメージセンサ(スマホやデジタルカメラのカメラ部分)と呼ばれるIC(半導体)の検査を行うためのプログラムと測定基板をつくる仕事をしていました。
仕事の上では、高専で学んだ電気やソフトウェア、メカの知識が役に立ったと思います。働くようになって技術的な話をされても、何となく直感で、どういう話をされているかがわかるんです。
当時はフィルムカメラからデジタルカメラに移り変わるタイミングで、イメージセンサが売れていく時代の変化を間近で見ることができたことは印象的でした。外資系は成果主義なので厳しいところもありましたが、テラダインで働いたことで、半導体業界に詳しくなれましたね。
─その後に起業され、株式会社iSTを設立されました。きっかけは何だったのでしょうか。
iSTは私が32歳の時に仲間3名で設立した会社でして、「一緒に会社を起ち上げないか?」と誘われ、それについていった形です。車載部品検査装置の製造や半導体製造装置メーカー開発案件のサポートを業務内容としていました。
テラダインを辞めて起業する直前はやはり不安もありましたが、新しいことにチャレンジするワクワク感の方が大きかったです。その後のキャリアを考えた時に、「これまでとは違うことをやってみよう!」と思ったのも、会社設立メンバーに加わった理由です。
ただ、会社を設立した時期は、今までの人生で一番きつかった時期でした。毎月お金が入ってこないと、資本金や銀行から借り入れた手元資金が減っていくので、コンスタントに毎月仕事を取ってこないといけない。これまでは技術者として働いていればよかったのが、経営や営業も自分たちでしないといけない。そういった意味で、つらいことも多かったですね。
アイデアを形にできる、ものづくりの醍醐味
─2007年、応用電機がiSTを吸収合併しました。その経緯について教えてください。
当時のiSTは社員も増え、事業も順調に進んでいたのですが、起業して2年経った頃に数億円規模の検査設備を開発する仕事を受注したんです。その時のiSTにしかない技術力を見込んでいただいたのですが、金額が大きすぎて、小さい会社では資金繰りが難しいのではと考えるようになりました。
そのため、iSTと協力関係にあった応用電機と合併する話になりました。経営者の一員として、社員の方たちが合併で本当に幸せになるのかという点で随分悩みましたが……、そうすることで大きな資金繰りに困らなくなり、結果的に従業員も幸せになると考えて合併に賛同しました。私個人としても「技術者としてお客様が喜んでくれるようなものづくりがしたい」という原点に立ち戻れると思いました。
─応用電機の強みについて教えてください。

応用電機は、半導体から自動車、医療など幅広い業界の様々なお客様向けに、回路、ソフトウェア、メカトロニクス、光学などといったあらゆる技術分野の設計・製造を行っている会社です。毎回、お客様からの依頼で設計・製造を行うため、「オーダーメイドのものづくり」をご提供しています。
電子回路基板の設計だけではなく、ソフトウェアや装置の設計など、対応できる守備範囲が広い点が強みです。例えば、どれか一つしかつくっていない企業は、他のものをつくりたいとなった時に、別の企業に依頼する必要がありますが、応用電機は基本的に一社で完結できるんです。
─現在の新山さんのお仕事について教えてください。
神奈川の事業部長として事業部を統括しながら、営業と技術のマネージャーも兼務しています。主に関東圏の企業様からの設備受注と、工場全体を切り盛りすることが今の仕事です。

応用電機の社員になった最初の数年は技術の仕事だけをしていたのですが、もともと技術がベースにあるということと、「よく喋る技術者」というのはどうやら希少価値があるそうで(笑) 今は営業と技術、両方の仕事に取り組んでいます。
─やりがいを感じるのは、どんなときでしょうか。
お客様からのご依頼は、「こういうものをつくりたい」という明確なイメージがあるケースと、お客様がもつ漠然としたイメージをもとに、最初の段階から一緒につくっていくケースがあります。特に後者の場合、提案の中に自分のアイデアを盛り込んで形にしていくのが非常に楽しいなと感じています。
大手の会社ではやり方が決まっていることも多いのですが、応用電機では、お客様に満足いただき、かつ利益が出るのであれば、基本的にやり方に縛りはありません。自分のアイデアを形にできる点で、非常にやりがいがありますね。
─貴社では高専出身の方も活躍されていると伺っています。
高専出身の社員も、ここ数年は増えつつあります。基本的に希望に応じた配属を行っており、「入社してからどこに行くかわからない」という採用はしていないので、入社時に選んだ仕事に取り組むことができます。転勤も原則ありませんし、評価も学歴ではなく実力主義なので、働きやすい環境だと思いますね。高専出身の後輩には、失敗してもいいから、思う存分やりたい仕事にチャレンジしてほしいと思っています。

未来の半導体業界を支える高専生へ
─母校である熊本高専で、特命客員教授としてもご活躍されているのですね。
私の子どもが熊本高専に通っていたことをきっかけに、学校からの依頼でお手伝いさせていただいた形です。半導体の製造工程などを説明する学生向けの講演会や、保護者向けの半導体業界講座を行いました。半導体業界で働く後輩に声をかけ、私が進行役をして、後輩に話を振りながら、半導体業界で働く人の生の声を届けています。

学校での講演をきっかけとして、東京で開催された「くまもと移住ラボ」(主催:熊本市)でも、トークセッションの司会としてお声がけいただきました。ここでは、熊本への移住を考える一般の方向けに、半導体業界について説明を行いました。
─最後に、高専生へのメッセージをお願いします。
やはり授業の内容を嫌がらずにしっかり学んでおくと良いと思います。社会人になってから、「高専でこんなことを学んだな」と思い出せるだけでも役に立つことは多いです。特に、技術者の中でそれなりのレベルになりたいなら、物理と数学はしっかり学んでおいた方が良いと思います。

起業を考えている方には、「成功した人の話よりも、失敗した人の話を聞いた方が良い」と言っています。成功談は起業の良い面しか語られないことが多いですし、成功した人は、起業した人の中の一部にすぎません。失敗した人の話をたくさん聞いて、そこからいかに学ぶかを大事にしてほしいですね。また、ものづくりが伴う起業は材料を買う必要があるので、特に経営学をしっかり学んでおかないと、コストが合わないといったことになりかねません。その辺りを、早めに見極めて学んだほうが良いと思います。
私が今の仕事にも対応できる基礎を身につけられたことは、高専で十代の頃から技術教育をしてもらった賜物だと思っています。高専生は幅広い技術の知識と論理的思考を学んでいるので、常識にとらわれず、様々な分野で活躍していってください!
新山 尚寿氏
Naohisa Shinyama
- 応用電機株式会社 神奈川事業部 事業部長、営業マネージャー/技術マネージャー 兼務

1993年3月 熊本電波工業高等専門学校(現:熊本高等専門学校 熊本キャンパス) 電子制御工学科 卒業
1993年4月 テラダイン株式会社
2005年9月 株式会社iST 取締役
2007年5月 応用電機株式会社
2010年1月 同 九州事業部 営業技術マネージャー
2023年10月より現職
熊本高等専門学校の記事
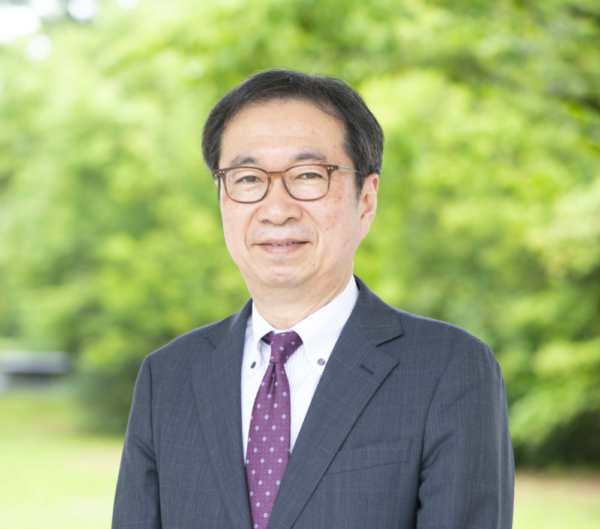


アクセス数ランキング


- 自ら教え続け、研究し続ける“現役”の校長——立場が変わっても貫く「人づくり」の教育
- 函館工業高等専門学校 校長
清水 一道 氏

- 「学びたい」を原動力に、金融×ITの最前線へ。成長意欲が連鎖するNTTデータフォースでの、高専卒社員2人の姿
- NTTデータフォース株式会社 北海道・東北ビジネス本部 チーフ
小田中 拓馬 氏
NTTデータフォース株式会社 システム開発事業本部 本部長
有田 久幸 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡
- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師
盛田 有貴 氏
-150x150.jpg)
- 「自分にしかできないこと」を追い求めたから、今がある。デザインで街を元気にする取り組みとは
- 石川工業高等専門学校 建築学科 教授・副校長(地域・国際連携)
道地 慶子 氏

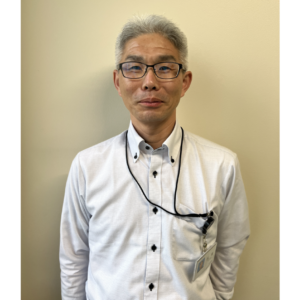
- 世の中で一番強い形は○○!? 12年間に及ぶ国内最難関のトンネル工事に挑む
- 清水建設株式会社 北海道支店 土木部 部長
松尾 勝司 氏

- 「研究が楽しい」「みんなで一緒にスタートが切れる」——高専生が進学先に奈良先端科学技術大学院大学を選んだ理由をご紹介
- 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 博士後期課程2年
浦上 大世 氏
奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成領域 博士後期課程1年
星川 輝 氏
奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 博士前期課程2年
山川 怜太 氏


- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力
- 日本郵船株式会社 一等航海士
川西 雄太 氏

-300x300.jpg)







