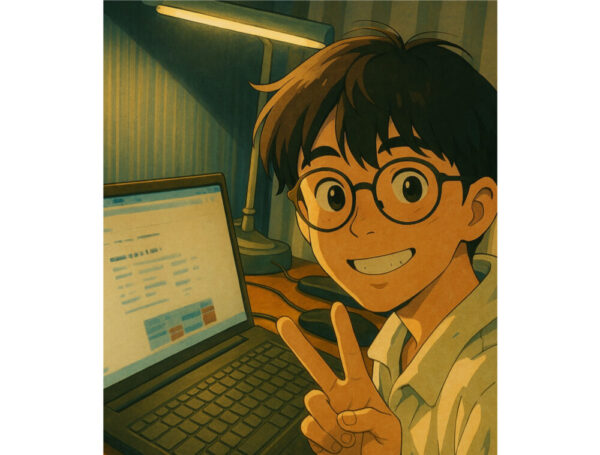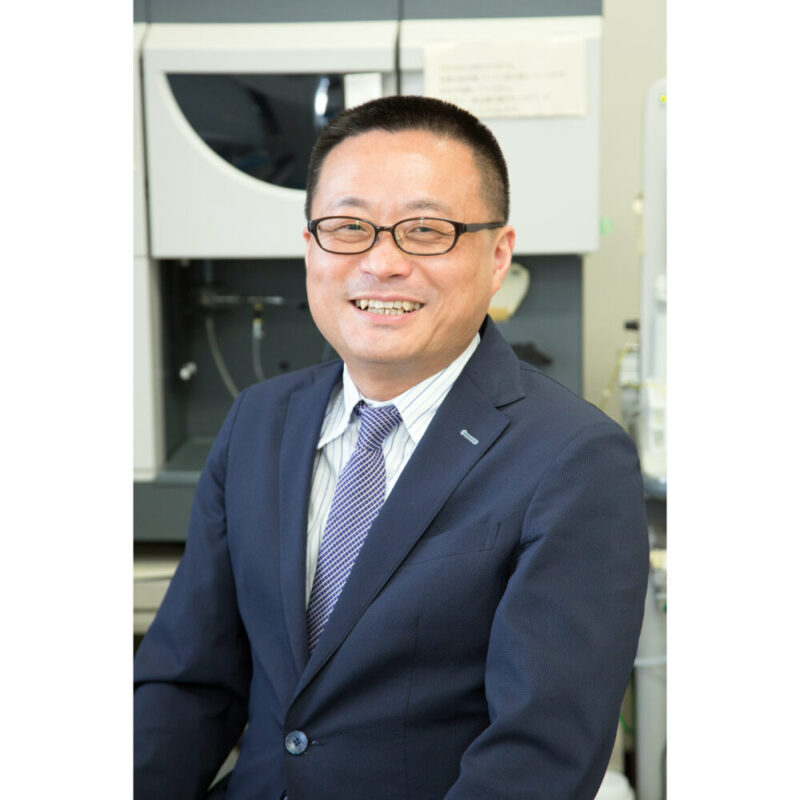
材料工学や環境技術の分野で複数の特許技術を開発されている富山高専の袋布昌幹先生。全国各地の企業と連携し、さまざまな社会課題の解決にご尽力されています。産学連携にここまで力を入れるのはなぜか。現在の取り組みと併せてお話を伺いました。
スランプからの大逆転! 数千万円の研究費を獲得
―先生が行われている研究について教えてください。

基礎として扱っているのは「リン酸カルシウムの高機能化」と「石膏のリサイクル」という2つのテーマです。
10個以上の共同研究を行っているため、幅広い研究を行っていると思われがちなのですが、あくまで、用途開発です。もっと言うと、石膏とリン酸カルシウムは、結晶の原子の並びが一緒なんですよね。ですから、似たような2つの化合物を扱っているだけなんです。
―その研究を始めたきっかけはなんだったのでしょうか。
私は大学院の頃、「人工骨」の研究をしていたもののうまくいかず、スランプに陥っていました。まして、高専では本格的な医学的研究はなかなかできません。そのため、高専に着任した当初は本当に最下層からのスタートで、助手から准教授になるのも、すごく遅かったんですよね。
そんな時、富山高専におられた丁子哲治先生から「富山高専が創立30周年記念事業として、“エコテクノロジー”をテーマに国際学会を開くから、手伝わないか?」と言われたんです。

当時は何も分からないまま参加することになったのですが、これが全ての始まりでした。
私たちは、「地下水汚染への対策」というテーマを立ち上げ、科研費を獲得しようと考えました。そして、北京にある古いホテルで丁子先生と一緒にお茶を飲んでいた時。丁子先生から、「地下水に含まれているフッ素の処理を、材料でなんとかできないかな?」と何気なく聞かれたんです。

そこで、大学時代の研究で得た知識から「ある材料を使えばできるかもしれない」という考えが浮かびました。その材料というのが「第二リン酸カルシウム」です。学生さんの献身的な実験により、これがフッ素と反応することを明らかにしました。それから筑波の研究所で研究員として調査研究を行うなかで、この技術の意義を確信したのです。

それ以降は運も味方し、科研費に加え、NEDOと環境省に関する事業も行い、1人で数千万円の研究費を獲得することができました。
廃棄物で赤土対策! 沖縄に新たな産業を
―現在は、沖縄で赤土問題に取り組まれているとお聞きしました。
きっかけは、壁材などに使われている石膏のリサイクルに関する共同研究です。この研究は、富山高専出身の商社の方を間に挟んでいたのですが、その方がある日、「クラピア」という植物の苗を持ってきて、「何か良いアイデアはないですか?」と言ってきたんです。
そこで、石膏を土に混ぜると植物が良く育つ性質を生かし、「廃石膏を土に混ぜることでリサイクルにつながるのではないか」と思いつきました。

実際にやってみたところ、初めは大失敗しました(笑) 雑草も元気になってしまって、苗の発育が阻害されてしまったんですよね。「これではいけない!」と思い、雑草をいかに生やさないかということをひたすら考えました。
ビニールシートを張って、穴を空けて苗を植えるという手法が一般的ですが、環境のことを考えると、どうしてもプラスチックは使いたくなかったんです。そのため、「どうにか土に細工をできないか」と考えまして。石膏に「石灰」を適切に混ぜることで、雑草は育たずに、苗だけが育つという技術を開発しました。
―それが沖縄の赤土問題に、どのようにつながっていくのでしょうか。
クラピアは10℃を下回ると育たなくなってしまうため、富山の冬では実験ができないんですよね。そのため、「それならば、1年中温暖な場所で実験をしよう!」と考えたんです。
石膏ボードの共同研究先としては、全国各地につながりを持っていたため、沖縄の企業に話を持ち掛け、実証研究がスタートしました。ここで沖縄につながってきますね。
しばらくすると、クラピアが土に根を深く張って育つことにより、土が固くなることが分かったんです。そこで、沖縄で問題となっている「赤土」の対策になるのではないかと考えました。
そして調べているうちに、琉球大学の研究によって、「クラピアによって赤土は99.9%防げるというデータが得られている」ことを知りました。ただ、それが実装できてないのは、ただ植えるだけでは、雑草に負けてクラピアが定着しないという問題があったからなんです。

ここで、私の持つ技術を活用すれば、この問題が解決できるのではないかと考え、現在の研究に至ります。これがうまくいけば、沖縄の廃棄物を使って現地の問題を解決できるうえ、沖縄に雇用を生み出し「産業化」にもつなげることができます。そのため、ビジネスモデルとしても高い評価を受けている取り組みなんです。
キラーコンテンツを見つけよう
―先生は、産学連携にかなり力を入れているんですね。
契約締結していないけれども連携している民間企業も含めれば全国に100社くらいあると思います。これによって、資金的な裏付けはもちろんのこと、「リアルな課題を高専の現場に落とし込む」という高専創設時からの理念を、学生さんと共有できる環境を整備してきました。

ひとことで共同研究と言っても、企業のデータを学生さんに解析させるだけでは、単なる労働になってしまいますし、企業と同等のレベルで行うことも難しいですよね。ですので、学生さんの研究テーマは企業のテーマと切り離しています。一方、企業の実験を補助いただく際には謝金をお支払いして対応してもらっています。
ただ、その内容は学生さんの研究と実験方法が同じだったり、使う装置が一緒だったり。研究を通して、得られたものは自分の研究に生かせるようなテーマを振り分けています。

―先生が研究や教育を行ううえで、大切にしていることはなんですか?
研究の際に大切にしているのが「プラットフォーム」と「キラーコンテンツ」という2つのキーワードです。
決定的な自信を持てるような「キラーコンテンツ」がないと、技術の差別化ができないんですよね。私の場合、石膏の汚染土壌対策や品質管理技術がこれに当てはまります。
だから、学生さんにもキラーコンテンツを見つけてあげたいですね。初めはうまくいかなかったとしても、諦めずに続けることで、歯車が回り始める瞬間がきっとあるんです。私は感覚としてもすごく分かりましたし、その経験は、今にも生かされていると感じています。
また、必ずしも、万能選手である必要はないと思うんです。どうしても、大学受験などでは全ての科目が同様のレベルで出来ることが求められますよね。
高専の場合は、専門分野を尖らせて、できない部分は他人と補い合えばいいと思うんです。学生・教員問わず、全国の高専が助け合って、埋め合わせて、大きな円をみんなでつくっていけば、それが高専の新たな強みになるんじゃないかなと思います。
今後も高専らしい産学連携に取り組み、学生さんにも還元できるような環境づくりをしていきたいです。
袋布 昌幹氏
Masamoto Tafu
- 富山高等専門学校 物質化学工学科 教授・校長補佐(研究高度化担当)
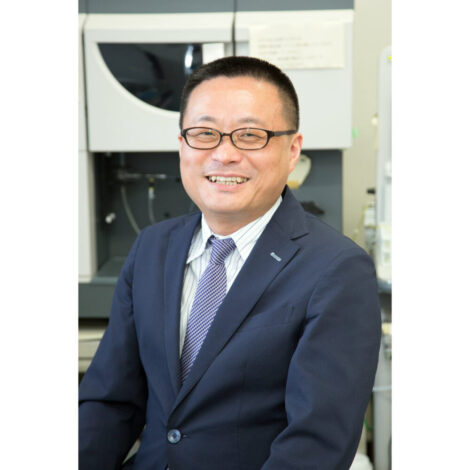
1991年 立命館大学 理工学部 化学科 卒業
1993年 京都大学大学院 理学研究科 化学専攻 修士課程 修了
1994年 富山工業高等専門学校 金属工学科 助手
1995年 富山工業高等専門学校 境材料工学科 助手
1998年 通商産業省工業技術院 物質工学工業技術研究所 流動研究員、1999年 同 客員研究員
2005年 富山工業高等専門学校 環境材料工学科 助教授、2007年 同 准教授
2005年 長岡技術科学大学(論文博士) 博士(工学)
2014年 富山高等専門学校 物質化学工学科 教授
富山高等専門学校の記事
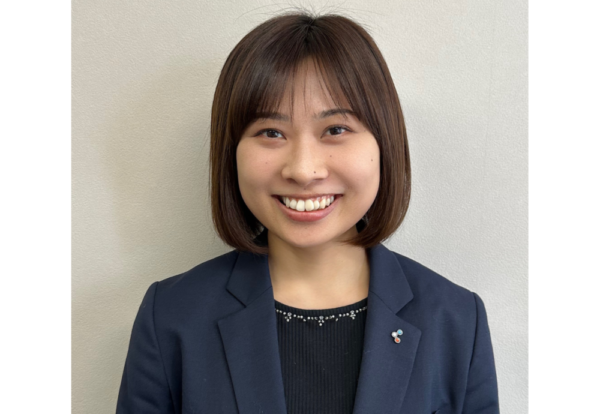


アクセス数ランキング


- 「電気を光で置き換える」可能性の追求。電子情報と応用物理の間で見つけた自分の道
- 東京科学大学 未来産業技術研究所 助教
相川 洋平 氏

- 高専初の「春高バレー」出場!松江高専を全国の舞台に導いた、教員の熱い思いとは
- 松江工業高等専門学校 数理科学科 教授
村上 享 氏

- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力
- 日本郵船株式会社 一等航海士
川西 雄太 氏

- 教員の傍ら、博士号を取るために大学院へ。目指すは高専の価値を高める教育
- 呉工業高等専門学校 建築学科 助教
河﨑 啓太 氏


- 合唱部創設、体育祭でのeスポーツ導入。NHKでも生き続ける「ないものはつくる」高専の精神
- NHK松山放送局 コンテンツセンター
下平 啓太 氏
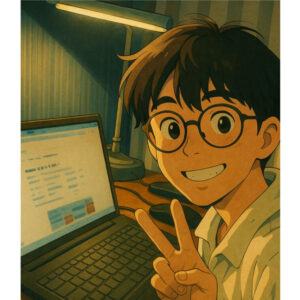
- 静岡でAIに熱狂する高専生! 経営者への取材活動を通して感じた、起業するときの「大人」の存在
- 沼津工業高等専門学校 制御情報工学科 3年
田村 愛琉 氏

- 研究職からプロアドベンチャーレーサーに転身! 「自分の選んだ道こそが正解」と胸を張って言える人生に
- プロアドベンチャーレーサー
イーストウインド・プロダクション 代表
田中 正人 氏

- 夢は持たなくてもいい! 基礎能力があればどこにでも行ける。だからこそ、日々の学びを大切に
- 富山高等専門学校 商船学科 航海コース 講師
村田 光明 氏





-300x300.jpg)