
久留米高専の電気工学科を卒業後、研究開発の現場でキャリアを重ねてきた小田正昭さん。企業での光学デバイス開発や、鳥取大学との共同研究を経て博士号を取得し、さらに大学発ベンチャーでマネジメントを担うなど、研究と事業の両面に携わってきました。そんな小田さんに、高専時代の思い出から技術者としてのやりがい、これからの展望についてお話を伺いました。
自由さと厳しさを実感した高専生活
―久留米高専に進学されたきっかけを教えてください。
子どもの頃から電気工学に関心がありました。父は戦後の時代にラジオをつくって販売していたらしく、テレビまでつくったこともあるそうで、私が物心ついた頃にはやめていまたが、壊れた家電を修理する姿はよく目にしました。そんな環境のなかで、自然と電気に親しみを持つようになったのだと思います。
もう一つは「高専は難しい」という評判を耳にしたことです。いとこや近所の人が高専に進学していて、「あそこは難関だ」と言われていました。もともとは地元の公立高校を第一志望にしていたのですが、挑戦心もあり、とりあえず受けてみようと思ったのです。担任の先生からは「落ちるとショックだから、受けるのはやめた方がいい」と、試験前日まで親に電話をかけてくるほど反対されましたが、両親は「本人が受けたいなら受けさせればいい」と背中を押してくれました。
また、当時の私立高校では「男子は丸刈り必須」「バイク免許取得禁止」といった規則が当たり前でしたが、高専にはそうした校則がなく、「好きな髪型にできる」「バイクの免許も取れる」というその自由な校風も後押しになり、高専に進学することを選びました。
―久留米高専では、どのような学生生活を送られましたか。
普通高校に比べると服装や生活の面でずっとおおらかで、のびのびと過ごせる雰囲気がありました。その一方で、カンニングや法律違反といったことには非常に厳しく、場合によっては退学処分になることもあると聞いたときは震えました(笑)
勉強は想像以上に大変でした。特に数学は独特で、ある分野を数Ⅰから数Ⅲまで一気に進むカリキュラム。数日のうちに難易度が急に上がり、ついていけなくなることもしばしばでした。試験も時間が足りず、苦労した記憶があります。
入学式で校長先生が「高専生は生徒ではなく学生だ」とお話しされたときは、その意味がよくわかりませんでした。しかし後になって、それは大学生と同じように「自由と責任が表裏一体で与えられている」ということだと理解しました。

―印象に残っている学生生活のエピソードはありますか。
昭和当時の体育祭の応援練習はとにかく過酷で、体調を崩して入院する学生が出るほどでした。私自身も「もう学校を辞めたい」と思うくらいきつかったです。筑後川の土手で行っていたのですが、あるとき近隣住民から「さすがに危険ではないか」と通報が入り、その後は先生の監視のもと校内で行われるようになりましたが、それほど厳しい行事でした。
ただし、厳しかったのは応援練習だけで、普段は先輩後輩の仲が良く、とても自由で楽しい学生生活を送ることができました。とくに部活動は大きな楽しみで、中学から続けていたバスケットボールを高専でも続けました。
―社会人なってからもバスケットボールを続けられたと聞きました。
高専では高校の大会への出場機会がなく、高専大会でも全国大会に行けなかったことを残念に思い、就職後も社会人でバスケットを続けました。広島に就職してからは自ら仲間を集めて会社のチームを立ち上げて、35歳頃までプレーを続けましたね。最初は初心者ばかりの弱小チームで、市内大会でも勝てない時期が続きましたが、週2回の練習を重ねるうちに力をつけ、3年目には勝ち星を挙げられるようになりました。
最盛期には広島市の二部リーグに所属し、広島県のトーナメントでベスト3に入るほどに成長。実業団リーグでは最初こそ大差で敗れるものの、戦略を磨き続けた結果、中国大会まで勝ち進み、全日本実業団バスケットボール競技大会出場まで、あと1勝というところまで迫る経験もしました。

鳥取大学との共同研究が博士課程への道に
―卒業後のキャリアについて教えてください。
最初の就職先は化学メーカーでした。高専には求人が多く届いていたものの、部活動に熱中してほとんど動かずにいたところ、担任の先生から「電気系に進むと周囲のレベルが高く大変だが、化学の会社なら電気の知識を持つ人が少なく、むしろ重宝されるだろう」と勧められたんです。当時は部活動の最後の大会前でもあり、深く考えずに応募を決めました。
また、地元に残りたい気持ちもありつつ、市役所に入りワークライフバランスを重視する道と、企業で仕事に打ち込む道のどちらかを考えた結果、後者を選び、「しっかり働こう」との思いで入社を決意しました。

そこでは研究所に配属され、光学デバイスの研究開発に携わりました。3人の小さなチームでスタートしましたが、開発は成功し、実際に工場の建設や運営にまで関わることができました。研究開発から生産まで経験できたのは非常に大きな学びでした。
その後、台湾系の商社に転職し、営業として活動しながら再び光学デバイスの研究にも関わることに。鳥取大学の教授と共同研究を行い、新しい光学デバイスの開発に取り組みました。経済産業省の補助金やJSTの委託開発を活用してプロジェクトを進め、社会人博士として鳥取大学に進学するきっかけにもなりました。
.png)
―博士課程に進まれた経緯について詳しく教えてください。
40歳頃、鳥取大学の教授から「博士課程に挑戦してみないか」と勧められたんです。社会人として働きながらの博士課程でしたが、これまでの研究経験を基に論文を書くことができると考え、進学を決めました。
化学は苦手でしたが、研究の中で必要になり自然と理解できるようになりました。避けていた分野に導かれたような感覚もありましたね。博士号を取得したことは、キャリアの幅を大きく広げる転機になりました。
―研究開発で特にやりがいを感じた瞬間はありますか。
自分の立てた仮説が実験でうまくいったときです。「予測が当たった」という達成感は格別で、失敗も含めて学びの連続でした。特に、論文や特許を調べ、試行錯誤しながら結果が出たときの喜びは大きかったです。
さらに、研究成果が実際に工場で量産されるプロセスに関われたことも大きなやりがいでした。効率化や品質改善を考えながら百人規模の工場を動かしていく。研究だけでなく現場を巻き込み成果を出せたのは貴重な経験でした。
―現在のお仕事について教えてください。
九州大学発のベンチャー企業「KOALA Tech」でジェネラルマネージャーを務めています。社員は15人ほどで、アルジェリア人の社長をはじめフランス人、インド人、イラン人など多国籍の研究者が集まる国際的な環境です。私は人事や総務に加えて、開発マネジメントにも関わってきました。
研究者は非常に優秀ですが、論文を書くことと製品を社会に届けることは別の課題です。例えば、研究者にとっては「興味のあるテーマを論文にまとめる」ことがゴールになりがちですが、企業としては「スケジュール通りに成果を形にし、次の段階につなげる」ことが求められます。その両者の視点の違いをすり合わせるのは簡単ではありません。私はこれまでの経験を生かして、研究から事業化への流れを支える「橋渡し役」として取り組んできました。

―今後についてどのように考えていますか。
実は、今年でKOALA Techを退職予定です。直近では、大規模な設備導入の立ち上げや研究者の採用を担当しましたが、事業が拡大していく過程で役割の整理が必要になり、一区切りを迎えることになりました。とはいえ、長年の事業マネジメントの蓄積を買っていただき、退職後もしばらくは外部から伴走する予定です。今後もこれまでの経験を生かしながら働き続けたいと考えています。
一方で、プライベートでは健康を維持しながら趣味のゴルフも楽しんでいます。学生時代から続けてきたバスケットボールはさすがに体力的に難しくなりましたが、新しい挑戦として競技ゴルフに取り組み、70代、80代になっても元気にプレーできる先輩方の姿に刺激を受けています。仕事も趣味もバランスよく続けながら、自分の活躍できる場所を見つけていければと考えています。
.png)
―最後に、高専生へのメッセージをお願いします。
仕事には興味を持って取り組んでください。大変なことや辛いことはありますが、興味を持つことでいろいろなことを吸収することができ、自分の力となります。また、進学できる機会があれば、学士や修士を取得するために、できるだけ進学することをおすすめします。
小田 正昭氏
Masaaki Oda
- 株式会社オプトプラス 代表取締役

1985年3月 久留米工業高等専門学校 電気工学科 卒業
1985年4月 三菱レイヨン株式会社 中央研究所配属
2000年9月 日本ライトン株式会社へ転職
2008年3月 鳥取大学大学院 工学研究科 物質生産工学専攻 博士後期課程 修了
2010年4月 株式会社オプトプラス設立、代表取締役就任
2012年1月 精密機器メーカーへ転職
2021年4月 Amethystum Japan 管理経営担当
2024年2月 株式会社KOALA Tech ジェネラルマネージャー
2025年11月 株式会社オプトプラス(現職)
久留米工業高等専門学校の記事



アクセス数ランキング


- 自ら教え続け、研究し続ける“現役”の校長——立場が変わっても貫く「人づくり」の教育
- 函館工業高等専門学校 校長
清水 一道 氏

- 「学びたい」を原動力に、金融×ITの最前線へ。成長意欲が連鎖するNTTデータフォースでの、高専卒社員2人の姿
- NTTデータフォース株式会社 北海道・東北ビジネス本部 チーフ
小田中 拓馬 氏
NTTデータフォース株式会社 システム開発事業本部 本部長
有田 久幸 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡
- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師
盛田 有貴 氏
-150x150.jpg)
- 「自分にしかできないこと」を追い求めたから、今がある。デザインで街を元気にする取り組みとは
- 石川工業高等専門学校 建築学科 教授・副校長(地域・国際連携)
道地 慶子 氏

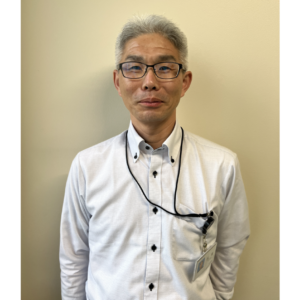
- 世の中で一番強い形は○○!? 12年間に及ぶ国内最難関のトンネル工事に挑む
- 清水建設株式会社 北海道支店 土木部 部長
松尾 勝司 氏

- 「研究が楽しい」「みんなで一緒にスタートが切れる」——高専生が進学先に奈良先端科学技術大学院大学を選んだ理由をご紹介
- 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 博士後期課程2年
浦上 大世 氏
奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成領域 博士後期課程1年
星川 輝 氏
奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 博士前期課程2年
山川 怜太 氏


- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力
- 日本郵船株式会社 一等航海士
川西 雄太 氏

-300x300.jpg)








