
明石高専を卒業後、北海道大学に進学された西山翔太さん。ロボットへの憧れから高専に進学したものの、在学中は一度ロボットを嫌いになったこともあったそうです。悩み抜いた高専時代があったからこそマインドが少しずつ変わっていったと語る西山さんに、高専時代の思い出や、現在の研究について伺いました。
ロボットへの憧れに対する疑い
―西山さんが明石高専に進学されたきっかけを教えてください。
もともと「何かをつくる」ということ自体に興味があり、機械に限らず料理にも裁縫にも関心がありました。ただ、ロボットに関しては半ば一辺倒なところがあり、ロボットという言葉がつくものであれば、とりあえず見に行くような愚直な熱意を持っていましたね。
小学校2年生の時、祖父に明石高専の高専祭へ連れられ、ロボット工学研究部のブースでロボットの操縦体験をさせていただいたことが、ロボット製作への憧れのきっかけになりました。
その時は高専ということも知らず、「学校」というざっくりとした括りでしか見ていなかったのですが、「この学校に行くのがベストなんだ」という先入観を持ち続け、いざ入学して校内に入った時、それが確信に変わったのを覚えています。
-実際に高専に進学されて、いかがでしたか。
3年生か4年生のとき、流体力学の授業で、ある先生が「流れるものは世の中にたくさんあります。『濃度の拡散』や『熱の拡散』という括りで捉えるのはもったいない。いろいろな現象には類似性(アナロジー)がある」いうことを教えてくださったんです。それが今の自分の興味に繋がっています。
実は高専に入学してから、「本当に自分はロボットが好きなのだろうか」という疑問を抱くようになりました。本当は何か別のものが好きなのではないかと思っていたのですが、当時はうまく言葉にできなかったんです。そんなとき「アナロジー」という言葉を知り、「もしかしたら、自分はロボットだけではなく、機械全般が好きなのかもしれない」と思うようになりました。
-高専時代はロボット工学研究部に所属していたそうですね。
他の部活動をほとんど見ずに、まっすぐロボット工学研究部に入りました。ただ、ロボコン等に向けて活動していくのが、そこまで楽しいと思えなかったんです。そこから「自分は本当にロボットが好きなのか?」と考え始めました。
手を動かして何かをつくること自体は楽しかったのですが、いざロボコンに参加してみると、求心力のようなものを感じられず、チームメイトとの温度感の違いを感じる日々でした。考えれば考えるほど自分の歩んできた道を否定しているような気分になり、しかし暗い気持ちになると分かっていても考えることをやめられないという状態でした。
しかし、悩んだ末に気づいたのは、ロボットにかぎらず「何かをつくること自体が好き」ということでした。この発見のおかげで、たとえロボットに強く惹かれなくても、自分の進む道は間違っていないんだと思えるようになり、気が楽になりました。
実は、4年生のときにチームがロボコンの全国大会に出場できるという状況になったとき、私は部費を両親から出してもらっていたこともあり、「旅費がもったいない」という理由で、あまり行きたいと思えなかったんです。そのことを両親に言うと、父から「今しかできないんだから」と言われ、すごく救われました。端的に言うと、「やらない後悔より、やる後悔を選ぼう」と思えたんです。そこから、機会があれば積極的に挑戦するようになりました。
また、卒業してしばらく経った後、当時を振り返って考えを整理するためにブログを書いたことがあります。自分の中で「先輩・後輩の関係を大事にできてなかった」という内省があり、想いを綴ることにしました。チームメイトが先輩・後輩と楽しそうにコミュニケーションを取っているのを側から見て、「自分もこうなりたい」という憧れを捨てきれなかったのかもしれません。
誰に向けた記事でもなく、ただ自分に対して書いたブログでしたが、長年悩んでいたことを分析して言語化することで、自分なりの区切りをつける意味があったと思います。
研究を通して垣間見た「職人の世界」
-卒業研究はどのようなことをされたのですか。
授業や部活を通して、「何かに興味があるからそれを追求する」という姿勢ではなく、「自分が体験していないこと、理解が追いついていないことを補填していく」というスタンスに変わりました。高専で熱流体関係の研究室を選んだのは、これが理由です。
卒業研究は、企業との共同研究でした。ゴムなどの袋状の製品をつくるとき、熱を加えて処理をするという工程が含まれます。その製造過程で蒸気などの熱いものを吹きかけて温めることは非常にコントロールしづらいといった問題があり、中でどうような現象が起こっているのか、それをコントロールするにはどのような方法をとるべきかという研究をしていました。
私は主に実験でデータを集めることをしました。実験を通して流体関係の部品を扱うときのテクニックも教えていただき、貴重な経験になりました。
研究の中間報告会の際、短いプレゼン資料をつくって、先生方の前で説明をするセッションがありました。準備段階では指導教員の先生からの評価が散々だったので、かなり心配になったのですが、発表当日のプレゼンはそれなりに上手にできました。発表前、先生から「頑張れ」と言っていただき、「これが愛の鞭か」と感じたのが印象に残っています(笑)
先生は1人1人に対して熱心にご指導してくださいました。週2回のミーティングでゼミ生全員が議論をするのですが、その時に私の意見が採用されたり、私の発言がきっかけになって新しく調べることができたり、実験の方針が決まったりすることも多く、研究のやりがいを感じました。
研究をしているうちに、自分が「職人化」されていくのを感じました。例えば材料ひとつとっても、それについての知識があれば、その物体は冷たいか・温かいかが触らなくても分かりますし、実際に触ると思っていた通りだったということが起こります。自分の知識と体験がマッチすると面白いですし、これが職人の世界か、と感慨深かったですね。
人が全てを知ったら、何がつくれるようになるのか?
―現在は北海道大学にいらっしゃるんですね。
進学自体は高専入学当初から決めており、勉強を続けるモチベーションは最初からありました。進路として北海道大学を選んだのは、大学の仕組みとしていろいろな勉強ができるためです。地元が温暖な地域だったこともあり、寒冷な気候にも惹かれましたね。

大学に入ってから、「失敗上等」というマインドは強くなりました。例えば、有志が集まってプロジェクトを立ち上げる活動に参加したことがあったんです。私たちは「海洋ゴミを回収するロボットをつくる」というプロジェクトを立ち上げました。
何かをつくるのはずっと好きでしたし、自分がつくりたいものをつくってお金がいただけるのはありがたいことだと思っていました。一方で、お金をいただくプロジェクトでは「どう役に立つか」が説明できないといけなかったので、そのためのリサーチが一番難しく、同時に一番面白いところだとも思いました。
私はロボット本体の製作を任され、船のような要領で海を進むロボットを目指しました。いざロボットができても、いきなり海に入れることはできなかったので、北大にある噴水の水をわざわざ止めてもらって実験させてもらえました。何かをやる学生への協力の手厚さを感じましたね。
―現在はどのような研究をされていらっしゃるんですか。
今の研究室は学生主体で、自由のやりたいことをやらせてもらえる場所です。学部4年生の時、教授と話している中で偶然出来上がったテーマ「関節にある軟骨の機能」について調べたことがありました。軟骨は膝などにあり、飛び跳ねて地面に着地したときに、クッションの役割を果たしています。そのことについてもう少し深く知りたいと思い、先行研究を調べたら、水の通りやすさが関係していることを知り、実験的に調べられる方法を研究しました。
ただ、これは卒業研究発表会の時点で失敗したのがオチです。「小さくて薄い軟骨のシートを切り出して、それに対して水を通す」という実験をするのですが、その中で水漏れが起こってしまって、参考になるようなデータが得られませんでした。
2024年はそれまで研究を続ける予定ではあったのですが、かなり実験をする必要があることや、水漏れの解決方法が見つかっていないことなど、いろいろな障壁があったので、一旦保留としています。現在は「休耕地の管理をAIに任せた結果、社会はどう移り変わるか」という社会実験を試みているところです。
―西山さんの研究のモチベーションは何ですか。
「物事を知れば知るほど、組み合わせてできるものが増えていくこと」です。組み合わせ爆発という現象がありますが、個人的にはそれがこの世の複雑さ(面白さ)の原理だなと感じています。知ること自体が面白いと思っているので、そういう意味では純粋な好奇心といえるのかもしれません。究極、「人が全てを知ったら、何がつくれるようになるのか」というテーマに興味を持っています。
また、勉強の姿勢としては「一は全、全は一」という考えを持っています。関係ないと思っていたピースがハマることはあると思っているので、自分の興味関心とは全然違う分野の勉強でも大歓迎、常に来るもの拒まずの姿勢でいます。
人生の中では、「物事に対して不寛容にならないこと」を大事にしています。いろいろなものに寛容でいられるということは、心に余裕がある状態だと思います。高専時代も人の手伝いをすることが好きだったのですが、人を手伝うためには自分に余力が必要です。「余裕こそ人の強さ」だと思ったことがあって、そこから派生したのが「寛容になること」でした。それがある意味、人の器の大きさだと思っています。
―現役の高専生にメッセージをお願いします。
「広く知る」ことは何事においても役に立つと思うので、よほど進路について確信があるわけではない限り、多少苦労しても進学することは悪くないと思います。また、その際に思い切って学部・専攻を変えたりすることも一興だと思いますし、自分としてはむしろそういったことができる人を応援したいと考えています(もちろん、一概には言えませんが)。
何か好きな分野に一途であることは、それ自体素晴らしく、尊いことではあると思いますが、最終的には全く違ったように見えた分野も「周辺分野」として扱うようになると思うので、一辺倒にならないマインドは持っていて損はないと思います。何事に対しても無関係な知識は存在しませんので、いろいろなことに興味をもってチャレンジしてください。
西山 翔太氏
Shota Nishiyama
- 北海道大学 大学院工学院 修士1年

2022年3月 明石工業高等専門学校 機械工学科 卒業
2024年3月 北海道大学 工学部 機械知能工学科 卒業
2024年4月 北海道大学 大学院工学院 修士課程 入学
明石工業高等専門学校の記事
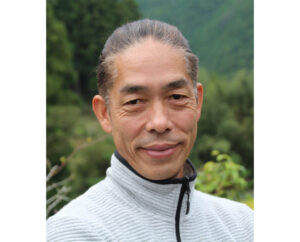


アクセス数ランキング

- 合唱部創設、体育祭でのeスポーツ導入。NHKでも生き続ける「ないものはつくる」高専の精神
- NHK松山放送局 コンテンツセンター
下平 啓太 氏

- 「電気を光で置き換える」可能性の追求。電子情報と応用物理の間で見つけた自分の道
- 東京科学大学 未来産業技術研究所 助教
相川 洋平 氏


- ノンストップで挑戦を続けた先に成長がある。米海軍基地で働きながら、世界遺産を通した平和を発信
- 米海軍横須賀基地 艦船修理廠 品質保証室 物理分析課
御堂岡 隼 氏

- 韓国への憧れをきっかけに、富山高専に進学! 「語学×専門分野」を武器に、未来を切り拓く
- 神戸大学 経営学部 3年
巾 優希 氏

- 得意の語学を究めるために高専へ! 趣味の筋トレから学ぶ、他者と比較せず、継続することの大切さ
- 埼玉大学 経済学部 3年
青木 大介 氏



- 企業と高専が手を取り合う未来へ。小山高専で実施する企業連携と、今後必要な高専教育のあり方
- 小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、キャリア支援室 室長
鈴木 真ノ介 氏
小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、校長補佐(国際主事)
平田 克己 氏

- 起業は引っ越しと一緒!? 起業という道を知ることで、起業じゃない道でも活躍できる能力が身につく!
- セブンセンスマーケティング株式会社 代表取締役
宮田 昌輝 氏

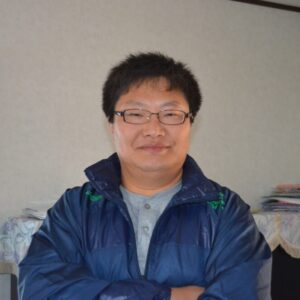




-300x300.jpg)




