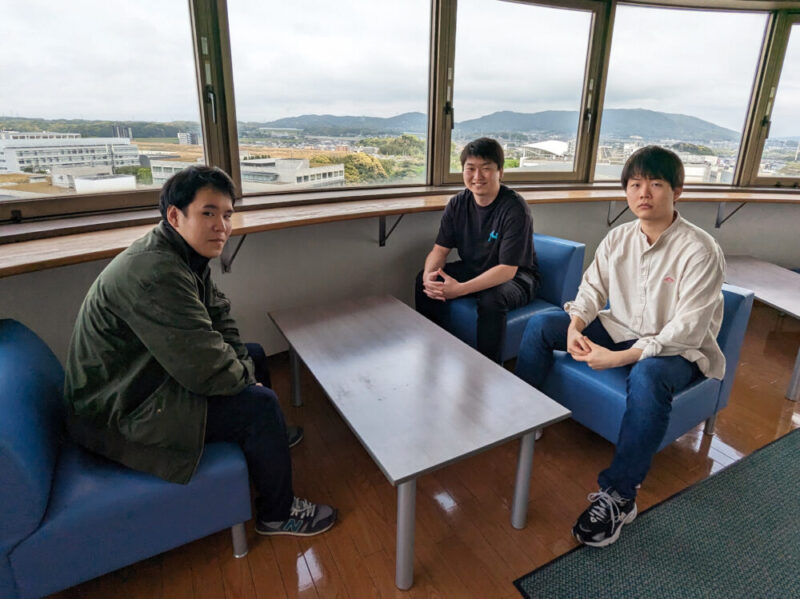
今回は、高専を卒業し、九州工業大学大学院 生命体工学研究科に進学された学生3名にお話を伺いました。九州工業大学(以下、九工大)の院を選んだきっかけは何だったのでしょうか。前編・後編の2本立てとし、今回は高専時代に焦点を当て、3名の過去に迫ります。
※この記事は、九州工業大学 井上創造先生によるインタビュー企画三部作の第二部です。
第一部 九工大で研究者として働いている高専卒生
第二部 九工大で学生として学んでいる高専卒生―九工大大学院 生命体工学研究科の高専卒学生に聞く―(前編)(この記事)
第三部 九工大で学生として学んでいる高専卒生―九工大大学院 生命体工学研究科の高専卒学生に聞く―(後編)
なんとなく/好きだった/夢があった——三者三様の高専入学
―高専に進学したきっかけを教えてください。
中岡さん:地元にあった呉高専はかなり優秀な学校で就職率も良いと聞いていたのと、公立高校より試験日が早かったので受験を決めました。電気情報工学科に入学したのですが、正直ものづくりや電気工学などの分野に興味があったわけではなく、軽い気持ちで受験し、合格したので入学した、というのが実際のところです。

長野さん:私の場合は、小さい頃からものづくりが好きだったのがきっかけです。祖父が大工で、小さい頃は余っている木材で椅子をつくっていました。中学生になると電子部品を使ったものづくりや、ロボット工作キットを取り寄せてものづくりをするようになり、そのまま、好きなことにつながる鹿児島高専を志望しました。

藤田さん:私は、5つ上の兄が苫小牧高専に通っていたので、他の人よりも高専を身近に感じていたと思います。
あるとき、祖父が倒れて半身不随になり、そのときに祖父や祖父を支える医療関係者の方々の助けになれる方法がないかと考えるようになりました。すると兄から「高専には人工心臓の設計の研究をされている先生がいる」と聞き、「これだ!」と思ったんです。
結局、高専で人工心臓の研究をすることはなかったのですが、高専に入れば工学技術で医療福祉分野の人々の助けになれると思ったのが、最初のきっかけでした。
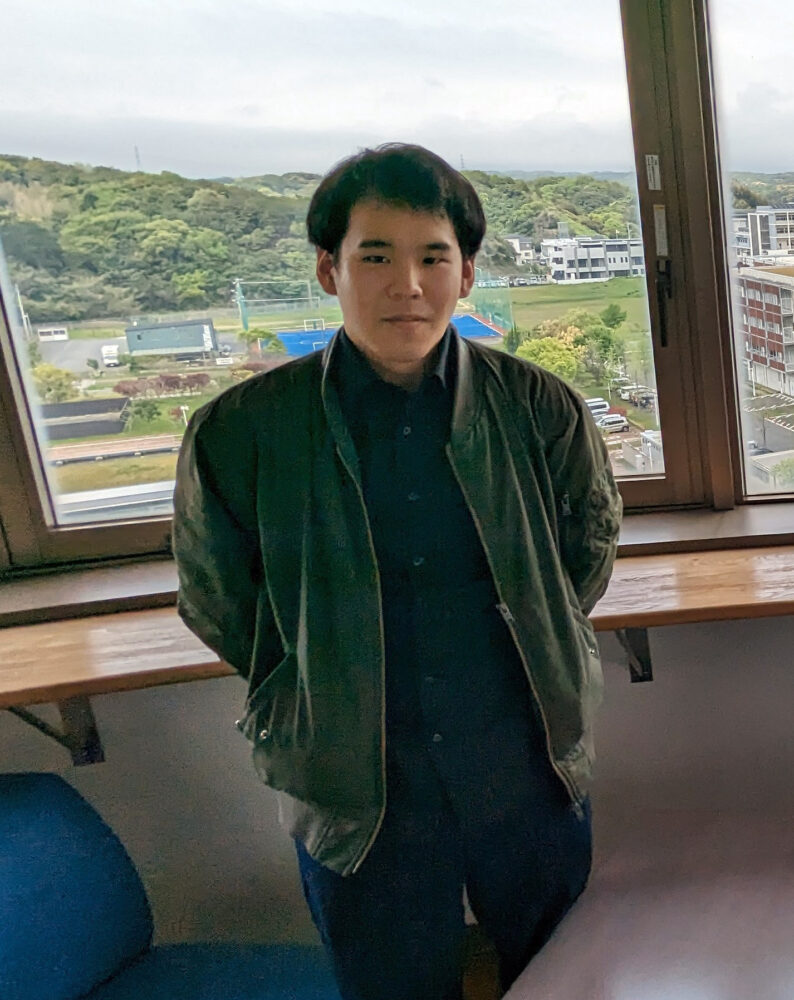
―高専での研究内容を教えてください。
中岡さん:電気回路や通信工学、トランジスタなどの電子工学について勉強し、研究室に配属されてからは、医療分野にも視野を広げて研究を行いました。というのも、高専で唯一電気的手法を使って医療の研究を行っている研究室があり、その研究内容を聞いて、面白そうだと思ったんです。
具体的に言うと、細胞から分泌される物質(エクソソーム)の内部情報を、電気泳動を使って同定することで、うつ病をはじめ病気を患った方を定量的に診断する研究でした。

長野さん:筋電義手に関する研究をしていました。筋電義手とは、手や前腕部分がない人がつけるロボットアームです。腕がない原因が後天的であっても先天的であっても、動かすことができます。この研究を始めたきっかけは、中学生のときにロボットアームを工作キットでつくって、ものを掴んで遊んでいたという経験からです。この経験や知識を生かして、人々の役に立つことができたらという思いで研究テーマに選びました。
専攻科では、本科で学んだことを元に、より付加価値の高い製品の設計・開発を行いました。例えば意識していた点で言うと、「求めやすい価格」「精度の高さ」などです。ただ、ものをつくるだけではなく、お客さんの立場になり、気持ちに寄り添った製品開発を目指していました。
藤田さん:私は高専に入学する前から、一貫して工学の中でも医療福祉分野と決めていたので、その分野の研究室に入りました。腰痛を研究テーマとし、レントゲン画像から腰のモデルを物理的に作成して、腰部への負荷の計測などをしていました。
介護師や看護師の方は腰痛になるリスクが高く、大体8割の方がなると言われています。ですので、間接的に医療福祉分野の方々の助けになるのではないかと思ったのが、腰痛に焦点を当てた理由です。

誰しもが持っている、今だから笑える失敗談
―高専時代の失敗談はありますか。
藤田さん:コンセントから電源を取って回路をつくる必要があったとき、電源ケーブルをコンセントに挿したままはんだをしていたことがありました。本来は絶対に挿したままにしてはいけない作業です。その時、指先がビリビリとしびれる感覚が何度かあって、今思うと感電していたのかもしれません。終わってから他の人に「コンセントに挿さったまま」だと教えられ、冷や汗をかきました。大きな事故にならなくて本当に良かったです。
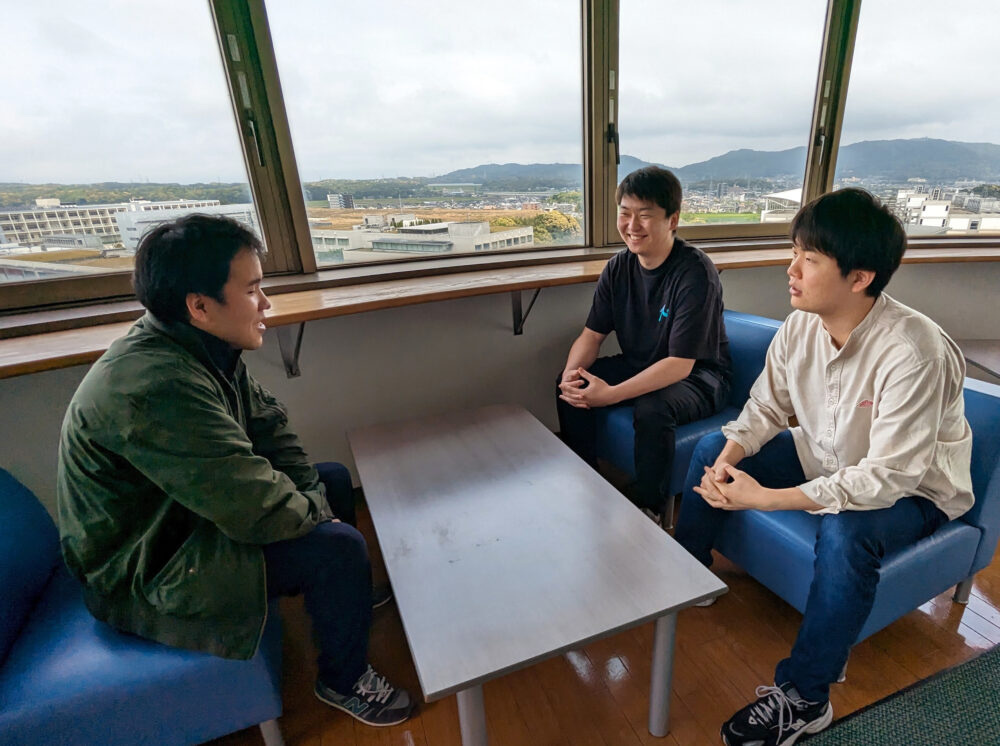
中岡さん:私も細かい失敗を言えばきりがないのですが、藤田さんと似たような経験で言うと、はんだをずっと付けっぱなしにしていて火事になりかけたことがあります。はんだでの失敗は、高専生にとってはあるあるなんでしょうか?
あと大きい失敗で言うと、高専4年生のときの大学への編入試験に失敗してしまったことです。高専出身の方ならわかってもらえると嬉しいのですが、高専生は化学をほぼ勉強しません。やはり物理や数学、あとは専攻分野にもよりますが、私の場合は電気が基本でした。ただ、(某大学の)大学編入試験の科目に化学があり、一から勉強を始めたようなものだったので、試験で点数を取れずに落ちてしまいましたね。
長野さん:私は勉強と部活の両立が難しく、中学生のときのようにうまくいかなかったことです。実験の時間が長引いて部活の練習に行けなかったり、土日は部活で試験勉強ができなかったりと、なかなか勉強にも部活にも身を入れることができず、どっちつかずの状態になっていました。部活は結局やめたのですが、3年生までは勉強にも力を入れることができませんでしたね。
テストもよく赤点を取っていた気がします。高専は普通高校よりも授業のペースが速いので、なかなかついていくのが難しかったんです。自分で学習したり、友人に聞いたりしていたのですが、知識が追いつかずに赤点を取ることはよくありました。
今考えると、赤点を取ったとしても再試験に受かればよく(※)、赤点のラインが高い場合もあるので、そこまでへこまなくてもよかったなと思います。同じように悩んでいる高専生の方がいれば、あまり気にしすぎずに再試験に望んでほしいです。
※先生によっては、再試験を行わない場合もあります。

―いろいろな失敗があるんですね。そのほかにもありますか。
長野さん:では、もう1つ暴露します(笑) あまり言うのは良くないかもしれませんが、九工大のオープンキャンパスに行くのを忘れてしまいました。結局はオンラインで九工大の先生にお話を伺うことができ、それが進学の1つの決め手になりました。そのような機会を設けていただけたことに感謝ですし、あのときしっかりと話を聞くことができて良かったと思います。
藤田さん:私は、九工大ではない他の大学への願書を出し忘れました……。ただ、本命の九工大に受かることができたので、今だから笑って話せる失敗談です。
九工大の大学院ならではの「自由でのびのび」とした実感
―大学院へ進学した理由と、その中でも九工大を選んだ理由は何だったのでしょうか。
中岡さん:まず、大学院への進学を決めたのは、高専4年生のときの研究室での研究が楽しく、続けたいと思ったからです。九工大を選んだ理由としては、インターンシップがきっかけでした。研究室の先生の関係でインターンシップに行くと、九工大は最先端の研究を行っていて、自然も多く、静かで集中できそうな環境だったことに魅力を感じました。
他にも候補の大学院はありましたが、自分にとって九工大はやりたい研究ができて、留学生も多くて多様性があり、自由にのびのびと研究ができると思ったのが理由です。
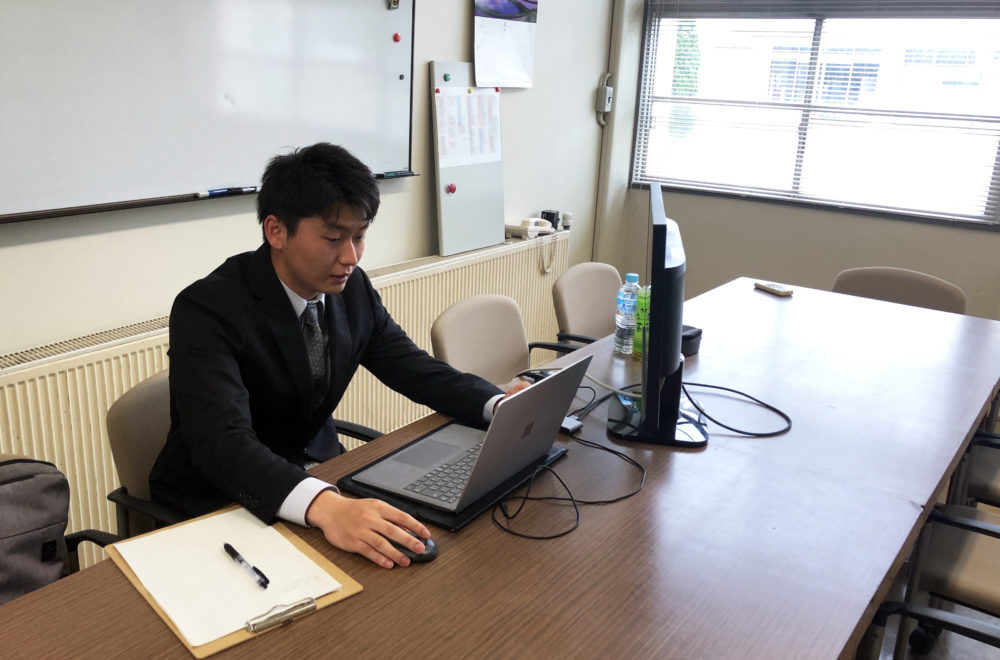
長野さん:私は、自分の将来の幅を狭めたくないと思い、専攻科で終わらず、大学院への進学を決めました。また、専攻科で思うような研究成果を得られず、より深く研究してみたいと思ったのも理由です。
私も中岡さんと同じように他の大学院も視野に入れていて、研究室の先輩に誘われていくつか見学に行ったことがあります。ただ、「研究がキツすぎるのを理由に泣いている」という先輩の話を聞き、「せっかく将来の幅を広げるために大学院に行くのなら、根を詰めずに自分に合った環境でのびのびと研究をしたい」と思いました。そして私にとって適した研究環境だと感じた九工大を選んだんです。
藤田さん:大学院に進んだ理由は、中岡さんと長野さんと一緒で、専攻科を終えてこのまま就職するのはもったいないという思いと、もっと研究をしたいという思いがあったからです。ただ、そのような思いはあったにせよ、実際はあまり深く考えず、気軽に進学を決めたような気がします。
九工大を選んだのは、専攻科で取り組んでいた研究の延長として研究ができると思ったことが大きな理由です。研究の対象者である介護士や看護師、ほかにもパーキンソン病などの疾患を抱えた方に対してのアプローチを、より現場に近い形で研究ができるのが魅力的でした。
あと、九工大の建物がある北九州学研都市内には、家具や計測器具が整備されているスマートライフケア共創工房があり、実際の介護現場に近い状態での模擬実験ができるんです。そのような設備があることも、九工大を選んだ理由の1つです。

―大学院への入学前後でギャップはありませんでしたか。
藤田さん:大学院に行く前は、自分の研究にのめり込んでいるような人が多いイメージでした。でも実際に入ってみると、多趣味だったり、いろんなことに挑戦していたりと、みんな私生活が充実していて、とっつきやすく優しい人が多かったですね。
中岡さん:たしかに、研究者は夜中まで研究に没頭しているイメージでした。でも、いざ九工大に来てみると、みなさん研究に熱を入れつつ、思ったよりも規則正しい生活を送っていらっしゃいましたね。
長野さん:入学前、大学院では先生に言われたことをただこなすというイメージだったのですが、実際には、先生に言われたことプラス自分でもしっかり考えて案を出して研究を進めなければいけない点にギャップを感じ、質の高さを感じました。また、中岡さんが入学の決め手として言っていた「自由度の高さ」も、入学してから実感しました。
あと、高専時代の自分の研究室では、他の人との研究以外での交流があまりなかったので、大学院でも自分の研究だけを進めて、人と関わる機会がないのかなと思っていたんです。しかし、実際には研究室の仲間と朝から夜まで一緒にいる中で、他の研究について聞いたり、食事に行ったりして仲を深めています。
―現在の高専生に向けて、高専出身の先輩として学生時代をより有意義にするためのアドバイスをお願いします。

中岡さん:私から言えるのは、「もっと高専の外に出ていろんな人と交流しましょう」ということです。もっと外に出ておけばよかったなと、実際に後悔しています。ただ、外に出て新たなコミュニティに入っていくのは難しいことかもしれませんが……。
藤田さん:私の高専時代の同期は、同じ通学電車の女子高生に話しかけて彼女をつくろうとしていましたよ(笑) まあこれはハードルが高いですが、恋愛という観点も含めて、学外に出ていろんな人と交流しましょうというのは良いアドバイスかもしれないですね。
中岡さん:そうですね。自発的に外に出ないと他の人との交流の機会がないので難しいですよね。なので、外に出ましょう。
藤田さん:同じ意見です。外に出ましょう!
長野さん:私もそう思います。学外でコミュニティをつくる方法で私のオススメはアルバイトです。ほとんどの高専でバイトに関するルールがあるとは思いますが、学外に出る手段としては最適です。それこそバイト先で彼氏・彼女が見つかることもありそうですよね。
中岡さん:たしかに、アルバイトは良いですね。多分ほとんどの高専では5年間クラスが一緒で、良くも悪くも井の中の蛙のような状態になってしまうことがあると思うんです。なので、クラスの外に出て、学外にも出て、もっといろんな環境でいろんな人と交流を深める。そうすることで、高専時代がより楽しいものになるのではと思います。
♦
今回は高専卒の九工大生3名に、主に高専時代のやらかし・思い出についてお話しいただきました。
次回の後編では、この3名が大学院に入って身につけた研究方法や、現役大学院生としてのアドバイスなどを掲載しています!
○九州工業大学 生命体工学研究科 公式LINE
九工大へ進学した高専生について詳しく知りたいという方や、学生生活や研究設備に興味のある方へ向けて、役立つ情報を配信しています。
登録はこちら(LINEアプリのダウンロードが必要です。)
○九工大インタビュー企画(全三部作)
第一部 「人前で緊張」「校長先生を怒らせる」——かつての未熟な高専生が世界を狙う研究者になるまで
第二部 願書を出し忘れた、感電した……高専時代の失敗や進学理由 ―九工大大学院 生命体工学研究科の高専卒学生に聞く(前編)―(この記事)
第三部 材料を応用した情報処理から介護・医療のアシスト装置まで……「研究に熱中できるキャンパス」の大切な特徴 ―九工大大学院 生命体工学研究科の高専卒学生に聞く(後編)
中岡 佑輔氏
Yusuke Nakaoka
- 九州工業大学大学院 生命体工学研究科 博士後期課程 生命体工学専攻 1年

2020年3月 呉工業高等専門学校 電気情報工学科 卒業
2022年3月 呉工業高等専門学校 専攻科 プロジェクトデザイン工学専攻 修了
2024年3月 九州工業大学大学院 生命体工学研究科 博士前期課程 人間知能システム工学専攻 修了
2024年4月より九州工業大学大学院 生命体工学研究科 博士後期課程 生命体工学専攻
藤田 亘氏
Wataru Fujita
- 九州工業大学大学院 生命体工学研究科 博士後期課程 生命体工学専攻 1年
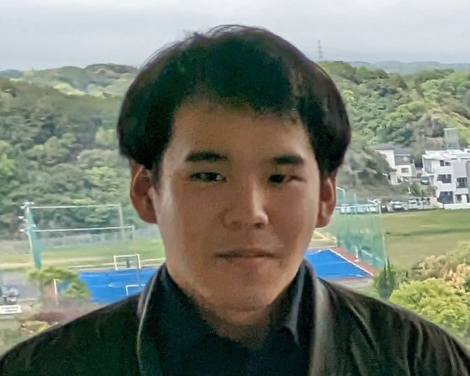
2020年3月 苫小牧工業高等専門学校 機械工学科(現・創造工学科 機械系) 卒業
2022年3月 苫小牧工業高等専門学校 専攻科 電子生産システム工学専攻(現・創造工学専攻) 修了
2024年3月 九州工業大学大学院 生命体工学研究科 博士前期課程 人間知能システム工学専攻 修了
2024年4月より九州工業大学大学院 生命体工学研究科 博士後期課程 生命体工学専攻
長野 聡一朗氏
Soichiro Nagano
- 九州工業大学大学院 生命体工学研究科 博士前期課程 生体機能応用工学専攻 2年

2021年3月 鹿児島工業高等専門学校 電子制御工学科 卒業
2023年3月 鹿児島工業高等専門学校 専攻科 機械・電子システム工学専攻 修了
2023年4月より九州工業大学大学院 生命体工学研究科 博士前期課程 生体機能応用工学専攻
アクセス数ランキング


- 自ら教え続け、研究し続ける“現役”の校長——立場が変わっても貫く「人づくり」の教育
- 函館工業高等専門学校 校長
清水 一道 氏

- 「学びたい」を原動力に、金融×ITの最前線へ。成長意欲が連鎖するNTTデータフォースでの、高専卒社員2人の姿
- NTTデータフォース株式会社 北海道・東北ビジネス本部 チーフ
小田中 拓馬 氏
NTTデータフォース株式会社 システム開発事業本部 本部長
有田 久幸 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡
- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師
盛田 有貴 氏
-300x300.jpg)
- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと
- 鹿児島工業高等専門学校 校長
上田 悦子 氏
-150x150.jpg)
- 「自分にしかできないこと」を追い求めたから、今がある。デザインで街を元気にする取り組みとは
- 石川工業高等専門学校 建築学科 教授・副校長(地域・国際連携)
道地 慶子 氏


- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む
- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教
久保田 翔大 氏

- 母校で社会実装に励む。地域の未来を見据え、本当に必要な支援ができるのは高専だからこそ
- 鳥羽商船高等専門学校 情報機械システム工学科 教授
江崎 修央 氏













