
大学卒業後は、普通高校の教員として勤務されていた釧路高専の浦家淳博先生。現在は「高専出身者のキャリア形成」や「子どもの理科離れ」に関心を持ち、教育・研究の両面に力を入れて取り組まれています。釧路高専に着任された経緯から現在の取り組み内容、今後の目標についてお話を伺いました。
「高校」教員から「高専」教員へ
―先生は、高専の教員になる前は、高校で教鞭をとられていたそうですね。

そうなんです。もともと、中学校の教員をしていた父の影響もあり、幼い頃から「教員になりたい」という思いがありました。もともと理数系が好きで、特に高校時代に学んだ「物理学」にロマンを感じていたことから、物理学を深く学べる地元・北海道の総合大学への進学を決めました。
大学卒業後はその夢をかなえ、網走市で高校の教員として勤めました。生徒や同僚にも恵まれ、非常にやりがいを持って仕事に取り組んでいました。
―そこから、なぜ釧路高専へ?

高校に勤めて4年が経った時、網走からの転勤が確定的になりまして、それも遠く離れた旭川市周辺の町らしいという情報が入ったんです。私はそれを聞いて、当時付き合っていた女性と遠距離恋愛になることがどうしても気になってしまって。
そんな折、彼女のお兄さんが釧路高専OBだったことから、次なる就職先として「高専もいいんじゃないかな.彼女ともそれほど離れないし」と思ったんです。
また、大学時代の経験から、研究の面白さについても知っていたので、「教育だけでなく、研究にも携わりたい」という思いもありました。
それから、釧路高専を訪問して話を聞くうちに、教員の方々の人柄や学校の雰囲気に惹かれ、釧路高専で教員になることを決めました。ちなみに、その時の付き合っていた女性というのが、現在の妻です。
―両方の教員を経験した先生から見て、高校と高専の大きな違いは何だと思いますか?

高校は、3年間という短い期間なので、卒業までの道筋が見えやすいという特徴があります。一方、高専は5年間あるので、1つのゴールに向かってモチベーションを保ち続けるというのはすごく難しいんですよね。その中でも、それぞれの目標に向かって、自立した行動が求められている。これは、学生指導をするうえで、難しさを感じている部分です。
その分、ちょっとした興味を持った時には、無制限のチャンスが転がっていると思うんです。たとえば、学校の図書館に置いてある専門書の数は高校の比ではありませんし、各分野に精通した研究者が身近にたくさんいるわけです。そういった先生方にお話を聞けば、アドバイスはもちろんのこと、学会や研究機関など、外部に連れて行ってもらえることもあります。
そこで、高校ではなかなか経験できないような社会体験をして、自身の人生観が変わったり、将来の可能性が広がるようなチャンスがたくさんあるのだと思います。
一般教科への配置転換を機に、キャリア教育の重要性に気づく
―これまでに、どのようなご研究をされましたか?

電子工学科の教員だった時には、結晶材料はどのように電流を流すかといった「物性」に関する研究をしていました。具体的には、温度差を与えると電流が流れるという「ゼーベック効果」というものがあります。
それを利用して、一定の温度差を生み出すことで発電が可能になるんです。たまたま北海道の東部は温泉が出ますし、冬には雪も降るので、自然のエネルギーから温度差を生み出せるという環境が整っているんですよね。そのため、実際に同僚の先生たちと共同で発電装置を作製し、実証研究を行っていました。
この研究はNHKからの取材を受け、BSでも放送されたこともあるんですよ。そうしたら、モンゴルと交流のある方から「温泉が出るモンゴルの地区で、同じような発電ができないか」というお話をいただいて。本格的な実証データを得るため、実際にモンゴルに行きました。
―モンゴルでの生活はどうでしたか?
モンゴル滞在中には、遊牧民の家である「ゲル」で過ごしました。ゲルについては忘れられない思い出があります。ゲルの中には中央に2本の柱があるのですが、柱と柱の間は神聖な空間で、人が通ることや物を渡すことは許されないんです。そのため、家の中では遠回りをして移動するなど、常に気を付けて生活していました。その名残からか、今でも2本の柱があるとその間を通ることに抵抗があります(笑)。
他にも、さまざまなしきたりや遊牧民伝統の飲み物も教えていただいて、研究以外にも貴重な経験をすることができました。
―現在は、どのような研究をされているのでしょうか。

本校に「専攻科」を新設する際に、私は一般教科の教員に配置転換することになりました。すると、学科の垣根を越えて多くの学生と接することになり、学生指導に関係する業務がかなり増えまして。材料物性だけでなく、学生のキャリア形成についての関心が徐々に強まっていったんです。
そして、内田由理子先生(香川高専詫間キャンパス)との出会いが大きな転機となりました。内田先生の共同研究者として、女性技術者というキーワードをテーマにして、さまざま取り組んでいます。
今は女性技術者の必要性がどんどん増していて、女子高専生が時代の先駆者としての役割を担っているんですよね。一方、理系女性の進路として保護者は医師・薬剤師などには好意的ですが、工学系はあまり好意的ではないのが事実です。また、女性というだけでなく「高専卒」というのは、普通高校・大学とはかなり毛色が違っており、卒業後の進路について、世間にあまり知られていないという現状もあります。ですから、女性技術者はどんな世界を歩むのかを調べ,広く伝えていく必要があると感じてきました。
取材した方々のキャリアの積み上げをロールモデルとして、これからは男子学生も含めてフィードバックし、また中学生などに伝えていく。これを社会的なキャリア教育システムとして整えることを目標に、研究を行っています。
「理科の面白さ」を伝えることで、地域活性化に貢献
―先生は、公開講座にも力を入れているのだとか。

まずは理工系について関心を持ち、視野を広げてほしいという気持ちから、子どもたちに理科の面白さを伝えるための公開講座を行っています。特に,2013年から小中学生対象の会員制通年公開講座である「エンジュニアクラブ」の主担当をしています。
ものをつくることの楽しさ,考えることの楽しさを伝えることを重視しています。また,この活動には、「科学ボランティア部」という部活動の学生にサポートをお願いしています。学生が学校で学んだことを学外で教える機会を設けることは、学生にとっても良い経験になると考えています。
―今後の目標を教えてください。

北海道東部は人口が年々減少している地域でもあります。若者がやりたいことのために地元を離れるのは仕方がありません。しかし、一度羽ばたいた後に、さらなる力を付けて戻り、地域を活性化させてほしいという思いも強くあります。
そのために、小中学生からの理科教育、キャリア教育にもっと力を入れていきたい。そして高専OB・OGや企業との連携を強めることで、学生のモチベーションも高めていければと考えています。
企業としてもそういった学生を受け入れることはプラスになると思いますし、その結果、釧路市としてもUターン人材を取り入れたまちづくりにつながっていく…。このように、理科教育やキャリア教育を通して、教育・行政・企業活動の循環を促すような体制づくりを目指していきたいと思っています。
浦家 淳博氏
Atsuhiro Uraie
- 釧路工業高等専門学校 創造工学科 一般教育部門 教授

1983年 北海道大学 理学部物理学科 卒業、北海道網走南ケ丘高等学校 教諭
1987年 釧路工業高等専門学校 電子工学科 助手
1997年 釧路工業高等専門学校 一般教科 助教授
2007年 北海道教育大学釧路校大学院 教科教育専修 理科教育専攻 修了、釧路工業高等専門学校 一般教科 教授
2016年より現職
釧路工業高等専門学校の記事



アクセス数ランキング


- 自ら教え続け、研究し続ける“現役”の校長——立場が変わっても貫く「人づくり」の教育
- 函館工業高等専門学校 校長
清水 一道 氏

- 「学びたい」を原動力に、金融×ITの最前線へ。成長意欲が連鎖するNTTデータフォースでの、高専卒社員2人の姿
- NTTデータフォース株式会社 北海道・東北ビジネス本部 チーフ
小田中 拓馬 氏
NTTデータフォース株式会社 システム開発事業本部 本部長
有田 久幸 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡
- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師
盛田 有貴 氏
-150x150.jpg)
- 「自分にしかできないこと」を追い求めたから、今がある。デザインで街を元気にする取り組みとは
- 石川工業高等専門学校 建築学科 教授・副校長(地域・国際連携)
道地 慶子 氏

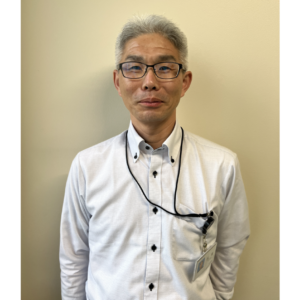
- 世の中で一番強い形は○○!? 12年間に及ぶ国内最難関のトンネル工事に挑む
- 清水建設株式会社 北海道支店 土木部 部長
松尾 勝司 氏

- 「研究が楽しい」「みんなで一緒にスタートが切れる」——高専生が進学先に奈良先端科学技術大学院大学を選んだ理由をご紹介
- 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 博士後期課程2年
浦上 大世 氏
奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成領域 博士後期課程1年
星川 輝 氏
奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 博士前期課程2年
山川 怜太 氏


- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力
- 日本郵船株式会社 一等航海士
川西 雄太 氏

-300x300.jpg)








