
現在、国立高専機構と防災科学技術研究所(防災科研)、国際科学振興財団が主催する「第4回高専防災減災コンテスト」が実施されています。これは、高専生が防災減災に関する地域の社会課題を取り上げ、その解決策と検証過程を発表・評価する取り組みです。本コンテストが始まった経緯や防災減災の課題、参加する高専生の変化、2026年1月24日(土)開催の最終審査会などについて、審査員を務めている防災科研の岩波越さん(研究主監)にお話を伺いました。
必ず成功しないといけない、わけではない
―高専防災減災コンテストの目的と設立背景について教えてください。
高専防災減災コンテストは、コンテストを通じて高専生が成長すること、若い力によって地域社会の災害対応力・回復力の向上に寄与することを目的としています。全国の高専生を対象として、防災減災に関わる地域の社会課題を解決するアイデアと、その検証過程を競います。

設立のきっかけとしては、防災科研が2016年にJST(国立研究開発法人科学技術振興機構)のイノベーションハブ構築支援事業に採択されたことが挙げられます。これにより、防災減災の分野で関係機関・企業などと協力しながらイノベーションを起こす基盤(ハブ)を構築していくことになりました。
そこで防災科研では、地域特性や利用者のニーズに応じた気象災害の予測情報を提供していくことで、気象災害を軽減していくことを目指し、自治体や研究機関などとの連携を進めていました。その連携先の一つが国立高専機構本部だったんです。それまでも個別の高専とは、夏場の気象災害について水・土砂防災研究部門と、雪氷災害について雪氷防災研究センターと共同研究を進めていたなど、つながり自体はありました。
そして、国立高専機構と2018年に連携・協力協定を結び、同年度に現コンテストの前身となる高専防災コンテスト(地域防災力向上チャレンジ)最終審査会を東京・一橋講堂で開催。その後はコロナによってオンライン開催となりましたが、2022年度に現在の高専防災減災コンテストにリニューアルしてからは対面開催に戻しました。高専防災コンテストのときと合わせると、通算8回目の開催となります。

―高専防災減災コンテストの魅力はどこにあるとお考えですか。
地域の防災減災に関する課題を報道や公開資料などに基づいて設定し、それを解決するアイデアを考え、実証していくプロセスを体験できるところです。このコンテストの特徴の一つとして、地域住民や関係機関・企業の方に聞き取り調査をして、アイデアに対する意見をもらうことを必須にしている点が挙げられます。これは防災科研での社会実装プロセスに近いものであり、それを経験できるのは魅力だと思います。
―審査のポイントを教えてください。
先ほど必須であるとお話しした聞き取り調査を含め、書類審査では以下の5点が挙げられます。
- 地域の特性や防災減災に関わる課題を把握しているか
- 解決するためのアイデアが独自の着眼点や新しい発想によるものか
- アイデアの検証方法の計画が具体的で、検証方法に必要な技術開発や科学的知見が盛り込まれているか
- 聞き取り調査の計画が適切に設定されているか
- 地域での普及や社会実装をどうイメージしているか
書類審査を通過したアイデア検証進出提案のチームには、防災科研の研究者や民間企業の方によるメンターサポートを受けながら、約半年間のアイデア検証を行っていただきます。そして、2026年1月24日(土)の最終審査会でアイデア検証によって実際にどうなったのかを発表いただき、事前に提出された最終報告資料の内容やプレゼンテーション、ポスターの出来栄えなどを評価することになります。

ただ、ここは本コンテストが始まった当初からの特徴だと思いますが、「必ず成功させてください」といったことはお伝えしていません。当初のアイデアが関係機関などへの聞き取りや、試作、実験などを通して変更になることはもちろん問題ないですし、課題が残ってしまった場合でも、しっかりとした理由が明示できれば評価をします。
―審査ポイントを決める際に重要視した思いは何ですか。
「地域」を重要視することを心掛けました。高専はほとんどの都道府県にあり、それぞれの地域とのつながりを形成しています。防災科研は国立研究開発法人ですので、最終的には日本全国のためになる研究をしていますが、研究成果を各地域に実装していくときに、全国の高専や国立高専機構本部との連携が良い効果を生むと考えています。
また今回から、アイデアの検証方法について「技術開発や科学的知見が盛り込まれているか」を審査ポイントとして明示しました。高専生らしい技術開発のスキルや考え方、取り組み方がはっきりとわかるよう、審査ポイントに追加させていただきました。
社会実装につながったアイデアも!
―通算8回開催されたコンテストで、高専生の取り組みに変化は感じられますか。
年々アイデアが高度になっていると思います。また、これまで運営事務局で工夫はしてきたものの、コンテストは単年度開催なので長い活動期間が確保できないのが難点なのですが、すでに取り組みが進んだ状態で応募するチームが増えてきたと思います。今回のアイデア検証進出提案チームには、特にそういうチームが多いと思いました。コンテストを8回続けてきたことで、高専側でも防災減災に関する取り組みを続けてくださる学生・先生が増えてきたのではないかと、継続の効果を感じています。
また、コンテスト後に実際に社会実装するチームが増えています。第1回、第2回の高専防災減災コンテストに出場した石川高専のチームのアイデアで「まちなかハザード標識」があります。この標識には、近くの災害時避難場所やそこまでの距離が記載されているほか、避難場所への地図が出てくるQRコードも掲載されており、自治体からの受託事業として電柱などに設置するに至りました。

―防災減災について、岩波さんが高専生に期待していることは何ですか。
日本が抱える防災減災の課題はたくさんあります。私自身、現在は研究主監という立場で防災科研の研究全般を統括する仕事をしていますが、元々は気象災害に関する研究をしていまして、防災減災に寄与できるよう取り組んできました。
現在の気象は極端になって、災害につながりやすくなっていると思います。例えば、1時間に雨量50ミリや80ミリといった短時間での強い雨は、1974年に運用を開始したアメダスの観測データを見ても、明らかに増えているんです。自分が子供のころは「夕立」という言葉が一般的でしたが、最近では、こういった短時間の強い雨が急に狭い範囲に集中して降って、道路冠水などを引き起こし、「ゲリラ豪雨」と呼ばれています。実は雪に関しても各地で観測史上最大の記録的豪雪が次々起きていまして、気象災害が激甚化しているのは確かです。
そんな中、線状降水帯の予測は防災減災の課題の一つとして挙げられます。先日の気象庁の発表によると、見逃し率(100%から捕捉率を引いた数値)が約29%で、的中率は約14%とのことでした。昨年に比べて率は良くなっていますが、気象災害が激甚化している現在において、気象予測の分野はまだまだ改善が必要です。防災科研が持っているデータなども使って予測方法の開発にぜひ取り組んでほしいと思っています。
また、避難所などでの電源確保も大きな課題になっています。避難所での通信やネットワーク、IT関係のアイデアは採用されつつあるのですが、その大元となる電気に対する課題については、まだまだ未解決のものが多いです。昨年度の第3回高専防災減災コンテストに出場した函館高専のチームは、船外機の電源を発電機として利用するアイデアで文部科学大臣賞を受賞しましたが、そういった電気・電源へのアプローチがなされたアイデアにも期待しています。

―最後に、2026年1月24日(土)開催の最終審査会について教えてください。
今回は北海道から沖縄までの10チームが一堂に集まります。会場はさまざまな学会や国際会議などが開催されている「つくば国際会議場」です。つくば駅から徒歩で行ける距離にあります。
高専生の発表に興味をお持ちの方や、高専への進学を検討されている中学生・保護者の方には、ぜひ現地で高専生たちの熱を感じてほしいですし、ポスターセッションなどでは高専生と交流することもできます。また、今回初めてライブ配信も実施しますので、現地に来られない関係者や全国の高専生には、配信でぜひご覧いただきたいです。
ちなみにですが、最終審査会はコロナでオンライン開催になって以降、最終提出資料としてチームでつくった7分の動画を流した後に、短いプレゼンテーションをしていましたが、今回からスライドを使った7分間程度のプレゼンテーションとなります。これまでより十分なプレゼンテーションの時間が確保されていますので、出場する高専生には、自分たちのアイデアと成果が、会場参加者、視聴者、私たち審査員に伝わるように、熱意を込めて発表してほしいですね。
◇
月刊高専ではアイデア検証進出提案に採択された10チームの中間報告を掲載しています。
こちらもぜひご覧ください。
◇
○イベント概要
【第4回高専防災減災コンテスト 最終審査会】
日時:2026年1月24日(土)11:30-17:00
場所:つくば国際会議場 中ホール 300
※最終審査会の申し込み開始時期は12月中旬を予定しています。
主催:独立行政法人国立高等専門学校機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、公益財団法人国際科学振興財団
後援:文部科学省、一般社団法人全国高等専門学校連合会、日本放送協会(NHK)
協賛:応用地質株式会社、株式会社関電工、三菱電機エンジニアリング株式会社
HP:https://www.bosai.go.jp/kosencon/contest_2025.html
アクセス数ランキング


- 自ら教え続け、研究し続ける“現役”の校長——立場が変わっても貫く「人づくり」の教育
- 函館工業高等専門学校 校長
清水 一道 氏

- 「学びたい」を原動力に、金融×ITの最前線へ。成長意欲が連鎖するNTTデータフォースでの、高専卒社員2人の姿
- NTTデータフォース株式会社 北海道・東北ビジネス本部 チーフ
小田中 拓馬 氏
NTTデータフォース株式会社 システム開発事業本部 本部長
有田 久幸 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡
- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師
盛田 有貴 氏
-150x150.jpg)
- 「自分にしかできないこと」を追い求めたから、今がある。デザインで街を元気にする取り組みとは
- 石川工業高等専門学校 建築学科 教授・副校長(地域・国際連携)
道地 慶子 氏

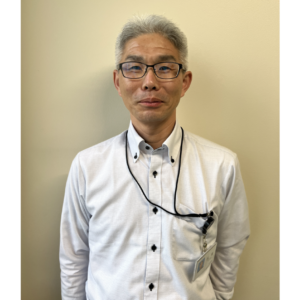
- 世の中で一番強い形は○○!? 12年間に及ぶ国内最難関のトンネル工事に挑む
- 清水建設株式会社 北海道支店 土木部 部長
松尾 勝司 氏

- 「研究が楽しい」「みんなで一緒にスタートが切れる」——高専生が進学先に奈良先端科学技術大学院大学を選んだ理由をご紹介
- 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 博士後期課程2年
浦上 大世 氏
奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成領域 博士後期課程1年
星川 輝 氏
奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 博士前期課程2年
山川 怜太 氏


- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力
- 日本郵船株式会社 一等航海士
川西 雄太 氏

-300x300.jpg)








